ここ私の席ですが [海外文化]
ジョージア駐日大使が電車内の優先席に腰掛ける動画をツイッターに上げ、非難のコメントが相次ぐ出来事があった。大使はこれに対し、空いている車内で優先席に座ることに問題はなく「大切なのは、必要とする方が来たときに率先して譲る精神です」と反論した。この顛末で思い出したことがある。
フランスで高速鉄道(TGV)に乗り込むとき、たまにこんなことが起こる。自分の予約した座席で、見知らぬ女性が一人悠然と読書している。慌てず騒がず「ここ私の席ですが」と呟くと、彼女はニコリとほほ笑んで別の席に移動する。TGVは全席指定なので、彼女はもちろん別の席に切符を買ってある。だが自席より気に入った座席を見つけると、とりあえず陣取って誰も来なかったらラッキー、誰か来たら自分の席に戻ればいいだけ、という算段なのである。西洋的な合理主義とでも呼ぶべきか。
日本の新幹線だと滅多にそういうことは起こらない。勘違いで違う席に座ってしまい指摘されることはあるかもしれないが、指摘する方もされる方もちょっと気まずい。日本は見知らぬ他人どうしが言葉を交わす事態をなるべく回避しようとする奥ゆかしい文化がある。スーパーのレジで「レジ袋が入用な方はこれをカゴに入れてください」のような札が用意されていることがあって、レジ袋下さいという一言すら店員にかけたくない人にわざわざ配慮しているのだ。まして「そこ私の席ですが」なんて見ず知らずの人に言いたくないし、逆に他人にそう言わせるのも忍びない。
 「空いている優先席」問題は、席を必要としている人に譲るか否かという道徳論に陥りがちだが、問題の本質はたぶん少し違うところにある。車内が空いているのに優先席を遠巻きにする美学は、他人同士の距離感をできるかぎり保っておきたい日本文化の一部なのである。席を譲るのは純粋な善意の行為なのに、なぜか漠然とした気恥ずかしさを感じる日本人は案外多いのではないか?「どうぞ」「どうも」で結ばれる他人どうしの邂逅によって、つかのま暗黙のタブーを破ったかのような罪の意識が胸をよぎるからである。
「空いている優先席」問題は、席を必要としている人に譲るか否かという道徳論に陥りがちだが、問題の本質はたぶん少し違うところにある。車内が空いているのに優先席を遠巻きにする美学は、他人同士の距離感をできるかぎり保っておきたい日本文化の一部なのである。席を譲るのは純粋な善意の行為なのに、なぜか漠然とした気恥ずかしさを感じる日本人は案外多いのではないか?「どうぞ」「どうも」で結ばれる他人どうしの邂逅によって、つかのま暗黙のタブーを破ったかのような罪の意識が胸をよぎるからである。
そんな苦手意識の反動で、たとえガラガラな車内でも若い健常者が優先席に腰掛けていると厚顔無恥なヤツと思いがちだ。ジョージア駐日大使はこれを「理屈のない不要な圧力」と一刀両断しているが、問題の根はもう少し雅で奥が深い。肝心なのは譲る心だという大使の主張は何ら間違っていないと思うが、在日経験の長い彼すら日本文化の機微を理解するのは容易でないようである。
フランスで高速鉄道(TGV)に乗り込むとき、たまにこんなことが起こる。自分の予約した座席で、見知らぬ女性が一人悠然と読書している。慌てず騒がず「ここ私の席ですが」と呟くと、彼女はニコリとほほ笑んで別の席に移動する。TGVは全席指定なので、彼女はもちろん別の席に切符を買ってある。だが自席より気に入った座席を見つけると、とりあえず陣取って誰も来なかったらラッキー、誰か来たら自分の席に戻ればいいだけ、という算段なのである。西洋的な合理主義とでも呼ぶべきか。
日本の新幹線だと滅多にそういうことは起こらない。勘違いで違う席に座ってしまい指摘されることはあるかもしれないが、指摘する方もされる方もちょっと気まずい。日本は見知らぬ他人どうしが言葉を交わす事態をなるべく回避しようとする奥ゆかしい文化がある。スーパーのレジで「レジ袋が入用な方はこれをカゴに入れてください」のような札が用意されていることがあって、レジ袋下さいという一言すら店員にかけたくない人にわざわざ配慮しているのだ。まして「そこ私の席ですが」なんて見ず知らずの人に言いたくないし、逆に他人にそう言わせるのも忍びない。
 「空いている優先席」問題は、席を必要としている人に譲るか否かという道徳論に陥りがちだが、問題の本質はたぶん少し違うところにある。車内が空いているのに優先席を遠巻きにする美学は、他人同士の距離感をできるかぎり保っておきたい日本文化の一部なのである。席を譲るのは純粋な善意の行為なのに、なぜか漠然とした気恥ずかしさを感じる日本人は案外多いのではないか?「どうぞ」「どうも」で結ばれる他人どうしの邂逅によって、つかのま暗黙のタブーを破ったかのような罪の意識が胸をよぎるからである。
「空いている優先席」問題は、席を必要としている人に譲るか否かという道徳論に陥りがちだが、問題の本質はたぶん少し違うところにある。車内が空いているのに優先席を遠巻きにする美学は、他人同士の距離感をできるかぎり保っておきたい日本文化の一部なのである。席を譲るのは純粋な善意の行為なのに、なぜか漠然とした気恥ずかしさを感じる日本人は案外多いのではないか?「どうぞ」「どうも」で結ばれる他人どうしの邂逅によって、つかのま暗黙のタブーを破ったかのような罪の意識が胸をよぎるからである。そんな苦手意識の反動で、たとえガラガラな車内でも若い健常者が優先席に腰掛けていると厚顔無恥なヤツと思いがちだ。ジョージア駐日大使はこれを「理屈のない不要な圧力」と一刀両断しているが、問題の根はもう少し雅で奥が深い。肝心なのは譲る心だという大使の主張は何ら間違っていないと思うが、在日経験の長い彼すら日本文化の機微を理解するのは容易でないようである。
返品天国のクリスマス [海外文化]
 アメリカでブラックフライデーと言えば、感謝祭(Thanksgiving)に続く大セールの日である。11月の第4木曜日、親族が集まってターキーを食べながらテレビでまったりとアメフト観戦するのが感謝祭の王道だが、その翌日は早起きして開店と同時に超特売品めがけて突っ走る。Black Tuesdayなら1929年の大恐慌を象徴する株価大暴落の日だが、火曜日が金曜日に代わるだけで意味合いがガラリと変わるのが面白い。フライデーの方のブラックとは、セールが繁盛して店が黒字になるからということだ。いつ頃からか、日本でもこれにあやかってブラックフライデーを謳うセールをよく目にするようになった。本来は感謝祭とセットのはずだから、セールだけぶち上げるのは単なる便乗商法のような気がしないでもない。
アメリカでブラックフライデーと言えば、感謝祭(Thanksgiving)に続く大セールの日である。11月の第4木曜日、親族が集まってターキーを食べながらテレビでまったりとアメフト観戦するのが感謝祭の王道だが、その翌日は早起きして開店と同時に超特売品めがけて突っ走る。Black Tuesdayなら1929年の大恐慌を象徴する株価大暴落の日だが、火曜日が金曜日に代わるだけで意味合いがガラリと変わるのが面白い。フライデーの方のブラックとは、セールが繁盛して店が黒字になるからということだ。いつ頃からか、日本でもこれにあやかってブラックフライデーを謳うセールをよく目にするようになった。本来は感謝祭とセットのはずだから、セールだけぶち上げるのは単なる便乗商法のような気がしないでもない。自分ですっかり忘れていたが、以前のブログ『コロラドの☆は歌うか』復刻企画を不定期でやっている。今回は第3弾として「返品天国のクリスマス」を再掲しようと思う。ブラックフライデーのCMを見ていてふと思い出した、米国滞在時のささやかなエピソードである。
小さい頃クリスマス・プレゼントといえば、欲しいおもちゃを一つだけ選んでサンタさん (か両親かは結果論上どうでもよろしい)に託したものでした。私の小学生時代は家庭向け電子ゲームが出回り始めた頃で、友達が持っていたインベーダーゲーム(死語)欲しさに狂おしい日々を送り、12月25日の朝ついに枕元にゲームの箱を発見した嬉しさはとても言葉では言い表せません。日本に比べキリスト教の浸透度が遥かに強いここアメリカのクリスマスは、もちろん年間を通じ最大の祭典の一つであることに変わりはありませんが、 商業化の徹底度においてもまた他の追随を許さぬ凄まじさがあります。クリスマスに先立ち一ヶ月に渡って繰り広げられるクリスマス商戦はエスカレートの一途を辿っています。その火蓋が切って落とされる感謝祭翌日には、大手スーパーが軒並み大セールに打って出ることがもはや伝統と化し、品数限定の目玉商品を狙って朝の5時から人々が列を作ります。
渡米した年の12月25日、知り合いのアメリカ人夫婦がクリスマス・ディナーに招いてくれました。そのお宅の子供夫婦と孫が全員集合した賑やかなパーティで、なかなか楽しかったのですが驚いたのはプレゼントの数です。天井まで届くかという巨大なツリーの袂には、大小さまざまの無数のギフト・ボックスが山積みになっていました。それを子供たちが片っ端から開けていき、出てきたプレゼントをしばし眺めたかと思うと次の箱のラップをびりびりと破き始めます。その光景は、心待ちにしていた贈り物をついに手に取った子供というより、ベルトコンベアの前で黙々と作業をこなす労働者を思わせました。彼らのもう片方の祖父母の家では輪をかけて大量のプレゼントが待っていると聞いたときには、思わず言葉を失ったものです。
アメリカ人のクリスマスプレゼントに対する価値観は、基本的に「質より量」志向であります。『賢者の贈り物』を書いたオー・ヘンリーはアメリカ人だったはずですが、 あのつましい美学はどこへやら、毎年クリスマス時期になると誰も欲しがらないガラクタが大量に流通しては片端から消費されていきます。
ただ厳密に言えば、実際に「消費」されているとすら限りません。というのは、クリスマスが過ぎるとあちこちのスーパーのカスタマー・センターに長蛇の列ができ、返品する品物を両手一杯に抱えた人々でごった返すからです。 ここアメリカは消費者天国で、レシートさえあればたとえ開封されていようが使われていようが、大抵のものは返品が可能です。返品できるのは買った当人に限りません。ご丁寧にもギフト・レシートなるものが存在し、プレゼントが気に入らなければ添えられたその紙切れと一緒に購入店(か同じチェーンの最寄店)に行くと、即座に交換ないし換金することができます。贈り物を選んでくれた相手に失礼のような気もするのですが、プレゼントにギフトレシートを付けること自体、贈った当人が初めから返品の可能性を想定していることになります。
アメリカ人にとってクリスマスプレゼントはいまや、経済的見地から見事に合理化された形式的な儀式に過ぎないのかもしれません。バーゲンでなければ誰も買わないようなプレゼントを次々と開封するクリスマスの米国人は、印刷済みの近況報告しかない年賀状の山をめくり続ける元旦の私たちとある意味でよく似ています。
ポール・オースターの短編に『オーギー・レンのクリスマス・ストーリー』という作品があります。クリスマスストーリーのネタに困った作家が行きつけのタバコ屋で愚痴ったところ、店の主人オーギーがとっておきの実話を教えてやると申し出ます。街角で日々定点観測の写真を撮り溜める風変わりな趣味を持つオーギーは、昼飯代と引き換えにこんな体験談を語って聞かせます。
ブルックリンでタバコ屋を営むオーギーは、一人きりで迎えたクリスマスの朝にふと、万引き少年が落として行った財布を返しに届けることを思いつきます。免許証の住所を頼りに訪ねたアパートで出会ったのは、その少年の祖母でした。目の見えないこの老女は、オーギーを久々に帰宅した孫と思い込み大喜びをします。成り行き上オーギーは孫のふりをする羽目になり、近所の店で食材を調達して戻ってくると祖母はひそかに取って置いたワインを持ち出し、二人きりのクリスマス・ディナーがささやかに開かれます。
オーギーはしかし、件の孫息子の仕業と思われる盗品のカメラがアパートのバスルームに積まれているのを見つけてしまいます。どういう出来心かそのカメラを一つ失敬して帰ったオーギーは後に罪悪感を感じ、数ヵ月後未使用のカメラを返しに再び老女のアパートを訪れます。だがその部屋は既に別人の住処となっており、老女の足取りは途絶えていました。持ち帰ったカメラを持て余したオーギーは、まるで罪滅ぼしのように街角を行き交う人々を撮り続ける日課を自らに課すようになったのです。
飽食の米国社会とは無縁の切なさに満ちたこの物語は、しかしこの国の現実の暗部を正確に切り取っています。オーギーがクリスマスの日に自分自身に贈る盗品のカメラは、もはや物質的な価値しか持たなくなったクリスマス・プレゼントの究極のメタファーであり、不埒な孫の帰りを待つ貧しい祖母の一途な想いと鋭い対照をえぐり出しています。その文脈の延長には、オーギーがカメラを返しに行くシーンが返品天国アメリカにあっていっそう象徴的な意味を帯びています。『オーギー・レンのクリスマス・ストーリー』は、コマーシャリズムで染まったこの国の12月25日を、社会の裏側から静かに皮肉った辛口の御伽噺と読むこともできます。
つい昨年(注:2004年)のクリスマス、以前招いてくれた一家が再度私たちを招待してくれました。巨大なツリーと莫大な量のギフト・ボックスは相変わらずでしたが、プレゼントの山に混じって一枚の絵がそっと置いてあることに気がつきました。 ワニをコミカルに描いたその絵は、落ち着いた緑を基調としたポップで可愛らしい作品です。誰への贈り物かこっそり聞いてみると、なんと小学生のサムが祖父母のために描いた自作だと聞いて驚きました。彼の画才にも脱帽しましたが、それ以上に絵を受け取る祖父母はきっと高価な名画を贈られるよりもずっと嬉しかっただろうと思います。孫とクリスマスを祝うために盲目の祖母が大事に取っておいたワインのように、サム君のワニの絵はどんな高額のギフト・レシートも及ばぬ、尊い贈り物だったに違いありません。
※初出:『コロラドの☆は歌うか』番外編2005年2月26日付 一部加筆修正
素晴らしい発表をありがとうございます [海外文化]
日本で開かれた国際会議に出ていて気付いたことがある。講演者の発表につづき質問に立った日本人が、決まって律儀に感謝の言葉で切り出すのだ。
論文のレビュー(査読)をしていて似たような状況に出会うことがある。丁寧なコメントをつけてくれたレビュワーに著者が回答の冒頭で一言礼を述べることは普通にある。しかし(アジア系の著者に多いのだが)過剰なくらいThank youが連発される回答文書を見かけることが少なからずある。数十項目に及ぶ一問一答がすべて判を押したように「Thank you for your comment」の決まり文句で始まっていて面食らったこともある。形式的な謝辞や賛辞は乱発すると誠意が失われ逆に印象が悪化することに、思いが至らなかっただろうか。いちど私が査読した論文で、別のレビュワーが再査読の際に「この著者は表向き礼儀正しいが口先だけで、こちらの改訂コメントを軒並みスルーしている」と怒りのリジェクト宣言を突きつけた現場を目撃したことがある。
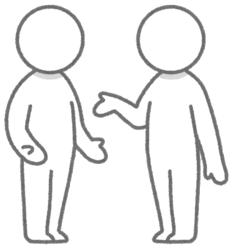 日本はもともとあまり議論をしたがらない文化圏だと言われる。人と違う意見を持つことに漠然とした恐怖感をもち、他人の意見に公然と異を唱えると「空気を読めない」と受け止められがちな風土がある。ただし研究者は特異な人種で、根っからの議論好きで相手の主張に反駁することを厭わない人も多い。だが面白いことに、慣れない英語を話す局面になると日本人らしい奥ゆかしさが急浮上する場面をしばしば見かける。「Thank you for your nice presentation」はたぶんその一例で、本当にナイスなプレゼンだったかどうかはさておき、質問はしますが挑発的な意図はないんですと暗に予防線を張っているのだ。
日本はもともとあまり議論をしたがらない文化圏だと言われる。人と違う意見を持つことに漠然とした恐怖感をもち、他人の意見に公然と異を唱えると「空気を読めない」と受け止められがちな風土がある。ただし研究者は特異な人種で、根っからの議論好きで相手の主張に反駁することを厭わない人も多い。だが面白いことに、慣れない英語を話す局面になると日本人らしい奥ゆかしさが急浮上する場面をしばしば見かける。「Thank you for your nice presentation」はたぶんその一例で、本当にナイスなプレゼンだったかどうかはさておき、質問はしますが挑発的な意図はないんですと暗に予防線を張っているのだ。
欧米人に「空気を読む」という概念は希薄なので、異を唱えられた方もそれを個人的挑発とは受け止めない。それでも、彼らと同じ土俵でアグレッシブな討論に臆せず入っていくのは、日本で生まれ育った私たちにはハードルが高い。その「ビビり感」がThank you連発の心理的背景にある気がする。
Thank you very much Professor Smith for your nice presentation. My question is ...これがもしアメリカ人なら、大抵もっとくだけてこうなる。
Bill, great talk. I'm just wondering...褒め方に文化的な温度感にちがいがあるのは当然で、日本人は概して謙虚で礼儀正しい。しかし私が講演者なら、Thank you very muchよりシンプルにgreat talkと言われた方が、真心がこもって嬉しい。
論文のレビュー(査読)をしていて似たような状況に出会うことがある。丁寧なコメントをつけてくれたレビュワーに著者が回答の冒頭で一言礼を述べることは普通にある。しかし(アジア系の著者に多いのだが)過剰なくらいThank youが連発される回答文書を見かけることが少なからずある。数十項目に及ぶ一問一答がすべて判を押したように「Thank you for your comment」の決まり文句で始まっていて面食らったこともある。形式的な謝辞や賛辞は乱発すると誠意が失われ逆に印象が悪化することに、思いが至らなかっただろうか。いちど私が査読した論文で、別のレビュワーが再査読の際に「この著者は表向き礼儀正しいが口先だけで、こちらの改訂コメントを軒並みスルーしている」と怒りのリジェクト宣言を突きつけた現場を目撃したことがある。
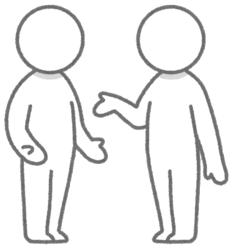 日本はもともとあまり議論をしたがらない文化圏だと言われる。人と違う意見を持つことに漠然とした恐怖感をもち、他人の意見に公然と異を唱えると「空気を読めない」と受け止められがちな風土がある。ただし研究者は特異な人種で、根っからの議論好きで相手の主張に反駁することを厭わない人も多い。だが面白いことに、慣れない英語を話す局面になると日本人らしい奥ゆかしさが急浮上する場面をしばしば見かける。「Thank you for your nice presentation」はたぶんその一例で、本当にナイスなプレゼンだったかどうかはさておき、質問はしますが挑発的な意図はないんですと暗に予防線を張っているのだ。
日本はもともとあまり議論をしたがらない文化圏だと言われる。人と違う意見を持つことに漠然とした恐怖感をもち、他人の意見に公然と異を唱えると「空気を読めない」と受け止められがちな風土がある。ただし研究者は特異な人種で、根っからの議論好きで相手の主張に反駁することを厭わない人も多い。だが面白いことに、慣れない英語を話す局面になると日本人らしい奥ゆかしさが急浮上する場面をしばしば見かける。「Thank you for your nice presentation」はたぶんその一例で、本当にナイスなプレゼンだったかどうかはさておき、質問はしますが挑発的な意図はないんですと暗に予防線を張っているのだ。欧米人に「空気を読む」という概念は希薄なので、異を唱えられた方もそれを個人的挑発とは受け止めない。それでも、彼らと同じ土俵でアグレッシブな討論に臆せず入っていくのは、日本で生まれ育った私たちにはハードルが高い。その「ビビり感」がThank you連発の心理的背景にある気がする。
追悼エリザベス女王 [海外文化]
 大学生の頃、当時留学していた友人を訪ねてイギリスを旅行した。ロンドンでは自然史博物館にハマり、ストーンヘンジに行く途中に泊まったソールズベリーでは街の教会で誰かが練習していたパイプオルガンの荘厳さに圧倒された。ソールズベリーで宿泊したB&Bで、部屋のいたるところに王室の肖像写真が掲げられていたのを覚えている。日本の民宿で皇室関連の写真が並んでいるのを見たことはないので、英国初体験の若造にとっては新鮮な驚きだった。
大学生の頃、当時留学していた友人を訪ねてイギリスを旅行した。ロンドンでは自然史博物館にハマり、ストーンヘンジに行く途中に泊まったソールズベリーでは街の教会で誰かが練習していたパイプオルガンの荘厳さに圧倒された。ソールズベリーで宿泊したB&Bで、部屋のいたるところに王室の肖像写真が掲げられていたのを覚えている。日本の民宿で皇室関連の写真が並んでいるのを見たことはないので、英国初体験の若造にとっては新鮮な驚きだった。その後イギリスには仕事で何度か訪れている。6年前の出張の際、帰国日に時間が空きバッキンガム宮殿まで散歩したことがある。すると宮殿前の広場が見物人でごった返している。何が行われているのか首を伸ばしてみたが、何も見当たらない。そばにいたどこかの国のツアーガイドに何事かと聞いてみたが、よくわからないが何かが起こるらしい、というまるで要を得ない返答が返ってきた。しばらく待っていると、やがて礼装に身を包んだ騎馬隊と歩兵隊の連隊が現れ、恭しく引かれた空の馬車が宮殿に吸い込まれていった。後から知ったがその一週間ほど後に宮殿でエリザベス女王90歳の祝賀行事が開かれたので、おそらくそのリハーサルの一部だったのではないかと思う。
ダイアナ妃事故死直後の英国王室をフィクションで描いた『クィーン』という映画があった。元皇太子妃の悲劇に冷ややかなエリザベス女王に世間の批判が集まり、王室廃止論まで飛び出した頃の話だ。映画の中で、宮殿前に追悼に集まる群衆の前に現れる女王のシーンがある。刺々しい視線に満ちた微妙な空気に戸惑うエリザベス女王に、一人の少女が小さな花束を差し出して言う。
「これはあなたのために、女王様。」王室の伝統を守りつつ家族の一員であり一人の人間であった女王の苦悩と孤独は、いかばかりだったか。七十年という長大な在位期間を全うしたエリザベス女王の献身に改めて深い敬意を覚える。
女王は死去の二日前、トラス新首相任命の際にカメラの前に姿を見せた。もし任命前に亡くなっていたらいろいろややこしかったのではと思うと、これだけは自身最期の公務として果たさなければという強いご意志だったのか。人生の引き際まで気高く責任感に満ちた方だったのだと思う。
まさかの味噌ラーメン [海外文化]
2年半ぶりの海外出張でアメリカに来ている。国際線の機内はほぼ満席だったが、ロサンジェルス空港の入国審査はガラガラだった。同時刻帯に到着した国際線が他になかったということで、コロナ前のLAX空港ではたぶんちょっと考えられなかったことだ。航空会社が需要ぎりぎりまで便数を絞っているということである。実際、私も当初予約したサンフランシスコ便が丸ごとキャンセルされ、ロス経由に振り替えられた次第だ。
 乗継の空港ラウンジでのこと。セルフの軽食レーンに「Ramen Bar」という一角がある。麺にトッピング(豆腐・シイタケ・ニンジン・ハラペーニョといった個性的なラインナップ)を自由に組み合わせて、ラーメンスープをかけるだけのシンプルな仕様だ。ところが肝心のスープがない。たまたまそばにいたスタッフに訊くと、「それよ!」と指さす先にある鍋はどう見てもMiso Soupと書いてある。この味噌汁は具が入っていなかったので、確かにラーメンと合わせるために用意されたようだ。
乗継の空港ラウンジでのこと。セルフの軽食レーンに「Ramen Bar」という一角がある。麺にトッピング(豆腐・シイタケ・ニンジン・ハラペーニョといった個性的なラインナップ)を自由に組み合わせて、ラーメンスープをかけるだけのシンプルな仕様だ。ところが肝心のスープがない。たまたまそばにいたスタッフに訊くと、「それよ!」と指さす先にある鍋はどう見てもMiso Soupと書いてある。この味噌汁は具が入っていなかったので、確かにラーメンと合わせるために用意されたようだ。
「味噌ラーメンのつもりですかね」というのが日本人の同僚の意見だったが、なるほどそうかもしれない。きっとどこかで味噌ラーメンという言葉を聞いたシェフが、アメリカ人ならだれでも知っている日本食「味噌汁」と「ラーメン」を連想し「それだ!」と膝を打ってしまったのが運の尽きだった。味噌汁に縮れ麺の入った食べ物を想像してみてほしいが、残念な一品である。シングルのトップ選手を二人を連れてくれば最強のダブルスが組めるかと言えば、話はそう簡単ではないのである。
さてアメリカが日本よりマスク率が低いのは想像通りだったが、屋内ではそこそこマスク姿を見かけるので、ここでも完全に脱パンデミックのムードと言うわけでもない。人口当たりの新規感染者数ではもっか日本はアメリカの三倍近い水準にあるようで、数字の上ではより安全な国に来たわけだが、感染してしまうと帰国できないので気を引き締めたい。
 乗継の空港ラウンジでのこと。セルフの軽食レーンに「Ramen Bar」という一角がある。麺にトッピング(豆腐・シイタケ・ニンジン・ハラペーニョといった個性的なラインナップ)を自由に組み合わせて、ラーメンスープをかけるだけのシンプルな仕様だ。ところが肝心のスープがない。たまたまそばにいたスタッフに訊くと、「それよ!」と指さす先にある鍋はどう見てもMiso Soupと書いてある。この味噌汁は具が入っていなかったので、確かにラーメンと合わせるために用意されたようだ。
乗継の空港ラウンジでのこと。セルフの軽食レーンに「Ramen Bar」という一角がある。麺にトッピング(豆腐・シイタケ・ニンジン・ハラペーニョといった個性的なラインナップ)を自由に組み合わせて、ラーメンスープをかけるだけのシンプルな仕様だ。ところが肝心のスープがない。たまたまそばにいたスタッフに訊くと、「それよ!」と指さす先にある鍋はどう見てもMiso Soupと書いてある。この味噌汁は具が入っていなかったので、確かにラーメンと合わせるために用意されたようだ。「味噌ラーメンのつもりですかね」というのが日本人の同僚の意見だったが、なるほどそうかもしれない。きっとどこかで味噌ラーメンという言葉を聞いたシェフが、アメリカ人ならだれでも知っている日本食「味噌汁」と「ラーメン」を連想し「それだ!」と膝を打ってしまったのが運の尽きだった。味噌汁に縮れ麺の入った食べ物を想像してみてほしいが、残念な一品である。シングルのトップ選手を二人を連れてくれば最強のダブルスが組めるかと言えば、話はそう簡単ではないのである。
さてアメリカが日本よりマスク率が低いのは想像通りだったが、屋内ではそこそこマスク姿を見かけるので、ここでも完全に脱パンデミックのムードと言うわけでもない。人口当たりの新規感染者数ではもっか日本はアメリカの三倍近い水準にあるようで、数字の上ではより安全な国に来たわけだが、感染してしまうと帰国できないので気を引き締めたい。
ハリウッドの大統領 [海外文化]
ロシア国内ではプーチン大統領の支持率が8割を超えているという。思ったことを率直に言えない厳しい状況とは言え、独立系メディアの調査ですらプーチン大統領の盤石な人気は揺るがない。祖国の蛮行を直視する痛みに耐えられず、耳に心地よい国営放送のプロパガンダに浸る。2割と8割を隔てる壁は、その誘惑の強さを意味しているのだろうか?
もちろん、それはロシアの人々だけに起こる問題ではない。今回は『コロラドの☆は歌うか』復刻企画の第2弾、2003年イラク戦争突入に踏み切ったアメリカで米国人の愛国心について考えたコラムを再掲したい。
(2003年)3月23日、ハリウッドでアカデミー賞の発表式典が開かれた。 日本では『千と千尋の神隠し』の長編アニメーション部門受賞がもっぱら話題を集めた(と思う)が、 今年の式典で際立っていたのは何といっても戦争の影だった。 主演男優賞を獲得した『The Pianist(戦場のピアニスト)』のエイドリアン・ ブロンディは、受賞スピーチの時間切れの合図を振り切るようにして、 平和的解決への願いを訴え満場の喝采を浴びた。 スピーチに直接・間接的を問わず反戦のメッセージを含ませた受賞者やプレゼンテーターは、彼に限らない。 だがその中で一人、公然とブッシュ大統領をこき下ろした長編ドキュメンタリー部門の受賞者マイケル・ムーアは、スピーチの最後を猛烈なブーイングに掻き消された。 この極端なまでの反応の違いは、アメリカ人にとって「反戦」と「反大統領」 の持つ意味の決定的な違いを浮き彫りにしたと言える。
 大統領に対するこの特殊な敬意は、(言うまでもなく) ジョージ・W・ブッシュの人望によるところではない。 彼の演説は語彙の貧弱さや無意味な言い回しの多いことで知られ、 ワイドショーではもっぱらコケにされ、 報道番組でも持ち上げられることはまずない。 だが彼がひとたび壇上に立ち、スピーチのさびに至って 「United States of America!」のキメ台詞を吐いた瞬間、 アメリカ人はボタンを押したように割れんばかりの拍手を送る。 ブッシュ個人をからかうのに遠慮はいらないが、アメリカ人に向かって大統領をこき下ろすのは避けた方が無難だ。 この国の人々にとって、「大統領」は星条旗と同じく彼らの神聖不可侵な価値観を代表する記号なのだ。演壇に立った瞬間から、そこにいるのはもはや 「ジョージ・W・ブッシュ」ではなくなるのである。
大統領に対するこの特殊な敬意は、(言うまでもなく) ジョージ・W・ブッシュの人望によるところではない。 彼の演説は語彙の貧弱さや無意味な言い回しの多いことで知られ、 ワイドショーではもっぱらコケにされ、 報道番組でも持ち上げられることはまずない。 だが彼がひとたび壇上に立ち、スピーチのさびに至って 「United States of America!」のキメ台詞を吐いた瞬間、 アメリカ人はボタンを押したように割れんばかりの拍手を送る。 ブッシュ個人をからかうのに遠慮はいらないが、アメリカ人に向かって大統領をこき下ろすのは避けた方が無難だ。 この国の人々にとって、「大統領」は星条旗と同じく彼らの神聖不可侵な価値観を代表する記号なのだ。演壇に立った瞬間から、そこにいるのはもはや 「ジョージ・W・ブッシュ」ではなくなるのである。
これはアメリカ人が幼いころから注意深く刷り込まれる、 抽象化された宗教といえるのかもしれない。 ふだんは至って理知的で愛国心のそぶりも見せない人すら、星条旗・国歌・大統領の 3点セットを突きつけられると、ある種のトランス状態に陥り God Bless Americaに涙することもある。 とは言え、普通の宗教とは大きく違うのは教義も教祖も存在しないことで、 あるのはあくまで象徴的な⏤⏤しかし実に強固な⏤⏤国家意識のみだ。 そのあたりに、表現・信教の自由を標榜する気風と矛盾することなく、 多宗教・多民族の国民を一つにまとめ上げた秘訣があるのかもしれない。
だがそれは逆に、あらゆる思想がアメリカの名の下に正当化され得る土壌を生む。 個人レベルでは底抜けにフレンドリーなアメリカ人が、 国家レベルでは最強の軍事力を引っ提げ他国を攻撃に行くという矛盾の裏には、星条旗に象徴されるアメリカの全てを肯定するワイルド・カードがある。 反戦運動は大いに結構⏤⏤ヒューマニズムはアメリカの心である⏤⏤だが、アメリカそのものに唾を吐くことは絶対に許されない。 マイケル・ムーアの反戦思想に共感する人は多かったはずだが、彼は憤りのあまり押してはいけないボタンを押してしまった。 アカデミー賞会場の聴衆の反応は、アメリカン・スピリットの二重構造を如実に体現していたと言えるだろう。
ハリウッド映画は、良くも悪くもアメリカ的価値観の鏡である。 露骨な一例は『インディペンデンス・デイ』のクライマックス、 異星人の襲撃による焼け野原で演説する大統領が、人々に抵抗を呼びかける場面だ。 非米国文化圏の観客にとっては困惑すら覚えるこのシーンも、アメリカ人なら容易に涙腺を緩めて不思議はない。
一方『インディペンデンス・デイ』とほぼ同時期に公開された『マーズ・アタック』は、物語のプロットが良く似ている反面、背後に流れる価値観はまるで逆である。 燦然たるオールスター・キャストを揃えながらチープな悪趣味に徹したこの映画では、米軍は火星人の襲撃にまるで歯が立たず、議会はあっさり全滅し、 最後には大統領すら火星人の首領にころりと騙され殺されてしまう。 結局地球を救うのは、痴呆の老女とその内気な孫だった。 『インディペンデンス・デイ』の大統領演説に対応するシーンは、 『マーズ・アタック』では死んだ大統領に代わってその娘が二人を表彰するシーンである。 そのとき、間に合わせのバンドが奏でるアメリカ国歌に、 老女は顔をしかめて耳をふさぐ。 このシーンの象徴する意味は深遠だ。 そこに私は、悪乗りの限りを尽くしたブラック・コメディにティム・バートン監督が仕込んだ、したたかで高潔なメッセージを見る。
宇宙戦争型SFの体裁を借り、「誰が世界を救えるか」という問いに正反対の答えを出した二つの映画。 強すぎる愛国心に目が眩んだアメリカの欺瞞と、 それを冷静に見据えるもう一つのアメリカ。 この二重の価値観のバランスがかろうじて持ちこたえている限り、 国際社会で孤立も辞さないこの国の奥深くに、いまだ潰えぬ良心が残されているはずである。
※初出『コロラドの☆は歌うか』2003年3月28日付
もちろん、それはロシアの人々だけに起こる問題ではない。今回は『コロラドの☆は歌うか』復刻企画の第2弾、2003年イラク戦争突入に踏み切ったアメリカで米国人の愛国心について考えたコラムを再掲したい。
(2003年)3月23日、ハリウッドでアカデミー賞の発表式典が開かれた。 日本では『千と千尋の神隠し』の長編アニメーション部門受賞がもっぱら話題を集めた(と思う)が、 今年の式典で際立っていたのは何といっても戦争の影だった。 主演男優賞を獲得した『The Pianist(戦場のピアニスト)』のエイドリアン・ ブロンディは、受賞スピーチの時間切れの合図を振り切るようにして、 平和的解決への願いを訴え満場の喝采を浴びた。 スピーチに直接・間接的を問わず反戦のメッセージを含ませた受賞者やプレゼンテーターは、彼に限らない。 だがその中で一人、公然とブッシュ大統領をこき下ろした長編ドキュメンタリー部門の受賞者マイケル・ムーアは、スピーチの最後を猛烈なブーイングに掻き消された。 この極端なまでの反応の違いは、アメリカ人にとって「反戦」と「反大統領」 の持つ意味の決定的な違いを浮き彫りにしたと言える。
 大統領に対するこの特殊な敬意は、(言うまでもなく) ジョージ・W・ブッシュの人望によるところではない。 彼の演説は語彙の貧弱さや無意味な言い回しの多いことで知られ、 ワイドショーではもっぱらコケにされ、 報道番組でも持ち上げられることはまずない。 だが彼がひとたび壇上に立ち、スピーチのさびに至って 「United States of America!」のキメ台詞を吐いた瞬間、 アメリカ人はボタンを押したように割れんばかりの拍手を送る。 ブッシュ個人をからかうのに遠慮はいらないが、アメリカ人に向かって大統領をこき下ろすのは避けた方が無難だ。 この国の人々にとって、「大統領」は星条旗と同じく彼らの神聖不可侵な価値観を代表する記号なのだ。演壇に立った瞬間から、そこにいるのはもはや 「ジョージ・W・ブッシュ」ではなくなるのである。
大統領に対するこの特殊な敬意は、(言うまでもなく) ジョージ・W・ブッシュの人望によるところではない。 彼の演説は語彙の貧弱さや無意味な言い回しの多いことで知られ、 ワイドショーではもっぱらコケにされ、 報道番組でも持ち上げられることはまずない。 だが彼がひとたび壇上に立ち、スピーチのさびに至って 「United States of America!」のキメ台詞を吐いた瞬間、 アメリカ人はボタンを押したように割れんばかりの拍手を送る。 ブッシュ個人をからかうのに遠慮はいらないが、アメリカ人に向かって大統領をこき下ろすのは避けた方が無難だ。 この国の人々にとって、「大統領」は星条旗と同じく彼らの神聖不可侵な価値観を代表する記号なのだ。演壇に立った瞬間から、そこにいるのはもはや 「ジョージ・W・ブッシュ」ではなくなるのである。これはアメリカ人が幼いころから注意深く刷り込まれる、 抽象化された宗教といえるのかもしれない。 ふだんは至って理知的で愛国心のそぶりも見せない人すら、星条旗・国歌・大統領の 3点セットを突きつけられると、ある種のトランス状態に陥り God Bless Americaに涙することもある。 とは言え、普通の宗教とは大きく違うのは教義も教祖も存在しないことで、 あるのはあくまで象徴的な⏤⏤しかし実に強固な⏤⏤国家意識のみだ。 そのあたりに、表現・信教の自由を標榜する気風と矛盾することなく、 多宗教・多民族の国民を一つにまとめ上げた秘訣があるのかもしれない。
だがそれは逆に、あらゆる思想がアメリカの名の下に正当化され得る土壌を生む。 個人レベルでは底抜けにフレンドリーなアメリカ人が、 国家レベルでは最強の軍事力を引っ提げ他国を攻撃に行くという矛盾の裏には、星条旗に象徴されるアメリカの全てを肯定するワイルド・カードがある。 反戦運動は大いに結構⏤⏤ヒューマニズムはアメリカの心である⏤⏤だが、アメリカそのものに唾を吐くことは絶対に許されない。 マイケル・ムーアの反戦思想に共感する人は多かったはずだが、彼は憤りのあまり押してはいけないボタンを押してしまった。 アカデミー賞会場の聴衆の反応は、アメリカン・スピリットの二重構造を如実に体現していたと言えるだろう。
ハリウッド映画は、良くも悪くもアメリカ的価値観の鏡である。 露骨な一例は『インディペンデンス・デイ』のクライマックス、 異星人の襲撃による焼け野原で演説する大統領が、人々に抵抗を呼びかける場面だ。 非米国文化圏の観客にとっては困惑すら覚えるこのシーンも、アメリカ人なら容易に涙腺を緩めて不思議はない。
一方『インディペンデンス・デイ』とほぼ同時期に公開された『マーズ・アタック』は、物語のプロットが良く似ている反面、背後に流れる価値観はまるで逆である。 燦然たるオールスター・キャストを揃えながらチープな悪趣味に徹したこの映画では、米軍は火星人の襲撃にまるで歯が立たず、議会はあっさり全滅し、 最後には大統領すら火星人の首領にころりと騙され殺されてしまう。 結局地球を救うのは、痴呆の老女とその内気な孫だった。 『インディペンデンス・デイ』の大統領演説に対応するシーンは、 『マーズ・アタック』では死んだ大統領に代わってその娘が二人を表彰するシーンである。 そのとき、間に合わせのバンドが奏でるアメリカ国歌に、 老女は顔をしかめて耳をふさぐ。 このシーンの象徴する意味は深遠だ。 そこに私は、悪乗りの限りを尽くしたブラック・コメディにティム・バートン監督が仕込んだ、したたかで高潔なメッセージを見る。
宇宙戦争型SFの体裁を借り、「誰が世界を救えるか」という問いに正反対の答えを出した二つの映画。 強すぎる愛国心に目が眩んだアメリカの欺瞞と、 それを冷静に見据えるもう一つのアメリカ。 この二重の価値観のバランスがかろうじて持ちこたえている限り、 国際社会で孤立も辞さないこの国の奥深くに、いまだ潰えぬ良心が残されているはずである。
※初出『コロラドの☆は歌うか』2003年3月28日付
Old Enough [海外文化]
 Netflixで公開が始まった日本の老舗テレビ番組が海外で話題を呼んでいるらしい。番組の英語タイトルは『Old Enough』。老人が人生経験でも語るのかと思えばさにあらず、何を隠そうその正体は『はじめてのおつかい』である。英国メディア(Guardian)と米国メディア(CNET)がレビューを書いているが、その戸惑いぶりが面白い。
Netflixで公開が始まった日本の老舗テレビ番組が海外で話題を呼んでいるらしい。番組の英語タイトルは『Old Enough』。老人が人生経験でも語るのかと思えばさにあらず、何を隠そうその正体は『はじめてのおつかい』である。英国メディア(Guardian)と米国メディア(CNET)がレビューを書いているが、その戸惑いぶりが面白い。日本の「はじめてのおつかい」は数時間ぶっちぎりで放映されることも多いが、ネトフリでは20分未満に刻んで放映しているようである。一回当たり一エピソード限定ということか。幼い子供が時に小さな胸を張り、時にとことん駄々をこね、最後には買い物袋をずるずる引きずり半べそで帰ってくる。そしてそれを迎える親が子供以上に号泣する。視聴者の涙腺を崩壊させる感動スイッチは万国共通のようだが、CNETの米国人ライターは番組を概ね好意的に評価しつつ「こんな小さな子たちを大人の目から離して大丈夫なのか」と困惑を隠し切れない。
私が米国コロラド州に住み始めたころ、まだ車がなかった私の必需品買い出しのためアメリカ人の同僚が付き添ってくれた。当時シングルマザーだった彼女は、人懐こい一人娘を同伴してきた。大人が商品棚の前で会話に夢中になると、娘はついフラフラと彷徨いはじめる。目が届くうちは良いのだが、子供が通路の角に姿を消したとたん同僚は血相を変え、おざなりに「Excuse me」と呟くや娘を連れ戻しに猛然と走り出した。小さな田舎町で凶悪犯罪などめったに起こらない土地柄ではあったが、安全に対する緊張感が日本とは全く違う事実を目の当たりにした瞬間であった。
もちろん「はじめてのおつかい」の制作チームは安全面に細心の注意を払い、通行人に扮したスタッフがやたらと子供の周りを徘徊する。上記の英米メディア記事でも番組側の配慮は認めているのだが、そもそも幼児だけでお使いに送り出すというコンセプト自体が彼らの文化圏では考えられないのである。乱暴な例えを許してもらえるなら、三歳児にバンジージャンプのハーネスを括り付けて高台から突き落とすドキュメンタリーを見せられているような残酷性を感じるのではないか。いくらバンジーの設備に安全性が担保されているとはいえ、シチュエーション自体に心理的な抵抗があるのだ。
もう一つ面白いと思ったのは、いずれの記事も日本独特の番組演出に言及している点だ。字幕をやたら多用する作りがGuardianの記者には少し目障りのようだ。一方、子供の心の声を代弁する「生意気系」ナレーションをCNETのライターは面白がっている。ちなみに、私が在米時に現地のテレビでよくやっていた日本の番組と言えば、『風雲!たけし城』と『料理の鉄人』であった。『Sasuke』も結構人気があって、『American Ninja Warriors』という米国版の模倣番組が存在する。
世界が受容する日本のエンタテイメントは何かと考えるとき、ジブリやポケモンのような王道を別にすれば、雑多なサブカルチャーの一群がひしめいている。そこに『はじめてのおつかい』がどこまで食い込むのか、今後の健闘に期待したい。
ある州知事の物語 [海外文化]
今回の記事は、旧シリーズ『コロラドの☆は歌うか』からの転載である。旧サイト運用で利用していたSo-netの「U-Page+」サービスが終了してしまったので、今後折に触れこのブログで少しずつ復刻掲載しようと考えている(単なるネタ切れ対策ではというご指摘は聞かなったことにする)。
戦時の困難な情勢にあって、社会に立ち込める憎悪に一人立ち向かい信念を貫いた政治家の物語である。これを書いた2004年はイラク戦争が混迷を深めつつあった時期であり、当時のきな臭い閉塞感が今日の状況と少し重なる。
コロラド・スプリングスから西に車で一時間ほど入った山間部に、クリップル・クリークという小さな町がある。現在では数軒のカジノが表通りに並ぶこじんまりとした歓楽街に過ぎないが、かつて金鉱を中心に栄えたゴールド・ラッシュの名残をかろうじて留めている。
当時の熱気がまだ余韻を引いていた20世紀初頭のクリップル・クリークに、ラルフ・ローレンス・カーという一人の少年がいた。当時の彼について知る手がかりは、今では全く残っていない。しかし、若き日のラルフがこの町で経験した何かが、やがて彼を類い稀な州知事へと導く礎を築くことになる。
コロラド大学を卒業したラルフ・カーは弁護士としてキャリアを踏み出した。行政機関の顧問弁護士を歴任した後、1939年コロラド州知事選に共和党の候補者として出馬する。民主党主導で全国を席巻していたニューディール旋風の中、彼は逆風に立ち向かい見事当選した。州知事としてラルフは行政機構の立て直しを指揮し、官僚システムの効率化に貢献した数少ないコロラド州知事の一人として認められた。が、それは彼が残すことになる偉業のほんの一部に過ぎない。
1941年12月、日本軍の真珠湾攻撃を機に太平洋戦争が勃発し、たちまち激しい反日感情が全米を揺るがした。ところが真珠湾攻撃の早3日後、ラルフ・カー州知事はラジオで公然と日系アメリカ人を擁護した。
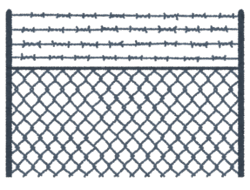 日系人に対するバッシングはコロラドにおいても例外ではなかった。ハイウエイ沿いには「ジャップは出ていけ」と書かれた看板が並んだ。そんな世相の中、ラルフ・カー州知事の姿勢は人々の反発と困惑を招いたが、彼は自分の信条をいささかたりとも曲げなかった。ラルフは、あらゆる日系人は他のアメリカ市民と同様の権利を保証されるべきだと繰り返し主張した。西海岸で土地と財産を奪われた日系人を受け入れるべくコロラド州南東部に建設された収容所は、当時の状況が許す範囲で住人の尊厳が認められていたという。
日系人に対するバッシングはコロラドにおいても例外ではなかった。ハイウエイ沿いには「ジャップは出ていけ」と書かれた看板が並んだ。そんな世相の中、ラルフ・カー州知事の姿勢は人々の反発と困惑を招いたが、彼は自分の信条をいささかたりとも曲げなかった。ラルフは、あらゆる日系人は他のアメリカ市民と同様の権利を保証されるべきだと繰り返し主張した。西海岸で土地と財産を奪われた日系人を受け入れるべくコロラド州南東部に建設された収容所は、当時の状況が許す範囲で住人の尊厳が認められていたという。
収容所に一人、隔離政策のためカリフォルニア大学を道半ばで諦めて来た女性がいた。ラルフは彼女を自宅で家政婦として雇い、彼女はその傍らデンバー大学で学位を取ることができた。彼女が卒業していくと、彼は収容所にいた別の日系人を雇った。
ラルフの隣人は、同じ屋根の下に日本人を迎え入れてどうして安眠できるのかと首をひねったが、ラルフにとって敵国人種の肌の色は何ら脅威ではなかった。「黄禍」を恐れなかった彼は、同時に世論から孤立する政治的リスクにも動じなかった。
1945年に終戦を迎え、コロラドの収容所にいた日系人は次々と西海岸に帰って行った。同年10月、その最後の一人がゲートを後にすると同時に収容所は閉鎖され、忌まわしい戦争と弾圧の記憶とともに永遠に封印された。
ラルフ・カーは一貫して日系人の市民権を擁護し続け、その引き換えに政界と人々の記憶から消し去られた。だが、コロラドに住む日系人は彼と彼の功績を決して忘れなかった。1976年、ラルフ・カーの胸像がデンバー・ダウンタウンの一角に立てられた。ダウンタウンの北のはずれ、サクラ・スクエアと呼ばれる小さな日本人街の中ほどで、ラルフの像はうつろいゆく時代の空気を今も静かに見据えている。
※初出『コロラドの☆は歌うか』2004年8月13日付
戦時の困難な情勢にあって、社会に立ち込める憎悪に一人立ち向かい信念を貫いた政治家の物語である。これを書いた2004年はイラク戦争が混迷を深めつつあった時期であり、当時のきな臭い閉塞感が今日の状況と少し重なる。
コロラド・スプリングスから西に車で一時間ほど入った山間部に、クリップル・クリークという小さな町がある。現在では数軒のカジノが表通りに並ぶこじんまりとした歓楽街に過ぎないが、かつて金鉱を中心に栄えたゴールド・ラッシュの名残をかろうじて留めている。
当時の熱気がまだ余韻を引いていた20世紀初頭のクリップル・クリークに、ラルフ・ローレンス・カーという一人の少年がいた。当時の彼について知る手がかりは、今では全く残っていない。しかし、若き日のラルフがこの町で経験した何かが、やがて彼を類い稀な州知事へと導く礎を築くことになる。
小さな町で育った私は、そこで人種偏見の憎悪がもたらす恥と不名誉を知りました。成長するにつれ、私は人種偏見を軽蔑するようになりました。なぜならそれは結局私たち全員の幸福を脅かすからです。
コロラド大学を卒業したラルフ・カーは弁護士としてキャリアを踏み出した。行政機関の顧問弁護士を歴任した後、1939年コロラド州知事選に共和党の候補者として出馬する。民主党主導で全国を席巻していたニューディール旋風の中、彼は逆風に立ち向かい見事当選した。州知事としてラルフは行政機構の立て直しを指揮し、官僚システムの効率化に貢献した数少ないコロラド州知事の一人として認められた。が、それは彼が残すことになる偉業のほんの一部に過ぎない。
1941年12月、日本軍の真珠湾攻撃を機に太平洋戦争が勃発し、たちまち激しい反日感情が全米を揺るがした。ところが真珠湾攻撃の早3日後、ラルフ・カー州知事はラジオで公然と日系アメリカ人を擁護した。
仲間や国家に対する想いの強さを、祖先のルーツがどこかという理由で決め付けてはいけません。連邦政府は西海岸に住んでいた日系人の土地や財産を没収し、強制収容所へ移住を命じたが、ラルフは日系人を捕虜のように扱うことにきっぱりと反対した。コロラドに住む日系人に対する制裁措置は一切認めようとしなかった。また連邦政府が内陸部の10州に収容所の用地提供を働きかけたとき、その要請を積極的に受諾した唯一の州がコロラドだった。他州が軒並み日系人を締め出そうとしていた最中、ラルフだけが進んで彼らに門戸を開いたのである。
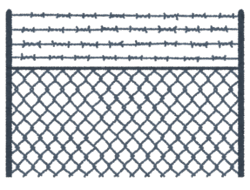 日系人に対するバッシングはコロラドにおいても例外ではなかった。ハイウエイ沿いには「ジャップは出ていけ」と書かれた看板が並んだ。そんな世相の中、ラルフ・カー州知事の姿勢は人々の反発と困惑を招いたが、彼は自分の信条をいささかたりとも曲げなかった。ラルフは、あらゆる日系人は他のアメリカ市民と同様の権利を保証されるべきだと繰り返し主張した。西海岸で土地と財産を奪われた日系人を受け入れるべくコロラド州南東部に建設された収容所は、当時の状況が許す範囲で住人の尊厳が認められていたという。
日系人に対するバッシングはコロラドにおいても例外ではなかった。ハイウエイ沿いには「ジャップは出ていけ」と書かれた看板が並んだ。そんな世相の中、ラルフ・カー州知事の姿勢は人々の反発と困惑を招いたが、彼は自分の信条をいささかたりとも曲げなかった。ラルフは、あらゆる日系人は他のアメリカ市民と同様の権利を保証されるべきだと繰り返し主張した。西海岸で土地と財産を奪われた日系人を受け入れるべくコロラド州南東部に建設された収容所は、当時の状況が許す範囲で住人の尊厳が認められていたという。収容所に一人、隔離政策のためカリフォルニア大学を道半ばで諦めて来た女性がいた。ラルフは彼女を自宅で家政婦として雇い、彼女はその傍らデンバー大学で学位を取ることができた。彼女が卒業していくと、彼は収容所にいた別の日系人を雇った。
ラルフの隣人は、同じ屋根の下に日本人を迎え入れてどうして安眠できるのかと首をひねったが、ラルフにとって敵国人種の肌の色は何ら脅威ではなかった。「黄禍」を恐れなかった彼は、同時に世論から孤立する政治的リスクにも動じなかった。
もし私を正しいと思うなら、日系人を迫害するのはやめることです。もし私が間違っていると考えるなら、次の選挙で私を葬り去るがいいでしょう。だが深まりゆく戦争の影の中で、人々の取った選択肢は明白だった。上院選に立候補したラルフは、日系人の排斥を主張したエド・ジョンソンに大敗を喫する。ラルフは人々を憎悪と差別に駆り立てた時代の狂気に一人で立ち向かい、敗れた。州知事就任からたった4年で政界から退いた彼は、その後二度と表舞台に返り咲くことはなかった。
1945年に終戦を迎え、コロラドの収容所にいた日系人は次々と西海岸に帰って行った。同年10月、その最後の一人がゲートを後にすると同時に収容所は閉鎖され、忌まわしい戦争と弾圧の記憶とともに永遠に封印された。
ラルフ・カーは一貫して日系人の市民権を擁護し続け、その引き換えに政界と人々の記憶から消し去られた。だが、コロラドに住む日系人は彼と彼の功績を決して忘れなかった。1976年、ラルフ・カーの胸像がデンバー・ダウンタウンの一角に立てられた。ダウンタウンの北のはずれ、サクラ・スクエアと呼ばれる小さな日本人街の中ほどで、ラルフの像はうつろいゆく時代の空気を今も静かに見据えている。
※初出『コロラドの☆は歌うか』2004年8月13日付
ウィル・スミスのビンタ問題 [海外文化]
 ウィル・スミスがアカデミー賞表彰式の場でクリス・ロックにビンタを食らわせ騒動になった。ロックがスミスの妻ジェイダの短髪をネタにしたことに怒りを爆発させたということである。ジェイダ・ピンケット・スミスは脱毛症を患っていたことをインスタ等で公表していた。ウィル・スミスへの同情論と、理由はなんであれ暴力に弁解の余地はないという批判が交差し、賛否両論が盛り上がっている。
ウィル・スミスがアカデミー賞表彰式の場でクリス・ロックにビンタを食らわせ騒動になった。ロックがスミスの妻ジェイダの短髪をネタにしたことに怒りを爆発させたということである。ジェイダ・ピンケット・スミスは脱毛症を患っていたことをインスタ等で公表していた。ウィル・スミスへの同情論と、理由はなんであれ暴力に弁解の余地はないという批判が交差し、賛否両論が盛り上がっている。同情論はクリス・ロックへの批判の裏返しである。コメディアンなのだから際どいジョークで笑いを取るのは仕事のうちだが、とは言え病気で頭髪を失った人の容姿をからかうのは許されるのか?お笑いに求めるOKとNGの線引きには、個人の価値観はもちろん文化的な受容度の違いもある。英国コメディ界のヒーローMr. Beanは老人や病人も容赦なくイジるので、日本人の感覚ではほぼ放送禁止レベルかと思われるような危ないネタもある。とは言え、スミスを刺激したクリス・ロックのジョークはアメリカでも好意的には受け止められていないようである。確信犯で笑いを取ったのなら下衆な話だが、そもそも彼はピンケット・スミスの脱毛症を知らなかったという話もある。
ウィル・スミスへ批判的な意見の方は、単に暴力反対というほかにいくつか別の観点があるようだ。愛する妻を侮辱され腹を据えかねた、というシナリオは同情論を煽る反面、その直情的な思考回路そのものを疑問視する論者も少なくない。スミスの行為を男性=庇護者という時代遅れのマッチョ社会観と見るフェミニズム的批判があれば、黒人と暴力が結び付けられがちな人種偏見をスミス自ら助長したと指摘する人もいる。ハリウッドの頂点を極める大スターが「格下」のコメディアンを公衆の面前で叩いたという事実も後味が悪い。平手打ちの被害そのものより、「あのウィル・スミス」が「あの流れ」でやらかしたが故に図らずも浮かび上がったメッセージ性にいろいろ物申したい人が多いようである。
クリス・ロックが問題のジョークをかましたとき、気丈ながら傷ついた表情を隠しきれない妻ジェイダの隣で、普通に笑っているウィル・スミスの映像が残っている。その直後に彼は立ち上がってビンタしに行き、席に戻った後も大声で悪態をついた。あれは本当にクリス・ロックへの純粋な怒りだったのか?それとも、つい笑ってしまった己の失態を大袈裟なパフォーマンスで取り繕いたかったのか?本来ウィル・スミスが取るべきだった態度は、ロックのネタにニコリともせず、黙って妻の手を握ることではなかったのか。あの出来事の直後、デンゼル・ワシントンがウィル・スミスを諭した言葉が「気をつけた方がいい。最高の瞬間にこそ悪魔は忍び寄ってくる。」だったと言う(しびれるセリフだ)。あのときウィル・スミスに取りついた悪魔とは、強すぎる家族愛が冷静な判断を曇らせたことだったのか、それとも本人が標榜するほどには強くなかった愛を妻に見透かされる恐怖だったのか。
別のパンダの話 [海外文化]
上野動物園の双子パンダ、シャオシャオとレイレイが一般公開を控えている。ただオミクロン株の影響で、当面は抽選の済んでいる3日間だけという話だ。ただし今日書こうと思っているのはその話ではない。
 Panda Expressという米国の中華ファーストフードチェーンがある。短期間でもアメリカに住んでいたことがある人なら、たぶんご存知だろう。ショッピングモールのフードコートなどによく入っていて、店員と対話しながら好きなメニューを選んでいく。サンドウィッチのサブウェイと同じ要領だ。この類の同業他社は多いが、パンダは老舗の一つと思う。中華だからパンダ、というベタな直球ネーミングが潔い。
Panda Expressという米国の中華ファーストフードチェーンがある。短期間でもアメリカに住んでいたことがある人なら、たぶんご存知だろう。ショッピングモールのフードコートなどによく入っていて、店員と対話しながら好きなメニューを選んでいく。サンドウィッチのサブウェイと同じ要領だ。この類の同業他社は多いが、パンダは老舗の一つと思う。中華だからパンダ、というベタな直球ネーミングが潔い。
サブウェイの注文がパンのチョイスから入るのと同じで、まずはベースの炭水化物系を聞かれる。ライス(炒飯)か焼きそばを選ぶが、ハーフ&ハーフと頼むと半分ずつ載せてくれる。おかずは1つか2つ(3つのオプションもあったかも知れない)を選べるコースがあって、欲しいメニューを自由に組み合わせればいい。ちゃちな再生紙か発泡スチロールの皿にてんこ盛りによそってくれ、たいてい焼きそばの端っこが皿から飛び出している。最後にレジで飲み物を選び、お会計をする。
アメリカで暮らす知恵の一つは、外食の際にどこで何を選べば不味くないか(美味いかではない)経験則を蓄積することだ。よほど高級レストランに行くのでなければ、だいたいエスニック料理にたどり着く。メキシカン、タイ、ベトナム、そのあたりは安い店でも致命的なハズレはない。中華はそもそも数が多いので残念な店も少なくないが、米国内どこに行っても出会えるチェーン店なら良くも悪くもクオリティが予測可能だ。個人的には、パンダのカシューチキンとかブロッコリビーフとかが好きだ。ほぼ見た目どおりのわかりやすい味で、安心感がある。感涙するほど美味しいわけではないが、アメリカで気軽に出会えるファーストフードとして何ら不足はない。
一年ちょっと前、住まいの近くにららぽーとがオープンした。そのフードコートに、なんとPanda Expressが入店している。日本に進出しているのを知らなかったので、再会が嬉しい。メニューも懐かしい品揃えで、テンションが上がる。本国のパンダに比べると、味は洗練されている気がするし、ボリュームは明らかに少ない(というかアメリカ標準のてんこ盛りがおかしい)。日本なので行くべき名店は他にいくらでもあるし、油と添加物で健康に悪そうな気もするが、それはそれでいい。Panda Expressとは、ある意味でアメリカという国の猥雑でチープで底知れない魅力の象徴なんだと思う。
 Panda Expressという米国の中華ファーストフードチェーンがある。短期間でもアメリカに住んでいたことがある人なら、たぶんご存知だろう。ショッピングモールのフードコートなどによく入っていて、店員と対話しながら好きなメニューを選んでいく。サンドウィッチのサブウェイと同じ要領だ。この類の同業他社は多いが、パンダは老舗の一つと思う。中華だからパンダ、というベタな直球ネーミングが潔い。
Panda Expressという米国の中華ファーストフードチェーンがある。短期間でもアメリカに住んでいたことがある人なら、たぶんご存知だろう。ショッピングモールのフードコートなどによく入っていて、店員と対話しながら好きなメニューを選んでいく。サンドウィッチのサブウェイと同じ要領だ。この類の同業他社は多いが、パンダは老舗の一つと思う。中華だからパンダ、というベタな直球ネーミングが潔い。サブウェイの注文がパンのチョイスから入るのと同じで、まずはベースの炭水化物系を聞かれる。ライス(炒飯)か焼きそばを選ぶが、ハーフ&ハーフと頼むと半分ずつ載せてくれる。おかずは1つか2つ(3つのオプションもあったかも知れない)を選べるコースがあって、欲しいメニューを自由に組み合わせればいい。ちゃちな再生紙か発泡スチロールの皿にてんこ盛りによそってくれ、たいてい焼きそばの端っこが皿から飛び出している。最後にレジで飲み物を選び、お会計をする。
アメリカで暮らす知恵の一つは、外食の際にどこで何を選べば不味くないか(美味いかではない)経験則を蓄積することだ。よほど高級レストランに行くのでなければ、だいたいエスニック料理にたどり着く。メキシカン、タイ、ベトナム、そのあたりは安い店でも致命的なハズレはない。中華はそもそも数が多いので残念な店も少なくないが、米国内どこに行っても出会えるチェーン店なら良くも悪くもクオリティが予測可能だ。個人的には、パンダのカシューチキンとかブロッコリビーフとかが好きだ。ほぼ見た目どおりのわかりやすい味で、安心感がある。感涙するほど美味しいわけではないが、アメリカで気軽に出会えるファーストフードとして何ら不足はない。
一年ちょっと前、住まいの近くにららぽーとがオープンした。そのフードコートに、なんとPanda Expressが入店している。日本に進出しているのを知らなかったので、再会が嬉しい。メニューも懐かしい品揃えで、テンションが上がる。本国のパンダに比べると、味は洗練されている気がするし、ボリュームは明らかに少ない(というかアメリカ標準のてんこ盛りがおかしい)。日本なので行くべき名店は他にいくらでもあるし、油と添加物で健康に悪そうな気もするが、それはそれでいい。Panda Expressとは、ある意味でアメリカという国の猥雑でチープで底知れない魅力の象徴なんだと思う。



