なめとこ山の熊 [文学]
 宮沢賢治は、他者の命を犠牲に生を紡ぐ生物界の掟に真正面から向き合った人である。『よだかの星』のよだかは、飲み込んだ虫が喉元を通過するたび、自身が奪う小さな命を思って胸がつかえる。生きるために不可欠な殺生の罪について考え続け、その行く末に安らぎの地平を見出そうとする葛藤の軌跡が、宮沢賢治作品のそこかしこに垣間見える。
宮沢賢治は、他者の命を犠牲に生を紡ぐ生物界の掟に真正面から向き合った人である。『よだかの星』のよだかは、飲み込んだ虫が喉元を通過するたび、自身が奪う小さな命を思って胸がつかえる。生きるために不可欠な殺生の罪について考え続け、その行く末に安らぎの地平を見出そうとする葛藤の軌跡が、宮沢賢治作品のそこかしこに垣間見える。『なめとこ山の熊』は、そんな宮沢賢治が到達した独特な世界観の結晶である(青空文庫で読める)。小十郎という熊取り名人の猟師となめとこ山に住む熊たちの生き様が、朴訥とした語り口に時折ハッとする美しい情景描写を散りばめながら綴られる。物語の中盤、銃を構える小十郎に一頭の熊がこう問いかけるくだりがある。
「おまえは何がほしくておれを殺すんだ」果たして二年後、熊は律儀に約束を果たす。住処の前で息絶え横たわる熊を前に、小十郎は思わず両手を合わせるのだ。
「ああ、おれはお前の毛皮と、胆のほかにはなんにもいらない。それも町へ持って行ってひどく高く売れるというのではないしほんとうに気の毒だけれどもやっぱり仕方ない。けれどもお前に今ごろそんなことを言われるともうおれなどは何か栗かしだのみでも食っていてそれで死ぬならおれも死んでもいいような気がするよ」
「もう二年ばかり待ってくれ、おれも死ぬのはもうかまわないようなもんだけれども少しし残した仕事もあるしただ二年だけ待ってくれ。二年目にはおれもおまえの家の前でちゃんと死んでいてやるから。毛皮も胃袋もやってしまうから」
小十郎と熊は、端から平和に共存することの叶わない宿命を生きている。しかしその残酷な運命を分かち合っているからこそ、両者は不思議な共感の絆で結ばれている。小十郎の足元を見て熊皮を二束三文で買い取る町の商人と対照的に、熊と小十郎の関係はどこまでも対等で誠実だ。年老いた小十郎はある日、大きな熊の襲撃に遭う。そのとき熊は「おお小十郎おまえを殺すつもりはなかった」と呟き、小十郎は「熊どもゆるせよ」と心に言い残し息絶える。やがて小十郎の亡骸の周りに山の熊たちが集結し、厳粛な敬意をもって小十郎を弔う場面で物語は幕を下ろす。
今年、全国各地で熊の襲撃による人的被害が記録的な件数に上っているという。やむなく地元のハンターが熊を駆除すると、地域外の人間から「なぜ殺した」と浅薄な苦情が相次ぐそうだ。そこでふと思い出したのが、『なめとこ山の熊』だ。宮沢賢治が描く世界は現代の日本と遠くかけ離れているとは言え、彼が考え続けた思索の深さと温かみは、今なお心に重く刺さるものがある。
午後の恐竜 [文学]
 『午後の恐竜』という星新一の短編がある。星新一と言えばユーモアと皮肉のきいたオチで読者を唸らせるショートショートの達人だが、もう少し長めでちょっとシリアスなテーマを扱った短編もたくさん書いた。『処刑』しかり『午後の恐竜』しかり、異彩を放つ傑作が少なくない。
『午後の恐竜』という星新一の短編がある。星新一と言えばユーモアと皮肉のきいたオチで読者を唸らせるショートショートの達人だが、もう少し長めでちょっとシリアスなテーマを扱った短編もたくさん書いた。『処刑』しかり『午後の恐竜』しかり、異彩を放つ傑作が少なくない。街を闊歩する恐竜たちを見上げ子供らがはしゃぐ不可思議な場面で幕を開ける。いったい何が起こっているのか、誰にもわからない。恐竜は蜃気楼のように実体がなく、触れることができない。そこら中に原始の植物がはびこり、空には翼竜が飛び交っているが、すべて立体映像のように儚く無害だ。次第に恐竜は姿を消し、代わりにマンモスのような哺乳動物が跋扈する。目まぐるしく時代が進み、やがて原始人が現れる。あたかも進化の歴史を早送りで再現するショーが繰り広げられているかのようだ。そして地球史がついに現代に追いついた夕暮れ時、物語は衝撃的な結末で幕を閉じる。
1968年に発表された『午後の恐竜』は、テーマパークのパレードを眺めているような祝祭感を装いながら、通底するのは冷戦期の緊迫した時代の空気である。一歩間違えれば容易に世界を破壊し得る核兵器の脅威。人は死の直前に一生の記憶が走馬灯のように頭をよぎると言うが、『午後の恐竜』で描かれるのは地球全史を網羅する壮大な「世界の臨死体験」だ。子供たちが嬉々として無害な恐竜と戯れる間に、世界は破滅に向かって猛然と突き進んでいく。
米ソが軍拡競争に邁進していた当時、人々は何食わぬ顔で当たり前の日常を送りながら、一皮むけばその深層に黙示録的な不安が潜んでいた。でも裏を返せば、どんな暗鬱な時代にも人々の変わらぬ暮らしがあり、日々のささやかな喜怒哀楽であふれているということでもある。ロシア軍に破壊されたウクライナの街で、かろうじて全壊を免れた自宅に暮らす市民がせっせと花壇の手入れをする様子をテレビで見た。そのとき思い出したのが『午後の恐竜』である。これは世界の終わりの話ではなくて、人々のたくましい知恵と生命力についての物語だったのか、と初めて気付いた。
ボタン、ボタン [文学]
 米国SF界の巨匠リチャード・マシスンが1970年に発表した『Button, Button』という短編がある。SFというよりむしろホラーに近い。ある夫婦のもとに不可解な小包が届く。中身は、押しボタンが一つあるだけの奇妙な装置だ。すぐにスチュワードと名乗るセールスマン風の男が夫婦を訪れ、このボタンを押すと大金(5万ドル)が贈られるが、代償として世界のどこかで知らない誰かが死ぬ、と説明する。
米国SF界の巨匠リチャード・マシスンが1970年に発表した『Button, Button』という短編がある。SFというよりむしろホラーに近い。ある夫婦のもとに不可解な小包が届く。中身は、押しボタンが一つあるだけの奇妙な装置だ。すぐにスチュワードと名乗るセールスマン風の男が夫婦を訪れ、このボタンを押すと大金(5万ドル)が贈られるが、代償として世界のどこかで知らない誰かが死ぬ、と説明する。謎の装置を巡る夫婦の会話が、物語の大半を占める。半信半疑ながら大金の誘惑にまんざらでもない妻は、見知らぬ他人の命と引き換えに幸福を手にする疚しさを遠回しに正当化しようとする。そんな彼女の独白を冷めた態度で聞き流す夫。嚙み合わない会話の落としどころが見つからないまま、妻は家で独りになったある平日、こっそりボタンを押す。そしてまもなく家の電話が鳴る。
最近ロシアの「核のボタン」を巡る懸念をメディアで耳にしない日はない。マシスンのボタンは、ある意味で核のボタンと似ている。仮に一国の指導者が核のボタンを押すことがあるとすれば、それは自国にとって何らかの利益になると考えるからであり、そしてその「利益」は他国の市民の多大な犠牲の上に成立する。冷戦が終結して久しい今そんな暴挙に出る者はいない、と世界は楽観的に望みをつないできた。でもその希望が再び揺らぎつつある。
電話に出た妻は、仕事帰りの夫が地下鉄事故で死亡したことを知らされる。そして、夫にかけた生命保険金が5万ドルであったことに思い至る。その直後に電話をかけて来たスチュワードに、妻は「死ぬのは知らない人だってあなた言ったじゃない!」と怒りをぶつける。するとスチュワードは答える。
「奥様。ご主人のことをご存じだったと、あなたは本当に思っておられるのですか?」ここで物語は唐突に終わる。
『Button, Button』はあまり若いうちに読んでもピンとこないかもしれない。しかし夫婦の乾いた会話劇にリアリティを感じる年齢になってから読み返すと、スチュワードの決め台詞に背筋が冷える。それはまた、核のボタンに指をかける誰かの深い孤立と愚かしさを暗示しているようでもある。
はらぺこバッハ [文学]
 毎日新聞が『はらぺこあおむし』をパロったIOC批判の風刺画を掲載し、絵本を出版する偕成社からこっぴどく叱られた(社長名で出された声明)。IOCの強欲ぶりを食欲満点のアオムシになぞらえたことが、出版元の機嫌をえらく損ねたようである。風刺画そのもの出来栄えはさておき、偕成社の怒りっぷりが並大抵でないので、失礼ながらそちらのほうに笑ってしまった。
毎日新聞が『はらぺこあおむし』をパロったIOC批判の風刺画を掲載し、絵本を出版する偕成社からこっぴどく叱られた(社長名で出された声明)。IOCの強欲ぶりを食欲満点のアオムシになぞらえたことが、出版元の機嫌をえらく損ねたようである。風刺画そのもの出来栄えはさておき、偕成社の怒りっぷりが並大抵でないので、失礼ながらそちらのほうに笑ってしまった。いちばん可笑しかったのは、「『はらぺこあおむし』の楽しさは、あおむしのどこまでも健康的な食欲と、それに共感する子どもたち自身の「食べたい、成長したい」という欲求にあると思っています」というくだりである。絵本を読みながら、嗚呼あおむしのように食べ成長したいなどと感動する子供が、いったいどこにいるんだろう?
この本は装丁に色々工夫があって、大きさの違うページをめくったり戻したり、虫食い穴に指を突っ込んだり、まずは身体感覚を刺激する。そして、日を重ねる度に増えていく食べ物とか、食べ過ぎて丸々と膨れたあおむしとか、最後にページいっぱいに羽ばたく極彩色の蝶とか、物語のリズムや溢れる色彩が独特だ。それだけで十分な魅力なのに、「子どもたち自身の食べたい、成長したいという欲求」などと妙に立派な理屈を持ち出してきたところが、残念である。
私は小さい頃、『のろまなローラー』という絵本の大ファンだった。たぶん今でも書店に並んでいると思う。道路工事で舗装に使われるあの重機が主人公である。黙々と仕事をこなすローラーだが、他の車から追い抜きざまにノロマぶりをバカにされる。しかしローラーがのろのろと山道に差し掛かると、追い抜いていった車が軒並み荒れた路面でパンクし困り果てている。一台一台に励ましの声を掛けながら、舗装作業を続けるローラー。やがて復旧した車が追いついて来て、今度はローラーの仕事ぶりに感謝を述べて走り抜けていく。
『のろまなローラー』のメッセージは明らかだ。歩みは遅いが効率では図れない仕事の価値。人に顧みられずともコツコツ努力を続ける尊さ。冷たい言葉を浴びせた相手にすら惜しまない思いやり。いずれもこの絵本が読み継がれる所以だとは思うが、所詮は大人目線の哲学でしかない。幼い私が『のろまなローラー』を愛読していた理由は、何よりも「ごろごろ ごろごろ ローラーは」といった言葉の響きやリズムが好きだったのである。運動音痴でトロかった自分を肯定してくれるような安心感も、手伝っていたかもしれない。いずれにせよ、子供が絵本を楽しむのに高尚な動機など必要ない。
偕成社が『はらぺこあおむし』に並々ならぬ愛着をお持ちなことはよくわかる。しかし残念なのは、出版元自ら『あおむし』の解釈を一方的に押し付けていることである。あおむしの顔にIOCバッハ会長をはめ込み、あおむしの「健康的な食欲」に飽くなき金銭欲を引っ掛けた毎日新聞は、下品と言えば確かに下品だ。でも『あおむし』を読む子供の中には、コイツは食べてばかりで困ったやつだと感じる子もいるかも知れないし、それはそれで構わない。数字や曜日を覚えるのにうってつけの本という親の賛辞も聞こえてくるが、絵本は絵本であって教科書ではない。先日他界した作者エリック・カール氏の意図は今や知る由もないが、小賢しい大人の読み方を強要するような人ではたぶんなかったのではないか。
繰り返すが、毎日新聞の風刺画が秀逸とは別に思わない。しかし偕成社の方も、毎日を名指しして「不勉強、センスの無さを露呈」とか「猛省を求めたい」とか言葉がいちいち刺々しい。あのおおらかな『あおむし』の世界と、まるで似つかわしくない。大した事件ではないが、やはりいろいろ残念である。
クララとお日さま [文学]
 『クララとお日さま(Klara and the Sun)』は、カズオ・イシグロが6年ぶりに上梓した新作長編である。もともと寡作な作家だが、その代わり作品一つ一つの密度と完成度が半端ない。前作『忘れられた巨人(The Buried Giant)』では、忘却の霧に沈みゆくアーサー王伝説後の世界を舞台に、仲睦まじい老夫婦の心深くに眠る孤独の闇をえぐり出した。『クララ・・・』はというと、差別や遺伝子改変技術といった社会の課題を横軸として、家族や隣人のあいだに交錯する複雑な感情を丁寧に見つめる。SFやファンタジーの設定を借りつつ、身近で普遍的な人間関係の軋みを描くのが、ここ10年ほどのイシグロ小説(二つだけだが)のテーマのようである。
『クララとお日さま(Klara and the Sun)』は、カズオ・イシグロが6年ぶりに上梓した新作長編である。もともと寡作な作家だが、その代わり作品一つ一つの密度と完成度が半端ない。前作『忘れられた巨人(The Buried Giant)』では、忘却の霧に沈みゆくアーサー王伝説後の世界を舞台に、仲睦まじい老夫婦の心深くに眠る孤独の闇をえぐり出した。『クララ・・・』はというと、差別や遺伝子改変技術といった社会の課題を横軸として、家族や隣人のあいだに交錯する複雑な感情を丁寧に見つめる。SFやファンタジーの設定を借りつつ、身近で普遍的な人間関係の軋みを描くのが、ここ10年ほどのイシグロ小説(二つだけだが)のテーマのようである。イシグロ作品の登場人物は、たいてい自我が強くてとげとげしい。表向き人当たりが良くても、往々にして内心は頑固で自己中心的だ。それは『クララとお日さま』でも例外ではないが、主人公のクララだけは一貫して冷静沈着で他意がない異色のキャラである。作者がクララだけに異例の特権を与えたのは、彼女がそもそも人間ではないからだ。
クララはAF(Artificial Friend)と呼ばれるアンドロイドの少女である。ショップの窓から垣間見える世界の一角を、日々観察するクララ。知的で洞察力に優れながら、その一方で世界を独特な「常識」で捉えている。太陽光発電で動作する彼女は、生身の人間も同じように陽射しを糧に命をつないでいると信じている。ある日クララは、病弱な少女ジョジーの話し相手として買い取られる(『アルプスの少女』のハイジとクララの関係に少し似ているが「クララ」の立場が逆転している)。クララはジョジーを不治の病から救うため、太陽を相手に取引を持ちかける奇矯な計画をひそかに温める。
AFの存在が当たり前の近未来世界だが、アンドロイドに向けられる人々の眼差しはしばしば冷たくぎこちない。しかし怒りや憎悪の情動をプログラミングされていないクララは、露骨な仕打ちすら淡々と受け止める。時折クララの認知機能に一時的な障害が生じ、彼女の視覚が奇妙に歪む。しかしストレスやパニックという概念を知らないクララは、明らかな機能不全すら慌てる素振りも見せない。クララの一人称で語られる物語は、早朝の湖面に映し出される大自然の風景のように、澄みわたった静けさに満ちている。
だが読者はやがて、そんな水面にさざ波を掻き立てる不穏な風向きを感じ取る。隣家に住むボーイフレンドのリックとジョジーを隔てる「階層」の壁。その壁に抜け穴を穿とうと企むリックの母。別居するジョジーの父と母を分かつ価値観の溝。そして、ジョジーの母がクララを手に入れた本当の理由。ジョジーとリック、リックと母、母とジョジー、人間たちがエゴと表裏一体の愛情に傷つき苦しむ傍らで、クララはひとり純粋で無償の友情を貫こうとする。イシグロ作品の常として過剰な演出を拝した静謐な物語だが、終盤思わぬできごとが春先の突風のように訪れる。仰々しい仕掛けは何もないのに、そのクライマックスが言葉を失うほど神々しい。
『クララとお日さま』の結末は果たしてハッピーエンドか?どの登場人物に肩入れするかで、たぶんその印象は変わるだろう。作品の舞台はクララにとって決して幸福な世界ではないが、それでも彼女の独白は相変わらず物静かで、取り乱すことはない。でもカズオ・イシグロが創り出したAFは、無私無欲の聖人ではないし、無機質なロボットでもない。最終章までたどり着いた読者は、明鏡止水のごときクララの語り口が隠しきれない、彼女のかすかな心の震えに気付くかも知れない。
火星人との付き合い方 [文学]
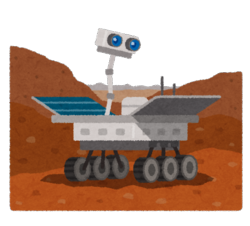 NASA JPLの火星探査機Perseverance Roverが、無事現地に着陸した。着陸船からローバーが紐で吊るされそろりそろりと降下される様子は、まるでドローンが宅配便を送り届けているかのようだ。前回の探査機Curiosityから採用された手法のようだが、ちょっと昔の火星ミッション(Mars Pathfinder)はエアバッグにローバーを包んで突き落とし、手荒くバウンドさせていた記憶がある。もし火星人がその様子に出くわしていたら、地球も文明が進んで少しは洗練された着陸ができるようになったか、と感心したかもしれない。
NASA JPLの火星探査機Perseverance Roverが、無事現地に着陸した。着陸船からローバーが紐で吊るされそろりそろりと降下される様子は、まるでドローンが宅配便を送り届けているかのようだ。前回の探査機Curiosityから採用された手法のようだが、ちょっと昔の火星ミッション(Mars Pathfinder)はエアバッグにローバーを包んで突き落とし、手荒くバウンドさせていた記憶がある。もし火星人がその様子に出くわしていたら、地球も文明が進んで少しは洗練された着陸ができるようになったか、と感心したかもしれない。H.G.ウェルズが『宇宙戦争』を発表したのは1898年、当時は人類がいつか火星に探査機を送り込むなど想像もしていなかったかもしれない。代わりに火星人の方が出向いてきて、地球の侵略を試みた。圧倒的な技術力を誇る火星人の襲撃に人類は為すすべもなかったが、最後は火星人が地球の伝染病にやられてコロリと全滅する。『宇宙戦争』の原題は『The War of the Worlds』で、直訳すれば世界と世界の戦争ということになる。ウェルズは地球対火星という構図に加え、ミクロとマクロの生態系が交える世界間決戦という寓意も重ねたかったのかも知れない。コロナとの付き合い方を暗中模索する今、ウェルズの火星人が舐めた辛酸を、今度は私たちが味わう羽目になっている。
『宇宙戦争』からおよそ半世紀後、レイ・ブラッドベリの代表作『火星年代記(Martian Chronicles)』が誕生する。短編集のようであり一大叙事詩のようでもあり、皮肉とユーモアと詩情が交叉する不可思議な魅力に溢れた作品だ。宇宙開発時代の黎明期に書かれたこの物語では、地球の文明は火星に人類を送り込むまでに発展している。しかし一大スペクタクルが繰り広げられるウェルズの『宇宙戦争』に比べ、ブラッドベリが描くファースト・コンタクトは拍子抜けするほどあっけない。
『火星年代記』の幕開けは、倦怠期の火星人夫婦が織りなす冷めた家庭劇だ。夢の中で王子様のような地球人飛行士の来訪を察知し胸が高鳴る妻と、無関心を装いながらそれが面白くない夫。居ても立っても居られない妻を家に置いて、夫が銃器を片手に一人猟に出る。やがて遠くから銃声が聞こえ、妻が待ち望んだ地球人の痕跡はテレパシーから突如途絶える。SF版レイモンド・カーヴァーとでも言えそうな夫婦の乾いた会話劇が、記念すべき人類の第一次先遣隊を見舞った悲運を暗示する。続く第二次先遣隊は地球からの使者と誰からも真に受けてもらえず、精神病棟に送られた挙句やはりあっさりと片付けられてしまう。
しかし、程なく火星人は自ずと全滅する。『宇宙戦争』の結末と同じく、彼らは訪問者が持ち込んだウイルスに無力だった。ただウェルズの火星人が悪意に満ちた侵略者であったのと対照的に、ブラッドベリの火星人にとっては地球人のほうが侵入者だ。かつて新大陸の先住民が欧州人の持ち込んだ伝染病で苦しんだように、『火星年代記』は無邪気に火星に押し寄せる地球人を植民地主義の再興として描く。
1970年代に人類が送った探査機が初めて火星に着陸し、そこが知的生命体など一切存在しない不毛の荒野であることを確認した。それから半世紀近くを経た現在、例え原始的な単細胞生物のカケラであるにせよ、私たちは火星に生命の痕跡を見つけ出す可能性を諦めていない。ウェルズやブラッドベリが危惧したような火星人との不幸な邂逅は杞憂だったが、人類は宇宙の果てしない闇にポツリと佇む孤独がどうしても耐えられないようである。
向田邦子のエッセイ [文学]
とある方のインタビュー記事で、こんな逸話に出会った。小学生の頃、学校から帰宅の時分ドシャ降りに遭った。家が近かったので、自宅の傘をいくつかひっつかんで学校へ戻り、傘がなくて困っていた先生に貸そうとした。ところが蛇の目の柄が気に入らなかったか、「こんな傘がさせるか」と不機嫌に突き返されてしまう。ひどく傷ついた彼女は帰宅後、歳の離れた姉にその出来事を訴えた。すると姉が言うには、大人も子供と同じように好みがあって、虫の居所が悪いときもあるから、理不尽な言い分で人に当たることもある。でもあなたのやったことはとても素晴らしい。彼女はその姉の言葉にとても救われた、というような話である。当時20歳とは思えぬ達観した温かい言葉で妹に寄り添った姉は、若き日の向田邦子さんである(インタビューに答える女性は末妹の和子さん)。
 先日たまたま自宅に『向田邦子ベスト・エッセイ』という本を見つけて、懐かしくなった。向田邦子のエッセイに目を通すのは、学生の頃ハマって読破して以来だからほぼ30年ぶりだ。お父上が無愛想で怒りっぽい昔ながらの大和男子で、子煩悩な本心を素直に表現する術を知らない。『父の詫び状』を始めたびたびエッセイに登場する不器用な父を、向田邦子は上品なユーモアを交え淡々と描く。でも「ちょっといい話」的な毒抜きされたほのぼの感とは、すこし違う。人の心のひだを見通す眼差しは触れれば指を切りそうなくらい鋭いのに、刃先を他人に向けることは絶対にない。聡明で思いやりの染み渡った美しい文章は、いつも諦観に近い寂しさが仄かに漂う。
先日たまたま自宅に『向田邦子ベスト・エッセイ』という本を見つけて、懐かしくなった。向田邦子のエッセイに目を通すのは、学生の頃ハマって読破して以来だからほぼ30年ぶりだ。お父上が無愛想で怒りっぽい昔ながらの大和男子で、子煩悩な本心を素直に表現する術を知らない。『父の詫び状』を始めたびたびエッセイに登場する不器用な父を、向田邦子は上品なユーモアを交え淡々と描く。でも「ちょっといい話」的な毒抜きされたほのぼの感とは、すこし違う。人の心のひだを見通す眼差しは触れれば指を切りそうなくらい鋭いのに、刃先を他人に向けることは絶対にない。聡明で思いやりの染み渡った美しい文章は、いつも諦観に近い寂しさが仄かに漂う。
『噛み癖』というエッセイで、彼女がかつて飼っていた大型犬の話が登場する。気立ての良い犬だったが、見境なく甘噛みする癖があった。隣人を追い回しては服の裾を駄目にしてしまう失態を繰り返し、ついに保健所送りになってしまった。見送る最後の日に大好物のソーセージを買い込んでくるが、駅で袋が破れホームにぶちまけてしまう。居心地の悪い視線を背に受けソーセージを拾い集めながら、人じゃないの犬が食べるの、いいヤツだったけど保健所に行かなくてはいけないの、と心のなかで叫ぶ。そのくだりを読みながら、むかし私の実家で飼っていた犬の二代目を思い出した。白黒モノトーンのおてんば娘で、名前をコムといった。
コムは私がしゃがんで相手をすると大喜びで飛び跳ね、しまいには決まって私の背中によじ登る。犬は群れの習性が刷り込まれているので、飼い主一家の下っ端をまず乗っ取ろうと企んでいると聞いたことがあるが、私が家族で一番年下であることを察知していたのかも知れない。だが両親が離婚したときコムを手放さざるを得なくなり、知人のつてで面識のない一家に引き取ってもらうことになった。何も知らないコムは、旅立つ日の朝も出かける私にいつものように飛びつき、そそくさと出て行く私を不満げに見送った。それが私が目にしたコムの最後の姿で、その日以来いちども犬を飼っていない。
コムの引き取り先を親から聞き出し、こっそり様子を見いくことも考えたが、結局行かなかった。家の事情で追い出してしまった疚しさもあって、慣れない犬小屋で心細く鳴いているコムを見たくはなかった。飼い主の気持ちは身勝手なもので、逆に新しい家族にはやばやと馴染んでいたら、それはそれで複雑な心境になっていたに違いない。事情は違うけれど、向田邦子さんが愛犬を手放したときの心中が、少しわかるような気がする。胸のうちをそのまま文章にさらけ出す人ではないから、愛犬との別れのシーンが何故かソーセージのエピソードになる。でも不思議なことに、人混みで這うようにソーセージを回収する彼女の背中を思い浮かべると、張り裂けそうな心痛がひしひしと伝わってくるのである。
向田邦子のエッセイの中で一つだけ、率直に心中を吐露した異色作がある。『手袋をさがす』という長めの随想で、気に入った手袋が見つからず、凍える手のまま寒い冬を越した意地っ張りな若き日の回想で始まる。自分の欠点や境遇が気に障り、そうやって苛立つ我が身を冷静に見つめてまた嘆息する。持ち前の人間観察力で自己分析を試みたなどと生易しいレベルではなく、人には決して向けない刃を自分の喉元に突きつけ、薄く血が滲み出すような痛々しさに満ちている。人並外れた才能で手に入れた人気放送作家の地位と、世間並の幸福に手が届かなかった喪失感のあいだで振り子のように揺れ続ける、満たされない渇望。若い頃に読んだときは息苦しさに面食らったが、今読み返すと、揺れたままの振り子を丸ごと受け入れ胸を張って生きる彼女の覚悟が沁みる。
 先日たまたま自宅に『向田邦子ベスト・エッセイ』という本を見つけて、懐かしくなった。向田邦子のエッセイに目を通すのは、学生の頃ハマって読破して以来だからほぼ30年ぶりだ。お父上が無愛想で怒りっぽい昔ながらの大和男子で、子煩悩な本心を素直に表現する術を知らない。『父の詫び状』を始めたびたびエッセイに登場する不器用な父を、向田邦子は上品なユーモアを交え淡々と描く。でも「ちょっといい話」的な毒抜きされたほのぼの感とは、すこし違う。人の心のひだを見通す眼差しは触れれば指を切りそうなくらい鋭いのに、刃先を他人に向けることは絶対にない。聡明で思いやりの染み渡った美しい文章は、いつも諦観に近い寂しさが仄かに漂う。
先日たまたま自宅に『向田邦子ベスト・エッセイ』という本を見つけて、懐かしくなった。向田邦子のエッセイに目を通すのは、学生の頃ハマって読破して以来だからほぼ30年ぶりだ。お父上が無愛想で怒りっぽい昔ながらの大和男子で、子煩悩な本心を素直に表現する術を知らない。『父の詫び状』を始めたびたびエッセイに登場する不器用な父を、向田邦子は上品なユーモアを交え淡々と描く。でも「ちょっといい話」的な毒抜きされたほのぼの感とは、すこし違う。人の心のひだを見通す眼差しは触れれば指を切りそうなくらい鋭いのに、刃先を他人に向けることは絶対にない。聡明で思いやりの染み渡った美しい文章は、いつも諦観に近い寂しさが仄かに漂う。『噛み癖』というエッセイで、彼女がかつて飼っていた大型犬の話が登場する。気立ての良い犬だったが、見境なく甘噛みする癖があった。隣人を追い回しては服の裾を駄目にしてしまう失態を繰り返し、ついに保健所送りになってしまった。見送る最後の日に大好物のソーセージを買い込んでくるが、駅で袋が破れホームにぶちまけてしまう。居心地の悪い視線を背に受けソーセージを拾い集めながら、人じゃないの犬が食べるの、いいヤツだったけど保健所に行かなくてはいけないの、と心のなかで叫ぶ。そのくだりを読みながら、むかし私の実家で飼っていた犬の二代目を思い出した。白黒モノトーンのおてんば娘で、名前をコムといった。
コムは私がしゃがんで相手をすると大喜びで飛び跳ね、しまいには決まって私の背中によじ登る。犬は群れの習性が刷り込まれているので、飼い主一家の下っ端をまず乗っ取ろうと企んでいると聞いたことがあるが、私が家族で一番年下であることを察知していたのかも知れない。だが両親が離婚したときコムを手放さざるを得なくなり、知人のつてで面識のない一家に引き取ってもらうことになった。何も知らないコムは、旅立つ日の朝も出かける私にいつものように飛びつき、そそくさと出て行く私を不満げに見送った。それが私が目にしたコムの最後の姿で、その日以来いちども犬を飼っていない。
コムの引き取り先を親から聞き出し、こっそり様子を見いくことも考えたが、結局行かなかった。家の事情で追い出してしまった疚しさもあって、慣れない犬小屋で心細く鳴いているコムを見たくはなかった。飼い主の気持ちは身勝手なもので、逆に新しい家族にはやばやと馴染んでいたら、それはそれで複雑な心境になっていたに違いない。事情は違うけれど、向田邦子さんが愛犬を手放したときの心中が、少しわかるような気がする。胸のうちをそのまま文章にさらけ出す人ではないから、愛犬との別れのシーンが何故かソーセージのエピソードになる。でも不思議なことに、人混みで這うようにソーセージを回収する彼女の背中を思い浮かべると、張り裂けそうな心痛がひしひしと伝わってくるのである。
向田邦子のエッセイの中で一つだけ、率直に心中を吐露した異色作がある。『手袋をさがす』という長めの随想で、気に入った手袋が見つからず、凍える手のまま寒い冬を越した意地っ張りな若き日の回想で始まる。自分の欠点や境遇が気に障り、そうやって苛立つ我が身を冷静に見つめてまた嘆息する。持ち前の人間観察力で自己分析を試みたなどと生易しいレベルではなく、人には決して向けない刃を自分の喉元に突きつけ、薄く血が滲み出すような痛々しさに満ちている。人並外れた才能で手に入れた人気放送作家の地位と、世間並の幸福に手が届かなかった喪失感のあいだで振り子のように揺れ続ける、満たされない渇望。若い頃に読んだときは息苦しさに面食らったが、今読み返すと、揺れたままの振り子を丸ごと受け入れ胸を張って生きる彼女の覚悟が沁みる。
キッシーの苦悩 [文学]
菅新内閣が誕生した。予定調和に終始した自民党総裁選のさなか、唯一新鮮だったのは岸田元政調会長のキャラが崩壊したことだ。突然メディアへ露出が増え上機嫌に質問に答え続けた挙句、ご自身をキッシーなどと呼び始めた。岸田さんて、こんな人だったか?
「〇っしー」は愛称の定番パターンである。さっしーとかふなっしーとか、バブルの頃にはアッシー君なるパシリが流行っていたが、元祖はたぶんネッシーだろう。ネス湖の怪物は最古の目撃例が6世紀の文献にまで遡るというから、思いのほか歴史が古い。スコットランド地方の民話には湖に住む魔物がよく登場するそうで、もともと文化的に親和性が高いようである。ちなみに女性名Agnesの愛称の1つがNessieがなので、英語圏の人の耳にはもともと馴染みがある語感なのかもしれない。
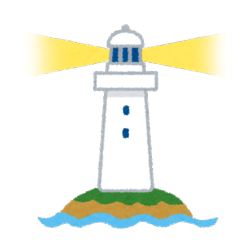 ネッシーに触発されたかどうか定かではないが、米国の作家レイ・ブラッドベリの代表作の1つに、海の底に棲む独りぼっちの怪獣を描いた作品がある。『The Fog Horn(霧笛)』という短編で、まるで一遍の詩を読んでいるかのような美しい文章が紡ぎ出す、哀しく幻想的な物語だ。
ネッシーに触発されたかどうか定かではないが、米国の作家レイ・ブラッドベリの代表作の1つに、海の底に棲む独りぼっちの怪獣を描いた作品がある。『The Fog Horn(霧笛)』という短編で、まるで一遍の詩を読んでいるかのような美しい文章が紡ぎ出す、哀しく幻想的な物語だ。
秋の霧に包まれた灯台を舞台に、灯台守が新人の同僚に不思議な話を語り聞かせる。太古の爬虫類最後の生き残りである怪獣は、気の遠くなるような孤独の年月に倦んだある日、はるか彼方から届く同胞の呼声を耳にする。居ても立ってもいられず深海の棲家を離れ、浅瀬に向かい少しずつ辛抱強く、何キロにも及ぶ道中を泳ぎ続ける。ついに海面から姿を表した怪獣は、目の前に屹立する一基の灯台を発見する。彼自身とそっくりの巨大な長い首と、そのてっぺんで煌めく眼光。そして、懐かしさに身が震える重く鈍い呼声。怪獣は、狂おしい思いで喉を振り絞り、灯台が発する霧笛に応える。
この様子を見た灯台守は、同僚にこう語る。
これが人生なのさ。二度と帰ってこない誰かをずっと待ち続けていたり。報われない愛をずっと何かに捧げていたり。そしてやがて、その愛する何かを叩きのめしてしまいたくなる。もうそれ以上、自分が傷つくことがないように。
そして、気まぐれに霧笛のスイッチを停止する。何の前触れもなく沈黙した灯台の「拒絶」に、募りに募った怪物の切なる想いは爆発する。逆上した怪物に激突された灯台は、ひとたまりもなく木っ端微塵に崩壊する。
岸田さんはもともと安倍元総理にとって後継者候補イチオシと言われていたが、結局菅さんに株を奪われた。総裁選のあいだつとめて親しみある人柄を演出しようと頑張っておられたが、岸田さんには不釣り合いに軽いキャラを狙い過ぎたようで、逆に必死さが滲み出て痛ましかった。気がつくと見放されていた岸田さんの不器用な笑顔に、突然沈黙した灯台の正体に気付いた怪獣の傷心がかぶる。無邪気にキッシーなどと名乗っておられたが、住処の暗い静けさに慣れすぎてしまったか、海上に浮上するタイミングがいささか遅過ぎたようである。悲しさのあまり灯台を叩き潰しに行くような人では、たぶんないと思うが。
「〇っしー」は愛称の定番パターンである。さっしーとかふなっしーとか、バブルの頃にはアッシー君なるパシリが流行っていたが、元祖はたぶんネッシーだろう。ネス湖の怪物は最古の目撃例が6世紀の文献にまで遡るというから、思いのほか歴史が古い。スコットランド地方の民話には湖に住む魔物がよく登場するそうで、もともと文化的に親和性が高いようである。ちなみに女性名Agnesの愛称の1つがNessieがなので、英語圏の人の耳にはもともと馴染みがある語感なのかもしれない。
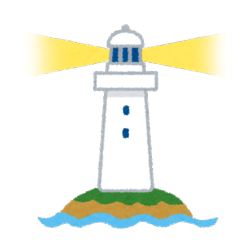 ネッシーに触発されたかどうか定かではないが、米国の作家レイ・ブラッドベリの代表作の1つに、海の底に棲む独りぼっちの怪獣を描いた作品がある。『The Fog Horn(霧笛)』という短編で、まるで一遍の詩を読んでいるかのような美しい文章が紡ぎ出す、哀しく幻想的な物語だ。
ネッシーに触発されたかどうか定かではないが、米国の作家レイ・ブラッドベリの代表作の1つに、海の底に棲む独りぼっちの怪獣を描いた作品がある。『The Fog Horn(霧笛)』という短編で、まるで一遍の詩を読んでいるかのような美しい文章が紡ぎ出す、哀しく幻想的な物語だ。秋の霧に包まれた灯台を舞台に、灯台守が新人の同僚に不思議な話を語り聞かせる。太古の爬虫類最後の生き残りである怪獣は、気の遠くなるような孤独の年月に倦んだある日、はるか彼方から届く同胞の呼声を耳にする。居ても立ってもいられず深海の棲家を離れ、浅瀬に向かい少しずつ辛抱強く、何キロにも及ぶ道中を泳ぎ続ける。ついに海面から姿を表した怪獣は、目の前に屹立する一基の灯台を発見する。彼自身とそっくりの巨大な長い首と、そのてっぺんで煌めく眼光。そして、懐かしさに身が震える重く鈍い呼声。怪獣は、狂おしい思いで喉を振り絞り、灯台が発する霧笛に応える。
この様子を見た灯台守は、同僚にこう語る。
これが人生なのさ。二度と帰ってこない誰かをずっと待ち続けていたり。報われない愛をずっと何かに捧げていたり。そしてやがて、その愛する何かを叩きのめしてしまいたくなる。もうそれ以上、自分が傷つくことがないように。
そして、気まぐれに霧笛のスイッチを停止する。何の前触れもなく沈黙した灯台の「拒絶」に、募りに募った怪物の切なる想いは爆発する。逆上した怪物に激突された灯台は、ひとたまりもなく木っ端微塵に崩壊する。
岸田さんはもともと安倍元総理にとって後継者候補イチオシと言われていたが、結局菅さんに株を奪われた。総裁選のあいだつとめて親しみある人柄を演出しようと頑張っておられたが、岸田さんには不釣り合いに軽いキャラを狙い過ぎたようで、逆に必死さが滲み出て痛ましかった。気がつくと見放されていた岸田さんの不器用な笑顔に、突然沈黙した灯台の正体に気付いた怪獣の傷心がかぶる。無邪気にキッシーなどと名乗っておられたが、住処の暗い静けさに慣れすぎてしまったか、海上に浮上するタイミングがいささか遅過ぎたようである。悲しさのあまり灯台を叩き潰しに行くような人では、たぶんないと思うが。
当たり前だったはずのこと [文学]
カフカやカミュの小説は、不条理の文学と評されることがある。ただ、理不尽でわけのわからないものを不条理と一言で片付けてしまうと、何を理解したことにもならない。不条理を突き詰めることは、そもそも「条理」とは何なのか、を見つめ直すことでもある。
 時節柄、カミュの『ペスト』が急に売れ出しているらしい。カミュの作品は『異邦人』しか手を出したことがなかったが、私も流行りに乗じて読んでみた。新潮文庫の訳書は、フランス語の文章構造に寄せる翻訳家のリスペクトが止まらないのか、格調高すぎる日本語がいささか読みづらい。だが、後半から終盤になると物語の吸引力に呑み込まれ、それも気にならなくなる。舞台は1940年代、アルジェリアの港町オラン。同名の街は実在するそうだが、小説で語られるペストの流行は作者の創作である。しかし、ルポルタージュ風の淡々とした筆致が醸すリアリティが生々しい。
時節柄、カミュの『ペスト』が急に売れ出しているらしい。カミュの作品は『異邦人』しか手を出したことがなかったが、私も流行りに乗じて読んでみた。新潮文庫の訳書は、フランス語の文章構造に寄せる翻訳家のリスペクトが止まらないのか、格調高すぎる日本語がいささか読みづらい。だが、後半から終盤になると物語の吸引力に呑み込まれ、それも気にならなくなる。舞台は1940年代、アルジェリアの港町オラン。同名の街は実在するそうだが、小説で語られるペストの流行は作者の創作である。しかし、ルポルタージュ風の淡々とした筆致が醸すリアリティが生々しい。
医師リウーはいち早くペストの兆候を見抜くが、当初は市民も行政もことの深刻さを認めようとしない。平穏な毎日に慣れすぎたばかりに、目の前の異常事態を正確に把握する想像力が機能せず、初動が遅れて事態を悪化させる(どこか記憶に新しい)。しかし死者数がうなぎ上りに増え、ついに街全体が隔離され外界との接触が封鎖される。オランの人々は、会いたい人に会えない狂おしさに苛まれ、いつ我が身にやってくるかわからないペストの恐怖に震える。当たり前だったはずの何でもない生活が、何の前触れもなく手の届かないところに消えてしまう。
奪われた「当たり前」は、日々の暮らしだけではない。ペストは人々の思想や価値観を試し揺さぶる。疫病は信心を失った民衆に神が突き付けた挑戦だ、と市民を断罪する街の神父がいる。しかし罪なき子供の命まで無慈悲に奪うペストの魔の手を目の当たりにしてから、彼は自身の信仰に確信を失い心理的に追い詰められていく。
個人に死の制裁を下す社会を受け入れることができず、検事の父と袂を分かった男がいる。無差別に死刑宣告を下すペストの猛威に社会の偽善を重ねた彼は、危険を承知で患者の看護を志願し、リウーと行動を共にする。
人知れず警察の追跡に怯え生きてきた、後ろ暗い過去を持つ男がいる。ペストに追われる恐怖に誰もが慄く中、立場が反転したことに気付いた彼は溌剌と生き返る。しかし街がついにペストから解放されたとき、市民が喜びに沸く傍らで独り精神の均衡を失う。
物語では医療従事者の献身的な努力が描かれるが、『ペスト』の語り部は彼らをことさら英雄視はしない。医師リウーは平時から人の死と向き合い、救える命と救えなかった命の狭間で自らの限界を見つめてきた男である。リウーが神の条理を信じず自分なりの死生観を築いたとすれば、検事たる父の権威を受け入れられなかった男は、社会の条理を受け入れず自身の正義を貫いた人物である。隔離された街で蔓延する疫病に対峙する非日常の中で、二人はやがて強い絆で結ばれていく。
条理と不条理を隔てる曖昧な境界を平時から直視し考え続けてきた人間だけが、疫病の猛威に敢然と立ち向かうことができる。『ペスト』は不条理の文学というより、条理(当たり前だったはずのこと)の脆さについての物語だ。ペストの終息は不条理の終焉ではなく、顕在化していた条理のほころびが再び人々の心の深層に潜り込んだに過ぎない。語り部が幕切れでペストの再来を匂わせているのは、そのせいである。
新型コロナのパンデミックで、私たちは当たり前だったはずの生活を当たり前に送ることができなくなっている。でも、当たり前すぎて今まで考えもしなかったことについて、今だからこそ真剣に思いを巡らすことができる。それで目の前の問題が溶けて失くなるわけではないが、なかなか晴れない霧の彼方に、微かな光明くらいは浮かび上がってくるも知れない。
 時節柄、カミュの『ペスト』が急に売れ出しているらしい。カミュの作品は『異邦人』しか手を出したことがなかったが、私も流行りに乗じて読んでみた。新潮文庫の訳書は、フランス語の文章構造に寄せる翻訳家のリスペクトが止まらないのか、格調高すぎる日本語がいささか読みづらい。だが、後半から終盤になると物語の吸引力に呑み込まれ、それも気にならなくなる。舞台は1940年代、アルジェリアの港町オラン。同名の街は実在するそうだが、小説で語られるペストの流行は作者の創作である。しかし、ルポルタージュ風の淡々とした筆致が醸すリアリティが生々しい。
時節柄、カミュの『ペスト』が急に売れ出しているらしい。カミュの作品は『異邦人』しか手を出したことがなかったが、私も流行りに乗じて読んでみた。新潮文庫の訳書は、フランス語の文章構造に寄せる翻訳家のリスペクトが止まらないのか、格調高すぎる日本語がいささか読みづらい。だが、後半から終盤になると物語の吸引力に呑み込まれ、それも気にならなくなる。舞台は1940年代、アルジェリアの港町オラン。同名の街は実在するそうだが、小説で語られるペストの流行は作者の創作である。しかし、ルポルタージュ風の淡々とした筆致が醸すリアリティが生々しい。医師リウーはいち早くペストの兆候を見抜くが、当初は市民も行政もことの深刻さを認めようとしない。平穏な毎日に慣れすぎたばかりに、目の前の異常事態を正確に把握する想像力が機能せず、初動が遅れて事態を悪化させる(どこか記憶に新しい)。しかし死者数がうなぎ上りに増え、ついに街全体が隔離され外界との接触が封鎖される。オランの人々は、会いたい人に会えない狂おしさに苛まれ、いつ我が身にやってくるかわからないペストの恐怖に震える。当たり前だったはずの何でもない生活が、何の前触れもなく手の届かないところに消えてしまう。
奪われた「当たり前」は、日々の暮らしだけではない。ペストは人々の思想や価値観を試し揺さぶる。疫病は信心を失った民衆に神が突き付けた挑戦だ、と市民を断罪する街の神父がいる。しかし罪なき子供の命まで無慈悲に奪うペストの魔の手を目の当たりにしてから、彼は自身の信仰に確信を失い心理的に追い詰められていく。
個人に死の制裁を下す社会を受け入れることができず、検事の父と袂を分かった男がいる。無差別に死刑宣告を下すペストの猛威に社会の偽善を重ねた彼は、危険を承知で患者の看護を志願し、リウーと行動を共にする。
人知れず警察の追跡に怯え生きてきた、後ろ暗い過去を持つ男がいる。ペストに追われる恐怖に誰もが慄く中、立場が反転したことに気付いた彼は溌剌と生き返る。しかし街がついにペストから解放されたとき、市民が喜びに沸く傍らで独り精神の均衡を失う。
物語では医療従事者の献身的な努力が描かれるが、『ペスト』の語り部は彼らをことさら英雄視はしない。医師リウーは平時から人の死と向き合い、救える命と救えなかった命の狭間で自らの限界を見つめてきた男である。リウーが神の条理を信じず自分なりの死生観を築いたとすれば、検事たる父の権威を受け入れられなかった男は、社会の条理を受け入れず自身の正義を貫いた人物である。隔離された街で蔓延する疫病に対峙する非日常の中で、二人はやがて強い絆で結ばれていく。
条理と不条理を隔てる曖昧な境界を平時から直視し考え続けてきた人間だけが、疫病の猛威に敢然と立ち向かうことができる。『ペスト』は不条理の文学というより、条理(当たり前だったはずのこと)の脆さについての物語だ。ペストの終息は不条理の終焉ではなく、顕在化していた条理のほころびが再び人々の心の深層に潜り込んだに過ぎない。語り部が幕切れでペストの再来を匂わせているのは、そのせいである。
新型コロナのパンデミックで、私たちは当たり前だったはずの生活を当たり前に送ることができなくなっている。でも、当たり前すぎて今まで考えもしなかったことについて、今だからこそ真剣に思いを巡らすことができる。それで目の前の問題が溶けて失くなるわけではないが、なかなか晴れない霧の彼方に、微かな光明くらいは浮かび上がってくるも知れない。
幸福の代償 [文学]
 『ゲド戦記』を書いたアメリカの作家アーシュラ・ル=グウィンの短編に『オメラスから歩み去る者たち』という不思議な作品がある。オメラスとは犯罪や戦争と無縁な平和に満たされた架空の街で、人々が思い思いに夏の到来を祝って集う華やいだ日常が綴られる。だがこの街の一角にただ一人、その幸福を分かち合うことの許されない孤独な子供がいる。子供は窓のない小部屋に幽閉されたまま劣悪な環境に放置され、気遣いの言葉一つかけてもらうことすら叶わない。オメラスで育つ少年少女は遅かれ早かれそんな街の秘密を知り、当然ながら憤りや悲しみに震える者もいる。だが彼らはやがて、子供が置かれた現実を直視することを止める。何故なら、不幸な子供の犠牲の上にこそ街の平穏な秩序が支えられていると気付いているからだ。もし子供を救い自由のもとに解き放てば、オメラスの人々が享受する幸福の日々は遠からず終わりを告げる。
『ゲド戦記』を書いたアメリカの作家アーシュラ・ル=グウィンの短編に『オメラスから歩み去る者たち』という不思議な作品がある。オメラスとは犯罪や戦争と無縁な平和に満たされた架空の街で、人々が思い思いに夏の到来を祝って集う華やいだ日常が綴られる。だがこの街の一角にただ一人、その幸福を分かち合うことの許されない孤独な子供がいる。子供は窓のない小部屋に幽閉されたまま劣悪な環境に放置され、気遣いの言葉一つかけてもらうことすら叶わない。オメラスで育つ少年少女は遅かれ早かれそんな街の秘密を知り、当然ながら憤りや悲しみに震える者もいる。だが彼らはやがて、子供が置かれた現実を直視することを止める。何故なら、不幸な子供の犠牲の上にこそ街の平穏な秩序が支えられていると気付いているからだ。もし子供を救い自由のもとに解き放てば、オメラスの人々が享受する幸福の日々は遠からず終わりを告げる。一頃流行ったハーバード大マイケル・サンデル教授の本では、ベンサムの功利主義を論ずる題材の一つとしてオメラスの物語が紹介される。英国の思想家ジェレミ・ベンサムは「最大多数の最大幸福」を唱えたことで有名だ。雑に要約すれば、たとえ一部の個人の犠牲が伴っても社会全体の幸福(快楽)を最大化する施政が善である、ということになる。囚われの子供一人の苦しみと引き換えに社会の幸福が担保されるオメラスの世界は、ベンサム的価値基準では肯定されるが、現代的な人権意識に照らせば到底容認されない。サンデルによるこの問題提起は、ほとんどそのままの形でウィルス水際対策に現実化した。クルーズ船の乗客や武漢帰還者を隔離すれば国土の安全は保たれるが、検疫期間が長引けば当事者の人権は著しく制限される。
ただ、ル=グウィンの思考の源泉はもっと深いところにある。オメラスの人々は賢人でも聖人でもなく、欲も弱さも併せ持った私たちと同じ人間だ。彼らは至上の幸福を手にしながら、心の底ではその幸福がいつ潰えるかと怖れている。御伽話のような桃源郷を信じるほどウブではないから、幸福を維持するには相応の代償が必要だと考える。作者は、幽閉された子供がどうやって社会の幸福に奉仕しているのか、その仕組みについては一切触れない。なぜなら、子供の犠牲が続く限り社会の安寧が担保されると人々が「信じている」こと、その盲目的な信念の裏に潜む秩序崩壊への怖れこそが、物語の本質だからだ。
日本各地で新型コロナの感染者が見つかると、ニュース速報が飛び交い感染経路や行動履歴がたちまち詳らかにされる。情報が速やかに共有されるのは健全な社会の証であるが、緊迫感あふれる連日の報道は、正体不明のウィルス蔓延が徐々に社会を蝕んでいくかのような終末論的な世界像をわざわざ醸成している感もある。オメラスの人々が幸福な日常を失う不安から一人の子供の犠牲を黙認したように、新型コロナに対する過敏な反応がエスカレートすれば社会全体が判断力のバランスを失いかねない。品薄のマスクを求めて店頭で小競り合いになったり、地下鉄で咳込む乗客と口論になったり、そういったできごとがもはや対岸の火事ではなくなっている。感染症そのもののリスクより、社会の理性が試されるフェーズに入りつつあるのではないか。
10ページに満たないオメラスの物語は、ひときわ謎めいた一節で唐突に終わる。最後に語られるのは、囚われた子供の不条理を受け入れることができず、人知れず街を出て行く少年少女たちだ。彼らがどんな暮らしを求めどこを目指すのか、何も明らかにされない。だがオメラスを去る者たちは、社会全体がスルーする理不尽を容認せず、その矛盾を考え続ける人々である。ル=グウィンが人類に託した、一抹の希望を見る思いがする。



