オッペンハイマー:映画編 [映画・漫画]
クリストファー・ノーラン監督の映画『オッペンハイマー』が日本で公開され、ようやく待望の大作を観る機会を得た。この作品に関しては、「広島と長崎の惨禍が描かれていないのがけしからん」という論評を時折り耳にするが、いささか的外れな批判である。被爆国目線で何か言っておくのが日本人の見識ということかもしれないが、映画はあくまでオッペンハイマーの半生を彼自身の内面に照らして描いたフィクションであり、原爆開発のドキュメンタリーではない。
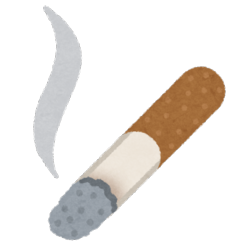 主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
映画の原案となった伝記本を読むと、内面が複雑に揺れ一筋縄では読み解き難いオッペンハイマー像が浮かび上がる(原著編で書いた)。映画『オッペンハイマー』はそんな彼の人物像を丁寧に再構築する。原爆開発を成功に導いた天才科学者が後に罪の意識から反核思想に転向する、といった直線的なヒューマンドラマでは全くない。象徴的なのは、原爆投下成功の報せに沸くロスアラモスの研究所で、オッペンハイマーが職場の同僚たちから拍手喝采で称えられる場面だ。歓喜に足を踏み鳴らす喧騒に迎えられ演壇に立った彼は、狂喜する聴衆の中に熱線が焼き尽くす被爆者の幻影を見る。以後オッペンハイマーにとって、英雄の栄光は破壊神の汚名と不可分になった。
オッペンハイマーが熱線の幻を見るシーンが、終盤にもう一度だけ登場する。原子力委員会の聴聞会で、22万人を超える広島と長崎の甚大な犠牲の事実を突きつけられ、彼が良心の呵責を認めた場面だ。ならばなぜ原爆の実戦使用に反対しなかったのか? 原爆を容認しながらなぜ戦後水爆開発に抵抗し続けたのか? 畳みかけられる詰問にオッペンハイマーは必死で正当化を試みるが、己の矛盾に心のどこかで気付いている。ひどく混乱した彼の頭中で観衆の踏み鳴らす靴音がフラッシュバックし、聴聞会の小さな部屋を眩い閃光が貫く。場面は上院公聴会の時間軸と目まぐるしく交差し、オッペンハイマーの偽善を罵るストロースの怒号がかぶる。史実の舞台装置を借りてオッペンハイマーを苛む心の軋みを鮮やかに可視化した、息を呑むクライマックスである。
オッペンハイマーを賞賛も非難もせず、彼の葛藤と矛盾を渾然一体のまま白日の下に晒すことが、この映画の着地点だ。幕切れの直前、ロスアラモスを勇退しプリンストンの高等研究所長に招かれたばかりのオッペンハイマーがアインシュタインと交わした会話が明かされる。当時のアインシュタインはすでに、本人が創始に関わった量子力学に背を向ける孤高の人であった。アインシュタインは、自ら生み出した魔物を持て余すオッペンハイマーに同じ運命の影を嗅ぎ取り、のちに訪れる試練を仄めかす暗い予言を告げる。この会話自体はおそらくフィクションだが、三時間にわたる長尺に深い余韻を残す見事なエンディングだ。
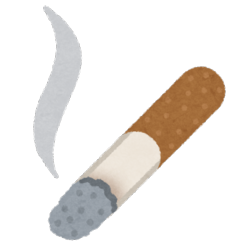 主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。映画の原案となった伝記本を読むと、内面が複雑に揺れ一筋縄では読み解き難いオッペンハイマー像が浮かび上がる(原著編で書いた)。映画『オッペンハイマー』はそんな彼の人物像を丁寧に再構築する。原爆開発を成功に導いた天才科学者が後に罪の意識から反核思想に転向する、といった直線的なヒューマンドラマでは全くない。象徴的なのは、原爆投下成功の報せに沸くロスアラモスの研究所で、オッペンハイマーが職場の同僚たちから拍手喝采で称えられる場面だ。歓喜に足を踏み鳴らす喧騒に迎えられ演壇に立った彼は、狂喜する聴衆の中に熱線が焼き尽くす被爆者の幻影を見る。以後オッペンハイマーにとって、英雄の栄光は破壊神の汚名と不可分になった。
オッペンハイマーが熱線の幻を見るシーンが、終盤にもう一度だけ登場する。原子力委員会の聴聞会で、22万人を超える広島と長崎の甚大な犠牲の事実を突きつけられ、彼が良心の呵責を認めた場面だ。ならばなぜ原爆の実戦使用に反対しなかったのか? 原爆を容認しながらなぜ戦後水爆開発に抵抗し続けたのか? 畳みかけられる詰問にオッペンハイマーは必死で正当化を試みるが、己の矛盾に心のどこかで気付いている。ひどく混乱した彼の頭中で観衆の踏み鳴らす靴音がフラッシュバックし、聴聞会の小さな部屋を眩い閃光が貫く。場面は上院公聴会の時間軸と目まぐるしく交差し、オッペンハイマーの偽善を罵るストロースの怒号がかぶる。史実の舞台装置を借りてオッペンハイマーを苛む心の軋みを鮮やかに可視化した、息を呑むクライマックスである。
オッペンハイマーを賞賛も非難もせず、彼の葛藤と矛盾を渾然一体のまま白日の下に晒すことが、この映画の着地点だ。幕切れの直前、ロスアラモスを勇退しプリンストンの高等研究所長に招かれたばかりのオッペンハイマーがアインシュタインと交わした会話が明かされる。当時のアインシュタインはすでに、本人が創始に関わった量子力学に背を向ける孤高の人であった。アインシュタインは、自ら生み出した魔物を持て余すオッペンハイマーに同じ運命の影を嗅ぎ取り、のちに訪れる試練を仄めかす暗い予言を告げる。この会話自体はおそらくフィクションだが、三時間にわたる長尺に深い余韻を残す見事なエンディングだ。
小説の映画化 [映画・漫画]
大ヒットした小説が鳴り物入りで映画化されることは多いが、映像化された作品が原作に匹敵する評価を得ることは稀だ。評価が割れるならまだ良い方で、大コケすることも少なくない。
 文学は文字情報だけで成り立っているので、登場人物の外見や風景など視覚情報は読者の想像力に委ねられる。先に原作を読んでしまうと読者なりの世界観が確立されてしまうので、映像化作品に違和感を感じると没入できない。例外は『ハリーポッター』のようにシリーズ初期に映画がヒットしたケースで、今やダニエル・ラドクリフのハリーやエマ・ワトソンのハーマイオニーを思い浮かべずに小説版を読むほうが難しい。
文学は文字情報だけで成り立っているので、登場人物の外見や風景など視覚情報は読者の想像力に委ねられる。先に原作を読んでしまうと読者なりの世界観が確立されてしまうので、映像化作品に違和感を感じると没入できない。例外は『ハリーポッター』のようにシリーズ初期に映画がヒットしたケースで、今やダニエル・ラドクリフのハリーやエマ・ワトソンのハーマイオニーを思い浮かべずに小説版を読むほうが難しい。
キューブリック監督の『シャイニング』を原作者スティーブヴン・キングが「エンジンを積んでいないキャデラックのようだ」と酷評したのはよく知られた話である。映像は壮麗だが物語の推進力が根本的に欠けている、と言うわけだ。『シャイニング』に関しては監督と原作者の美学が違いすぎるわけで必ずしも良し悪しでは整理できないが、一般にキングのホラー作品の映画化は原作の魅力にはるか及ばない。もともとキングのホラーはハロウィン的なB級テイストが基本なので、そのまま映像化するとチープに見えるのはむしろ必然である。
スティーヴン・キングを初めて読む人は、ホラー要素の薄い作品から入った方がいい。その方が、キング本来の魅力である物語の圧倒的な面白さと人物造形のリアリティ、そして読後感の深い余韻に没入しやすい。キングには『デッドゾーン』『スタンドバイミー』『ショーシャンクの空に』『グリーンマイル』といった非ホラーの名作がいくつもある。邪悪なモンスターが登場しないおかげでキング本来の文学的魅力が輝いているためか、各々映画版も高く評価されている傑作ばかりだ。彼のホラー作品の映像化で成功した数少ない例は『ミザリー』だが、この物語は実質的に登場人物二人の駆け引きで読者を引き込む密室劇で、もともと高度に文学的な題材なのである。
アンソニー・ホプキンスとエマ・トンプソンの燻し銀のごとき共演が光った『日の名残り』のように、映画としても最上級の賞賛を浴びた文学作品も存在する。とは言え、この映画はカズオ・イシグロの同名小説とは別物と考えた方がいいかもしれない。語り手の言いよどみや隠しごとが見えない真実を紡いでゆくイシグロの小説は、原理的に映像化が困難だからである。執事としての職業的な誇りと、その陰で自ら封印し続けた恋心の葛藤が、奇しくも同じ晩にクライマックスを迎え主人公の心中で混線し一体化する。イシグロが『日の名残り』に仕掛けたこの離れ業は、行間を読者の想像力に委ねる小説の中でしか体験することができない。
言葉はある意味で視覚情報より雄弁である。ディーリア・オーウェンズの小説『ザリガニの鳴くところ』は、主人公の少女が暮らす森と湿地の描写が濃密で、文面から音や匂いまでもが立ち昇るかのようだ。小説で描かれる大自然は、普段は優しく美しく、しかし時に不吉で荒々しく、人への渇望と恐れに揺れる孤独な少女の心象をなぞるように千変万化する。本作の映画版は雄大な風景の映像が堪能できる美しい一編だが、本を読んでから映画を見ると、むしろ映像表現の限界に思いが及ぶ。
原作モノの映画は、未知の文学世界に扉を開くきっかけだと思えばいい。一冊の長編が上手に編集され二時間にダイジェストされているから、手軽に要約を知る手段としてコスパがいい。一見して気に入らなければスルーすればいいし、気に入れば原作を読んでみるのもいい。私は映画の『ショーシャンクの空に』を見て小説を手に取って以来、いまも変わらぬスティーヴン・キングのファンになった。
 文学は文字情報だけで成り立っているので、登場人物の外見や風景など視覚情報は読者の想像力に委ねられる。先に原作を読んでしまうと読者なりの世界観が確立されてしまうので、映像化作品に違和感を感じると没入できない。例外は『ハリーポッター』のようにシリーズ初期に映画がヒットしたケースで、今やダニエル・ラドクリフのハリーやエマ・ワトソンのハーマイオニーを思い浮かべずに小説版を読むほうが難しい。
文学は文字情報だけで成り立っているので、登場人物の外見や風景など視覚情報は読者の想像力に委ねられる。先に原作を読んでしまうと読者なりの世界観が確立されてしまうので、映像化作品に違和感を感じると没入できない。例外は『ハリーポッター』のようにシリーズ初期に映画がヒットしたケースで、今やダニエル・ラドクリフのハリーやエマ・ワトソンのハーマイオニーを思い浮かべずに小説版を読むほうが難しい。キューブリック監督の『シャイニング』を原作者スティーブヴン・キングが「エンジンを積んでいないキャデラックのようだ」と酷評したのはよく知られた話である。映像は壮麗だが物語の推進力が根本的に欠けている、と言うわけだ。『シャイニング』に関しては監督と原作者の美学が違いすぎるわけで必ずしも良し悪しでは整理できないが、一般にキングのホラー作品の映画化は原作の魅力にはるか及ばない。もともとキングのホラーはハロウィン的なB級テイストが基本なので、そのまま映像化するとチープに見えるのはむしろ必然である。
スティーヴン・キングを初めて読む人は、ホラー要素の薄い作品から入った方がいい。その方が、キング本来の魅力である物語の圧倒的な面白さと人物造形のリアリティ、そして読後感の深い余韻に没入しやすい。キングには『デッドゾーン』『スタンドバイミー』『ショーシャンクの空に』『グリーンマイル』といった非ホラーの名作がいくつもある。邪悪なモンスターが登場しないおかげでキング本来の文学的魅力が輝いているためか、各々映画版も高く評価されている傑作ばかりだ。彼のホラー作品の映像化で成功した数少ない例は『ミザリー』だが、この物語は実質的に登場人物二人の駆け引きで読者を引き込む密室劇で、もともと高度に文学的な題材なのである。
アンソニー・ホプキンスとエマ・トンプソンの燻し銀のごとき共演が光った『日の名残り』のように、映画としても最上級の賞賛を浴びた文学作品も存在する。とは言え、この映画はカズオ・イシグロの同名小説とは別物と考えた方がいいかもしれない。語り手の言いよどみや隠しごとが見えない真実を紡いでゆくイシグロの小説は、原理的に映像化が困難だからである。執事としての職業的な誇りと、その陰で自ら封印し続けた恋心の葛藤が、奇しくも同じ晩にクライマックスを迎え主人公の心中で混線し一体化する。イシグロが『日の名残り』に仕掛けたこの離れ業は、行間を読者の想像力に委ねる小説の中でしか体験することができない。
言葉はある意味で視覚情報より雄弁である。ディーリア・オーウェンズの小説『ザリガニの鳴くところ』は、主人公の少女が暮らす森と湿地の描写が濃密で、文面から音や匂いまでもが立ち昇るかのようだ。小説で描かれる大自然は、普段は優しく美しく、しかし時に不吉で荒々しく、人への渇望と恐れに揺れる孤独な少女の心象をなぞるように千変万化する。本作の映画版は雄大な風景の映像が堪能できる美しい一編だが、本を読んでから映画を見ると、むしろ映像表現の限界に思いが及ぶ。
原作モノの映画は、未知の文学世界に扉を開くきっかけだと思えばいい。一冊の長編が上手に編集され二時間にダイジェストされているから、手軽に要約を知る手段としてコスパがいい。一見して気に入らなければスルーすればいいし、気に入れば原作を読んでみるのもいい。私は映画の『ショーシャンクの空に』を見て小説を手に取って以来、いまも変わらぬスティーヴン・キングのファンになった。
Road to Perdition [映画・漫画]
 TBSの『VIVANT』最終話を見ていて、20年ほど前に見た映画『Road to Perdition』を思い出した。雑にまとめれば、大恐慌直後のアメリカ中西部を舞台に一匹狼の殺し屋がギャングと渡り合う話である。トム・ハンクスとポール・ニューマンに若き日のダニエル・クレイグ(まだジェームス・ボンドでなかったころ)が絡む、どこまでも渋く暗くそして哀しい映画である。
TBSの『VIVANT』最終話を見ていて、20年ほど前に見た映画『Road to Perdition』を思い出した。雑にまとめれば、大恐慌直後のアメリカ中西部を舞台に一匹狼の殺し屋がギャングと渡り合う話である。トム・ハンクスとポール・ニューマンに若き日のダニエル・クレイグ(まだジェームス・ボンドでなかったころ)が絡む、どこまでも渋く暗くそして哀しい映画である。ハンクス演じる凄腕の殺し屋サリヴァンは、孤児だった幼少時ニューマン演じるギャングのルーニーに引き取られ、我が子同然に育てられる。しかしそれが面白くないルーニーの実子コナーは、一計を案じサリヴァンを妻子もろとも消し去ろうとする。サリヴァン本人と長男マイケルは難を逃れるが、妻と次男は殺されてしまう。コナーへの復讐を誓うサリヴァンと、不良息子の蛮行に激怒しつつ実の息子を切り捨てられないルーニー。ギャングの非情な掟の中で、二人はやがてどちらも望んでいなかった直接対決へと追い込まれていく。
『Road to…』は、さまざまな父子の愛情と葛藤が交錯する映画だ。ルーニーとサリヴァン、ルーニーとコナー、そしてサリヴァンと幼いマイケル。よそよそしい父に孤独感を募らせていたマイケルだが、それが血塗られた己の道から息子を遠ざける父の想いに他ならないと気付くことになる。サリヴァンを追う刺客から父子二人で逃亡する道中の果て、ついに刺客と対峙した息子マイケル。しかし、彼は銃の引き金を引くことができない。マイケルが殺し屋の血を受け継がなかった事実を最期に目にしたサリヴァンは、息子の腕の中でホッとしたように息を引き取る。
物語の山場、息子同然のサリヴァンから銃口を向けられた絶体絶命のルーニーが、「I'm glad it's you=(俺を殺るのが)お前で良かった」と呟くシーンがある。『VIVANT』最終話でよく似た台詞が出てきたので、そこでふと『Road to…』を思い出したのである。実子と育ての子の確執というサイドストーリーも、二つの物語に共通している。
ただ『VIVANT』の作者は、国を守るためであれば手段を選ばない「別班」的哲学を、どちらかというと肯定的に描いている節がある。組織の掟が人間性を圧し潰す悲劇を描いた『Road to…』とは対照的だ。『VIVANT』はエンタメとしては破格に面白かったが、全体主義的な美学が無邪気に匂う甘さだけが、どこか喉に刺さった小骨のようにスッキリしない。
ザ・ホエール [映画・漫画]
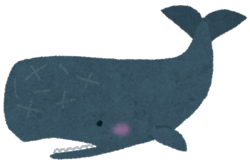 映画『ザ・ホエール』のことを書きたい。(かつての)二枚目俳優ブレンダン・フレイザーが肥満で歩行もままならない巨漢を演じてアカデミー主演男優賞を勝ち取った映画だが、日本ではあまり話題になっていない。題名はクジラだが、本物の鯨は一切出てこない。物語で重要な縦糸を紡ぐメルヴィルの『白鯨』から来ているが、鯨はおそらく主人公チャーリー自身のメタファーでもある。
映画『ザ・ホエール』のことを書きたい。(かつての)二枚目俳優ブレンダン・フレイザーが肥満で歩行もままならない巨漢を演じてアカデミー主演男優賞を勝ち取った映画だが、日本ではあまり話題になっていない。題名はクジラだが、本物の鯨は一切出てこない。物語で重要な縦糸を紡ぐメルヴィルの『白鯨』から来ているが、鯨はおそらく主人公チャーリー自身のメタファーでもある。チャーリーは、かつて同性の恋人と駆け落ちし妻子を捨てた男である。しかしその恋人が自ら命を絶ったトラウマから過食が止まらず、極度の肥満で心臓疾患を患っている。死を予期したチャーリーが娘との絆を取り戻そうとするところから物語が始まり、彼の昇天を想起させる結末で幕を下ろす。登場人物はそれぞれ心に癒しがたい傷を抱え、苦く痛々しい人間模様がただ綿々と描かれる。
チャーリーは妻と娘を深く傷つけた業を背負いながら、娘を一途に想い続けている。娘はそんな父を嫌悪し強い言葉をぶつけつつ、心の底では大好きだった父の面影を求め続けている。それ自体はよくありそうなフィクションの題材であるが、宣教に訪れたキリスト教系新興宗教団体の青年が二人の関係に図らずも絡んでくる。怪しげな終末論を語りチャーリーの魂を救おうと願う青年だが、やがて黒歴史の過去から逃げ出して来た彼の過去が暴かれる。しかし物語終盤で彼自身が己の罪から解放されたと知るや、ありきたりな道徳観を振りかざしチャーリーを断罪するに至る。
チャーリーはオンラインで大学の文学講座を教えている。エッセイのイロハを語りながら、決まりきったセオリーによって学生の自己表現を漂白している偽善に自ら耐えられなくなる。チャーリーはそこに、宣教師の青年のように通り一遍の価値観で生身の人間を全否定するに等しい冷酷さを感じたのである。報われない愛情と許されない罪の意識に引き裂かれ既に限界の状態にあったチャーリーは、パソコンのスクリーン上に並ぶ学生たちの前でついに感情を爆発させる。
この映画は、最近日本で話題になった二つの出来事を少し思い起こす。一つは宗教二世が直面する虐待問題、もう一つは芸能人の不倫をネタに楽しそうに盛り上がる世間である。家族や社会が軽々しく投げつける批判や同情では決して裁けないはずの当事者の深い煩悶を、底辺でもがく彼らの葛藤に寄り添って描いた物語が『ザ・ホエール』だ。たぶん、気分が沈みがちな時には見ないほうがいい映画である。
フェイブルマンズ [映画・漫画]
歳を取るにつれ映画をわざわざ見に行くのが億劫になり、海外出張に行く機内のつれづれにふと思い立って見ることが多くなった。4月いっぱいベルギーの大学に滞在する機会があり、往路の機内で見たのが前回のコラムで触れた『Living』である。今回は、復路のお供に選んだ『フェイブルマンズ』の話をしたい。
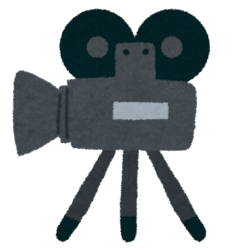 スピルバーグ監督の最新作『フェイブルマンズ』は、監督本人の生い立ちをベースにした半自伝的映画である。それだけの予備知識から、一人の映画少年がハリウッドで脚光を浴びるに至るサクセスストーリーかと思っていたら、全くそうではなかった。もちろん、映画作りに魅せられた少年が主人公であることに変わりはない。だが、物語が描き出す核心は彼の成功ではない。
スピルバーグ監督の最新作『フェイブルマンズ』は、監督本人の生い立ちをベースにした半自伝的映画である。それだけの予備知識から、一人の映画少年がハリウッドで脚光を浴びるに至るサクセスストーリーかと思っていたら、全くそうではなかった。もちろん、映画作りに魅せられた少年が主人公であることに変わりはない。だが、物語が描き出す核心は彼の成功ではない。
少年サミー・フェイブルマンの父は、有能なエンジニアである。優しく家族思いな反面、理系オタクの魂が見え隠れし時に独走する。コンサートピアニストを道半ばで諦めたサミーの母は、芸術家らしい奔放な明るさと繊細な脆さを併せ持つ、父と対照的な女性だ。父の8mmカメラでフィクションを撮る面白さに目覚めたサミー少年は、初めは妹たちを相手に、のちに友人たちを巻き込み、フィルムに虚構のリアリティを記録する趣味に没頭する。
現実指向の父は、絵空事を映像化するサミーの才能を認めつつ、そこに趣味以上の価値を認めようとしない。だがサミーの映画作りは、思いもよらぬ形でサミーとフェイブルマン一家の運命を変えていく。家族キャンプの実録をカメラに収めたサミーは、編集作業中にフィルムに映り込んだ母の予期せぬ一面を発見する。彼だけが気付いた家庭の小さなほころびは、幸福を絵に描いたような6人家族の平穏が静かに崩壊していく前兆だった。
サミーは高校で学生イベントの撮影を担当するが、その完成披露を見たある学生がサミーに詰め寄る。スポーツ万能でスクールカーストの頂点に君臨する彼は、映像が賛美する自身のヒーロー像に予想外の反応を示した。他人には決して見せなかった彼の内なる苦しさを、サミーは知らないうちにフィルムに焼き付けていたのだ。映画は単に絵空事を綴るメディアではなく、目に見える真実と隠れた真実の多層性をまるごと語る力がある。それを自覚したせいか否かはさておき、両親に反発していた思春期のサミーはやがて、父と母それぞれが一人の人間として抱える心の葛藤を素直に受け止めるようになる。
映画の幕切れ、サミーはジョン・フォード監督とつかのま面会の機会を得る。伝説の名監督は、オフィスの壁にかかる絵画を指してサミーにこんな話をする。
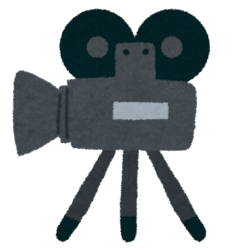 スピルバーグ監督の最新作『フェイブルマンズ』は、監督本人の生い立ちをベースにした半自伝的映画である。それだけの予備知識から、一人の映画少年がハリウッドで脚光を浴びるに至るサクセスストーリーかと思っていたら、全くそうではなかった。もちろん、映画作りに魅せられた少年が主人公であることに変わりはない。だが、物語が描き出す核心は彼の成功ではない。
スピルバーグ監督の最新作『フェイブルマンズ』は、監督本人の生い立ちをベースにした半自伝的映画である。それだけの予備知識から、一人の映画少年がハリウッドで脚光を浴びるに至るサクセスストーリーかと思っていたら、全くそうではなかった。もちろん、映画作りに魅せられた少年が主人公であることに変わりはない。だが、物語が描き出す核心は彼の成功ではない。少年サミー・フェイブルマンの父は、有能なエンジニアである。優しく家族思いな反面、理系オタクの魂が見え隠れし時に独走する。コンサートピアニストを道半ばで諦めたサミーの母は、芸術家らしい奔放な明るさと繊細な脆さを併せ持つ、父と対照的な女性だ。父の8mmカメラでフィクションを撮る面白さに目覚めたサミー少年は、初めは妹たちを相手に、のちに友人たちを巻き込み、フィルムに虚構のリアリティを記録する趣味に没頭する。
現実指向の父は、絵空事を映像化するサミーの才能を認めつつ、そこに趣味以上の価値を認めようとしない。だがサミーの映画作りは、思いもよらぬ形でサミーとフェイブルマン一家の運命を変えていく。家族キャンプの実録をカメラに収めたサミーは、編集作業中にフィルムに映り込んだ母の予期せぬ一面を発見する。彼だけが気付いた家庭の小さなほころびは、幸福を絵に描いたような6人家族の平穏が静かに崩壊していく前兆だった。
サミーは高校で学生イベントの撮影を担当するが、その完成披露を見たある学生がサミーに詰め寄る。スポーツ万能でスクールカーストの頂点に君臨する彼は、映像が賛美する自身のヒーロー像に予想外の反応を示した。他人には決して見せなかった彼の内なる苦しさを、サミーは知らないうちにフィルムに焼き付けていたのだ。映画は単に絵空事を綴るメディアではなく、目に見える真実と隠れた真実の多層性をまるごと語る力がある。それを自覚したせいか否かはさておき、両親に反発していた思春期のサミーはやがて、父と母それぞれが一人の人間として抱える心の葛藤を素直に受け止めるようになる。
映画の幕切れ、サミーはジョン・フォード監督とつかのま面会の機会を得る。伝説の名監督は、オフィスの壁にかかる絵画を指してサミーにこんな話をする。
これは覚えておきたまえ。地平線が下にあれば、面白い。上にあっても、面白い。地平線が真ん中だと、まったくもってつまらん。フォード監督本人は、構図の基本をレクチャーしただけかもしれない。だがその含意はたぶんもう少し深い。初めから直線で二等分された調和は、何も生み出さない。調和が乱れているからこそ、人生に陰影と魅力が生まれる。それは若きサミーにとって感動的な啓示であり、同時に救済でもあった。
生きる [映画・漫画]
黒澤明監督の『生きる』を基にした英国映画『Living』が公開されている。オリジナルが世界的に知られる不朽の古典的名作だけに、リメイクはハードルが高い。個人的には、カズオ・イシグロが脚本を書いたことにとても関心を引かれた。
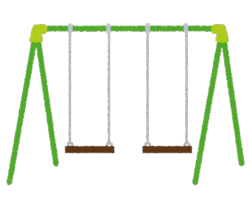 物語の骨格は、オリジナルをかなり忠実になぞっている。車のフロントガラス越しに見える雨の日の記憶とか、雪の夜にひとりブランコを漕ぐ有名なラストシーンとか、黒澤版へのオマージュに事欠かない。それでいて、映画が醸成する全体的な印象はかなり違う。1950年代の日本と同時代のイギリスを隔てる文化的背景や人物像の違いも大きいと思うが、理由はそれだけではないような気もする。
物語の骨格は、オリジナルをかなり忠実になぞっている。車のフロントガラス越しに見える雨の日の記憶とか、雪の夜にひとりブランコを漕ぐ有名なラストシーンとか、黒澤版へのオマージュに事欠かない。それでいて、映画が醸成する全体的な印象はかなり違う。1950年代の日本と同時代のイギリスを隔てる文化的背景や人物像の違いも大きいと思うが、理由はそれだけではないような気もする。
黒澤映画の前半は不治の病を知り混乱した渡辺の苦悩を描き、後半は渡辺の死後その変貌ぶりを同僚らが回想する。オリジナルより40分短いイシグロの脚本は、どちらかというとその前半部に焦点を当てている。結果として、人が変わったように小さな公園の建設に尽力するウィリアムより、そこに至るまでの彼の煩悶が映画全体の雰囲気を支配する。
ウィリアムは妻を亡くした孤独の中で生き、同居する息子夫婦との関係もぎこちない。お互い伝えたいことを切り出せず、他愛のない会話に逃げ込むシーンのリアリティはイシグロの真骨頂である。ウィリアムにとどまらず、『Living』の登場人物は皆すこし寂し気だ。自暴自棄のウィリアムを場末のパブやストリップ小屋へ案内する作家の男も、死の直前に公園のブランコに座るウィリアムを目撃した警官も、どこか悲しい目をしている。ウィリアムが「生き返る」きっかけを与える快活な部下の女性ハリスすら、転職先で彼女自身の悩みを抱えている。
役所の形式主義に染まり無為の日々を送っていた主人公が、死期を悟り逡巡の末に人生の意味に目覚める。根底にあるテーマは共通だが、単調な仕事一徹に身を削り続けたが故の惨めさがにじみ出る渡辺に比べ、ウィリアムは透明で消え入りそうな寂寥の中を生きている。だがウィリアムが息子にすら明かせなかった余命をハリスに打ち明け、自らを静かに蝕んできた孤独を彼女と分かちあったとき、ついに自身の進むべき道を見出す。
オリジナル版の『生きる』で渡辺を変えるきっかけを与えた小田切は、ハリスほど元上司に深い共感を示さなかった。渡辺にとって救済は主に社会的役割の回復にあったが、ウィリアムを変えたのはより個人的な温もりに近い何かだった。『Living』でカズオイシグロが描く人物が、程度の差こそあれみな同じような哀しみを秘めているのは、潜在的には誰もがウィリアムと同じ苦悩を心の奥底に抱えているからである。
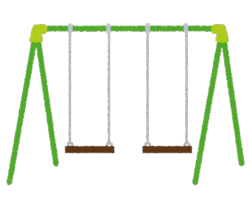 物語の骨格は、オリジナルをかなり忠実になぞっている。車のフロントガラス越しに見える雨の日の記憶とか、雪の夜にひとりブランコを漕ぐ有名なラストシーンとか、黒澤版へのオマージュに事欠かない。それでいて、映画が醸成する全体的な印象はかなり違う。1950年代の日本と同時代のイギリスを隔てる文化的背景や人物像の違いも大きいと思うが、理由はそれだけではないような気もする。
物語の骨格は、オリジナルをかなり忠実になぞっている。車のフロントガラス越しに見える雨の日の記憶とか、雪の夜にひとりブランコを漕ぐ有名なラストシーンとか、黒澤版へのオマージュに事欠かない。それでいて、映画が醸成する全体的な印象はかなり違う。1950年代の日本と同時代のイギリスを隔てる文化的背景や人物像の違いも大きいと思うが、理由はそれだけではないような気もする。黒澤映画の前半は不治の病を知り混乱した渡辺の苦悩を描き、後半は渡辺の死後その変貌ぶりを同僚らが回想する。オリジナルより40分短いイシグロの脚本は、どちらかというとその前半部に焦点を当てている。結果として、人が変わったように小さな公園の建設に尽力するウィリアムより、そこに至るまでの彼の煩悶が映画全体の雰囲気を支配する。
ウィリアムは妻を亡くした孤独の中で生き、同居する息子夫婦との関係もぎこちない。お互い伝えたいことを切り出せず、他愛のない会話に逃げ込むシーンのリアリティはイシグロの真骨頂である。ウィリアムにとどまらず、『Living』の登場人物は皆すこし寂し気だ。自暴自棄のウィリアムを場末のパブやストリップ小屋へ案内する作家の男も、死の直前に公園のブランコに座るウィリアムを目撃した警官も、どこか悲しい目をしている。ウィリアムが「生き返る」きっかけを与える快活な部下の女性ハリスすら、転職先で彼女自身の悩みを抱えている。
役所の形式主義に染まり無為の日々を送っていた主人公が、死期を悟り逡巡の末に人生の意味に目覚める。根底にあるテーマは共通だが、単調な仕事一徹に身を削り続けたが故の惨めさがにじみ出る渡辺に比べ、ウィリアムは透明で消え入りそうな寂寥の中を生きている。だがウィリアムが息子にすら明かせなかった余命をハリスに打ち明け、自らを静かに蝕んできた孤独を彼女と分かちあったとき、ついに自身の進むべき道を見出す。
オリジナル版の『生きる』で渡辺を変えるきっかけを与えた小田切は、ハリスほど元上司に深い共感を示さなかった。渡辺にとって救済は主に社会的役割の回復にあったが、ウィリアムを変えたのはより個人的な温もりに近い何かだった。『Living』でカズオイシグロが描く人物が、程度の差こそあれみな同じような哀しみを秘めているのは、潜在的には誰もがウィリアムと同じ苦悩を心の奥底に抱えているからである。
ヘンリー王子の羅生門 [映画・漫画]
1995年公開の『ユージュアル・サスペクツ』という映画がある。裏社会の抗争がらみとみられる船舶爆破事件が起こった。唯一の生存者である詐欺師の男と彼を尋問する刑事のやり取りが、事件の背景を少しずつ紐解いていく。やがてカイザー・ソゼと呼ばれる冷酷無比な黒幕の存在が浮かび上がるが、そのミステリアスな正体をめぐり登場人物の見解はまちまちで、謎はむしろいっそう深まる。
しかし映画の幕切れに至り、まさかのどんでん返しが待ち構えている。主人公によるウソの証言というミステリーの禁じ手が使われているので、オチがフェアではないという論議はあったように記憶している。が、綿密に張り巡らされた伏線が一気に回収されるラストは圧巻で、大半の人は気持ちよく騙された。
 『ユージュアル・サスペクツ』の隠れたテーマは、真実の重層性である。この映画が出世作となったブライアン・シンガー監督は、黒澤明監督の『羅生門』から受けた影響を認めている。芥川龍之介の短編『藪の中』を下敷きにした映画『羅生門』は、平安時代の強盗殺人を題材に、語り手ごとに食い違う「真実」の曖昧さを描いた。
『ユージュアル・サスペクツ』の隠れたテーマは、真実の重層性である。この映画が出世作となったブライアン・シンガー監督は、黒澤明監督の『羅生門』から受けた影響を認めている。芥川龍之介の短編『藪の中』を下敷きにした映画『羅生門』は、平安時代の強盗殺人を題材に、語り手ごとに食い違う「真実」の曖昧さを描いた。
面白いことに、事件の当事者三人はいずれも被害者の武士を殺したのは自分だと語る。殺人の罪を逃れることよりも、無意識に己の役回りを見栄えよく粉飾するナルシシズム的美学が勝っているのである。映画には事件をこっそり目撃していた四番目の人物(芥川の原作には登場しない)が存在し、彼の証言により当事者の虚飾がつまびらかに暴かれる。が、この人物もまた自らに不都合な事実を隠そうとしていた。
英国王室を去った(追い出された)ヘンリー王子の暴露本『スペア』が発売され、話題を呼んでいる。書かれていることがウソかホントかと報道を賑わせているが、真相は何かという議論にあまり意味はない。ヘンリー王子にとっては紛れもない「真実」も、他の当事者にとっては継ぎはぎだらけの言い訳に過ぎないかもしれない。読んだわけではないが、『スペア』はたぶんヘンリー王子が脚色したロイヤルファミリー版『羅生門』なのである。
しかし映画の幕切れに至り、まさかのどんでん返しが待ち構えている。主人公によるウソの証言というミステリーの禁じ手が使われているので、オチがフェアではないという論議はあったように記憶している。が、綿密に張り巡らされた伏線が一気に回収されるラストは圧巻で、大半の人は気持ちよく騙された。
 『ユージュアル・サスペクツ』の隠れたテーマは、真実の重層性である。この映画が出世作となったブライアン・シンガー監督は、黒澤明監督の『羅生門』から受けた影響を認めている。芥川龍之介の短編『藪の中』を下敷きにした映画『羅生門』は、平安時代の強盗殺人を題材に、語り手ごとに食い違う「真実」の曖昧さを描いた。
『ユージュアル・サスペクツ』の隠れたテーマは、真実の重層性である。この映画が出世作となったブライアン・シンガー監督は、黒澤明監督の『羅生門』から受けた影響を認めている。芥川龍之介の短編『藪の中』を下敷きにした映画『羅生門』は、平安時代の強盗殺人を題材に、語り手ごとに食い違う「真実」の曖昧さを描いた。面白いことに、事件の当事者三人はいずれも被害者の武士を殺したのは自分だと語る。殺人の罪を逃れることよりも、無意識に己の役回りを見栄えよく粉飾するナルシシズム的美学が勝っているのである。映画には事件をこっそり目撃していた四番目の人物(芥川の原作には登場しない)が存在し、彼の証言により当事者の虚飾がつまびらかに暴かれる。が、この人物もまた自らに不都合な事実を隠そうとしていた。
英国王室を去った(追い出された)ヘンリー王子の暴露本『スペア』が発売され、話題を呼んでいる。書かれていることがウソかホントかと報道を賑わせているが、真相は何かという議論にあまり意味はない。ヘンリー王子にとっては紛れもない「真実」も、他の当事者にとっては継ぎはぎだらけの言い訳に過ぎないかもしれない。読んだわけではないが、『スペア』はたぶんヘンリー王子が脚色したロイヤルファミリー版『羅生門』なのである。
8月のラピュタ [映画・漫画]
 先週の金曜ロードショーで『天空の城ラピュタ』を放映していたそうだ。見損ねたが、原爆記念日と終戦記念日のはざまの『ラピュタ』は、今年は少し考えさせられるものがある。
先週の金曜ロードショーで『天空の城ラピュタ』を放映していたそうだ。見損ねたが、原爆記念日と終戦記念日のはざまの『ラピュタ』は、今年は少し考えさせられるものがある。宮崎駿作品で『ラピュタ』が一番好きと言う人は少なくないようである。初期の宮崎作品は『未来少年コナン』や『カリオストロの城』のようなバリバリの冒険活劇だったが、やがて『トトロ』や『宅急便』など子供目線で周囲の世界を丁寧に描く作品群を経て、『もののけ姫』『千と千尋』『ハウル』のような深遠で混沌とした幻想絵巻へと変遷していく。『ラピュタ』はその過渡期にあって、それらすべての要素をバランスよく味わえるお得な作品と言える。海賊ドーラというお茶目なヒールと、ドーラの気弱な息子たちの存在も人気の一因に違いない。
その意味で『ラピュタ』が極上のエンタメ作品であることは衆目の一致するところであるが、ラピュタが世界を破滅させ得る軍事要塞であることが明るみになった終盤、物語はシリアスな結末を迎える。ラピュタの兵器を目覚めさせたムスカは「ラピュタは滅びぬ・・・ラピュタの力こそ人類の夢だからだ」と言い放つ。しかし、シータにとって先祖のルーツであり、パズーにとっては憧れの目標だったはずのラピュタを、二人は捨て身で破壊する決断をする。
今年の8月6日、広島の原爆慰霊式で挨拶した湯崎広島県知事の言葉が深い洞察に満ちている。こんな一節がある。
ウクライナ侵略で世界が突然変わった訳ではありません。世界の長い歴史の中で,理不尽で大量の死を招く暴力は,悪により,しかし,時に正義の衣をかぶりながら,連綿と繰り返されてきました。現在の民主国家と言われる国でさえ完全に無縁とは言いにくいかもしれません。持てる力を放棄するには、勇気がいる。騙されて自分だけ丸腰にされるのではという疑心暗鬼から、力を手放すことができない。だから銃規制反対論者や核抑止論者は、力を持ち続ける理由を「みんなそうだから」と正当化する。だが抑止論が保証する平和は、不安定で際どい均衡の上でしか成立しない。手元に置いた武器はつねにその持ち主を誘惑するからだ。つまりムスカの言う「人類の夢」だ。
人間の合理性には限界があるという保守的な見方をすれば,この歴史の事実を直視し,これからもこの人間の性(さが)から逃れられないことを前提としなければなりません。
しかしながら,力には力で対抗するしかない,という現実主義者は,なぜか核兵器について,肝心なところは,指導者は合理的な判断のもと「使わないだろう」というフィクションたる抑止論に依拠しています。本当は,核兵器が存在する限り,人類を滅亡させる力を使ってしまう指導者が出てきかねないという現実を直視すべきです。
『ラピュタ』が放映される日は「バルス祭り」なるイベントが恒例行事になったようである。物語の山場でシータとパズーが唱える滅びの呪文「バルス」を、視聴者がツイッターで唱和するらしい。物語ではムスカの野望は阻止され、世界は救われた。しかし現実世界には、まだ無数のラピュタが徘徊している。
アナキンとパドメ、ニューヨークへ行く [映画・漫画]
 小室夫妻がニューヨークに到着した。圭さんは、Tシャツにプリントされたダースベイダーがセーターの陰から顔をのぞかせる独特のコーデで話題をさらった。一方、眞子さんのあまりにサラサラな長髪が全国の女子から羨望の眼差しを浴びているそうである。
小室夫妻がニューヨークに到着した。圭さんは、Tシャツにプリントされたダースベイダーがセーターの陰から顔をのぞかせる独特のコーデで話題をさらった。一方、眞子さんのあまりにサラサラな長髪が全国の女子から羨望の眼差しを浴びているそうである。もし圭さんがダースベイダーだとすれば、眞子さんはベイダーが(アナキン・スカイウォーカーだったころに)結婚したパドメ・アミダラとういことになる。パドメはもともと惑星ナブーの女王であった。ナブーの君主は公選制で、任期も限定されている。優れた君主であったパドメは任期満了のとき人民から慰留され、再選のために憲法改正の提案まで受けるが、それを断って王室を去っている(このサイトに詳しい)。女性宮家をめぐる制度改正の議論が進展しないなか皇室イチ抜けを果たした眞子さんと、微妙にシンクロする話である。
有り体に言えばアナキンとパドメは身分違いの恋だったので、婚姻は秘密裏に進められ、式に参列したのはC-3POとR2-D2だけだった。世間の風向きを読み皇室伝統のセレモニーを行わず地味に入籍した小室夫妻と、ちょっと似ている。アナキンは結婚後いろいろあってダークサイドの誘惑に負け、ダースベイダーと化した。圭さんが自分をベイダーになぞらえてスターウォーズTシャツを着ていたのか定かではないが、もしかして自らの将来にさらなる波乱を予期しているのか?
アナキンをダークサイドに引き込んだ陰の立役者は、銀河皇帝パルパティーンであった。圭さんの身近なところで皇帝役をスカウトするなら、おそらく「元婚約者」あたりか。一連の問題を白日に晒す原因を作った張本人だし、関係者の中で唯一実名が明かされない黒幕感とか、役に不足はなかろう。渡米直前に解決金で折り合いがついたそうで、意のままに帝国を支配した挙げ句最後はベイダーの返り討ちにあった銀河皇帝よりは、和やかな結末に落ち着いたようである(たぶん)。
ちなみにパドメは、ダークサイドに堕ちていくアナキンに心を痛めつつ、若くして命を落とした。異国暮らしの中、眞子さんは健康に留意して欲しい。
ズートピア:差別と偏見について [映画・漫画]
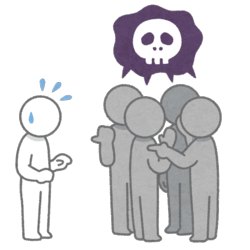 コロナ禍の不満や不安が、世界でアジア系への偏見や差別を生んでいるという。通りすがりの人から何となく避けられるといった話はあちこちで聞くし、罵声を浴びせられたり中には傷害事件に巻き込まれる深刻な事例もある。確かにウイルスの出処は中国だったが、その後ほどなくしてイタリア北部で感染が急拡大し、あっという間にヨーロッパそして全世界に広がった。武漢の収束以降、感染者数の推移を見る限り東アジア諸国は(もちろん日本を含め)一貫してコロナ対応の優等生だ。トランプ元大統領はChinese Virusと連呼していたが、実際のところ過去一年せっせと感染を広げてきた震源地はどこなのか?だが、今日書きたいのはそういうことではない。
コロナ禍の不満や不安が、世界でアジア系への偏見や差別を生んでいるという。通りすがりの人から何となく避けられるといった話はあちこちで聞くし、罵声を浴びせられたり中には傷害事件に巻き込まれる深刻な事例もある。確かにウイルスの出処は中国だったが、その後ほどなくしてイタリア北部で感染が急拡大し、あっという間にヨーロッパそして全世界に広がった。武漢の収束以降、感染者数の推移を見る限り東アジア諸国は(もちろん日本を含め)一貫してコロナ対応の優等生だ。トランプ元大統領はChinese Virusと連呼していたが、実際のところ過去一年せっせと感染を広げてきた震源地はどこなのか?だが、今日書きたいのはそういうことではない。『ズートピア』というディズニーのアニメ映画がある。一行で要約すれば、天真爛漫なウサギと皮肉屋のキツネが反目しながらも友情の絆を深めていく物語、ということになる。しかし『ズートピア』の本質は差別と偏見を描いた寓話で、その点においてかなりリアルで重い話だ。差別とは特定のグループに向けられた社会の圧力のことで、偏見とは個々人が心の底に抱える心理的バイアスを言う。偏見が差別の構造を生み、差別はいったん広まると偏見を正当化する。偏見と差別はそうやって相互に強化していくので、社会から完全に駆除することは難しい。
ズートピアなる世界は、草食動物と肉食動物が仲良く共存する理想郷である。しかし、草食動物は無意識下で肉食動物への本能的な恐れを抱えている。そしてある事件をきっかけに、両者を隔てる心の壁が顕在化する。『ズートピア』の作者は、弱肉強食の食物連鎖ピラミッドをひっくり返し、マジョリティである草食動物を社会的強者に据える。電車の座席で偶然隣に座ったトラから距離を取るように、そっと娘を引き寄せるウサギの母親。かすかに悲しげな表情を隠せないトラの男性。束の間のシーンだが、目に見えない偏見が目に見える差別として社会に固定されていく瞬間を、鋭く切り取っている。映画が公開された2016年の2月はパリ同時多発テロの直後だったので、イスラムの人々へ向ける眼差しが厳しくなった現実と『ズートピア』の世界が、時にギョッとするほどよく似ていた。
米国コロラド州に住んでいたある日、勤め先の大学が開いた交流イベントでトルコ人留学生のスピーチを聞いた。当時は2001年の9・11テロからまだ間もない頃で、彼は在学中にテロの速報を目の当たりにした。イスラム教徒の学生が集う学内施設に駆けつけると、そこは重苦しい空気に沈んでいる。屋外に気配を感じて外を見ると、見慣れない学生の一群が取り囲んでいるではないか。スピーチで彼は「なんてこった、俺の人生は終わりだ」と思ったと冗談めかして語ったが、実際その瞬間は本気でそう感じていたのかも知れない。しかし外で待っていた学生たちは、「あなた達は私たちの変わらぬ友人です、それを伝えに来ました」と手に抱えた花束を差し出してきたという。
偏見が消しがたい心の闇だとしても、闇を自覚することでそこに光を取り戻すこともできる。アジア系への差別はコロナ前からあったし、コロナ後もなくなりはしないだろうが、手を差し伸べる人は社会のどこかに必ずいる。傷ついたり救われたりを繰り返しながら、社会全体はたぶん、少しずつでもより住みやすい世界に変わろうとしているのだと思いたい。



