小泉進次郎の話術と英語力 [語学]
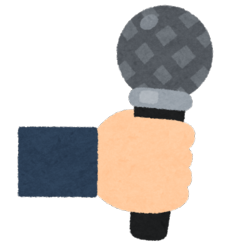 日本の政治家はスピーチが苦手な人が多い。話している時間の半分以上が「あー」とか「えー」で埋まる演説を耳にすると、だれか喋り方を教えてあげる人は周りにいなかったのかと少し気の毒になる。言葉を探してつい出てしまう「えーっと」の類は言語学でフィラー(Filler)と呼ばれ、スピーチでは極力避けるべきとその筋の指南書に必ず書いてある。安倍首相は歴代総理の中では弁舌が滑らかな方と思うが、「・・・と、このように思うわけであります」といった無駄な言い回しが多い。フィラー同様、情報量の薄い文言がスピーチの合間をつなぐと聞き手の集中力が削がれ、肝心な話の要点が記憶に残らない。
日本の政治家はスピーチが苦手な人が多い。話している時間の半分以上が「あー」とか「えー」で埋まる演説を耳にすると、だれか喋り方を教えてあげる人は周りにいなかったのかと少し気の毒になる。言葉を探してつい出てしまう「えーっと」の類は言語学でフィラー(Filler)と呼ばれ、スピーチでは極力避けるべきとその筋の指南書に必ず書いてある。安倍首相は歴代総理の中では弁舌が滑らかな方と思うが、「・・・と、このように思うわけであります」といった無駄な言い回しが多い。フィラー同様、情報量の薄い文言がスピーチの合間をつなぐと聞き手の集中力が削がれ、肝心な話の要点が記憶に残らない。その一方ピカいち演説力が光っていたのが小泉純一郎元首相だ。この人の言葉は短くて力強い。そしてフィラーにほとんど頼らない。「あー」や「えー」に代わり、ここぞという時この人はフッと沈黙する。すると、何を言い出すんだ?という期待が高まり、場の緊張感がぐっと凝縮する。そして「感動した!」と一言吐き出されるのを聞いて、ああそうか感動したのか、と大したことでなくても妙に納得してしまう。言うまでもないが、スピーチが上手いことと話の深度は全く関係ない。「私の内閣の方針に反対する勢力、これはすべて抵抗勢力だ」とかやんちゃな発言にも事欠かなかったが、言葉のインパクトを巧みにに利用する勘の良さでは最近の首相の中でダントツであろう(かつては吉田茂とか田中角栄とか味のある名言を残した曲者がいたが)。
最近なにかと注目を浴びる小泉進次郎環境相が、父の話術を忠実に受け継いで見事である。この人も沈黙の使い方が上手く、簡潔な言葉を淀みなく吐き出しカッコいい。あとから字面をなぞると結局何を言いたいのかよくわからない発言も多く、「もっともらしくて無意味」な進次郎風ネタを投稿する大喜利がネットで盛り上がっているらしい。とはいえ公人はネタにされてナンボ、耳目を集める吸引力に優れていることに変わりなく、発言内容はさておき話術ではどの政治家もこのくらいの水準を目指して欲しい。
先の国連気候行動サミットでも、小泉環境相の発言が注目された。地球環境問題が醸し出す堅苦しさを嘆いて"It’s gotta be fun, it’s gotta be cool, it’s gotta be sexy too."と言い放ったあれである。これは進次郎節が英語でも遺憾なく発揮されるという感動的な発見であった。とはいえ国を代表して発言する以上gotta-be的なタメぐち英語よりもう少し正調な言葉遣いを聞きたかった、と言うと少し要求が過ぎるか。語学の格調に関しては、同じサミット中にトランプ大統領の背中を口をへの字にして睨み付けたスウェーデンの少女がなかなかの貫禄で、感極まりつつ率直な思いをシンプルながら美しい英語で吐露した彼女は近寄りがたい凄みにあふれていた("How dare you"とか芝居じみた啖呵はともかく)。
オランダやスウェーデンは、ネイティブ並に英語を操る人がやたらと多いことで知られている。彼らの母国語がそもそも英語に近いせいでもあるが、同じゲルマン語派のドイツ語話者はインテリでも英語が流暢な人ばかりではない。ラテン系言語圏のフランスやイタリアではなおそうだ。オランダはテレビをつければBBCなど英語の番組が吹き替え抜きで流れているので、幼い頃から当たり前のように英語が耳に入ってくる。意地悪く言えばオランダ語だけであらゆる番組を制作する経済性が見込めないわけで、自国言語のマーケットが小さい国はその隙間を埋めるように英語が自然と生活のなかに染み込んでいるのだ。逆に、文化的影響力の強い言語を持つドイツやフランスは、観光地を除けば普段の暮らしの中で生の英語が聞こえてくる余地は少ない。その点で日本も事情は同じである。スウェーデン語が本国とその周辺でしか通用しないように日本語もマーケットの限られた言語かと思いきや、日本語を母国語とする人口はドイツ語やフランス語のそれより多く、その市場規模は侮りがたい。日本国内で暮らす限り、外国語を知らないとアクセスできないコンテンツにはほとんどお目にかからない。
日本語の地産地消で高度な文化圏が成立しているのは誇らしいことであるが、その結果私たちがふだん英語に触れる機会は学校の中だけになった。中学以降(今では小学校から)綿々と授業で絞られるのに、英語に苦手意識を持つ日本人は多い(TOEFLの国別ランキングで日本はアジア内最下位クラス常連である)。以前別のところでも書いたが、「テストで減点されない英語」を指向した教育に疲れ果てた私たちは、自発的なコミュニケーションのための英語を会得する意欲を失ってしまったのである。その意味では、タメぐちでも気軽に初対面の外国人と話せる進次郎英語(と社交性)は、むしろ日本人が目指すべき姿を体現しているのかもしれない。他愛もない軽口を交わすだけで「こいつ意外にいいヤツだな」と打ち解けることもあるし、それだけで世界への眼差しが少し優しくなったりするものである。
彼岸にあたって [その他]
 秋の彼岸、旅先から母の墓参に足を伸ばしてきた。お彼岸は仏教伝来よりも古い日本古来の慣習らしいが、折に触れて故人を偲ぶのは時代や洋の東西を問わない。ひところ『千の風になって』という歌が流行って、私の墓の前で泣かないでください、風になったりいろいろ忙しいのでいま不在です、今度はアポ取ってから来てね、というような歌詞だった気がするが、もともとは米国で伝えられてきた詞だそうで、世を去った近しい人を想いつづける苦しさもまた古今東西変わらない。
秋の彼岸、旅先から母の墓参に足を伸ばしてきた。お彼岸は仏教伝来よりも古い日本古来の慣習らしいが、折に触れて故人を偲ぶのは時代や洋の東西を問わない。ひところ『千の風になって』という歌が流行って、私の墓の前で泣かないでください、風になったりいろいろ忙しいのでいま不在です、今度はアポ取ってから来てね、というような歌詞だった気がするが、もともとは米国で伝えられてきた詞だそうで、世を去った近しい人を想いつづける苦しさもまた古今東西変わらない。私たち自身誰しもやがて死を迎えるが、最期の時を迎える過程で生と死を分かつ境目は厳密にはどこにあるのだろうか?脳死の問題一つとっても人の死を人が判断する困難の根は深いが、私が考えているのは少し別のことだ。ニュースなどで耳にする「心肺停止」という言葉があり、たしかに心臓と肺の機能が失われれば生命維持は物理的に不可能だが、死に至る病は必ずしも心肺機能が真っ先に損なわれるわけではない。例えば膵臓がんは5年生存率が10%に満たない難しい病気で、膵機能が低下すれば徐々に体力が衰えていくのは必然とは言え、衰弱という連続的なプロセスが生死という不連続な垣根を超えるとき、体内で何が起こっているのだろうか。心臓や肺が「膵臓さん、もう持たなそうだな、うちらもぼちぼち仕事納めか」とシャットダウンのスイッチが入るのか?そんなことが医学的にあり得るだろうか?
母の最期が膵臓がんであった。背中の痛みを訴えて医者に行き診断が下ったとき、すでに余命数ヶ月の状態だった(末期まで自覚症状のないことがこの病気の予後が悪い原因のひとつである)。東京で一人暮らしをしていた母はもともと独立心が強く、入院の勧めを拒否し訪問介護を受けながら在宅で闘病する道を選んだ。ところが私が見舞いに訪れたある日、緩和ケア病棟に入りたいと突然言い出した。不意の心変わりにケアマネさんともども戸惑いつつ、母の意思が固いので急遽近くの病院に入院の手配をした。緩和ケア病棟のあるフロアは眺望が良く開放感があり、最期のひと時を過ごすのに悪くない場所だと思った。
結局、母がその部屋に滞在した時間はわずかだった。入院翌日に姉が病院を訪れ母と話をしたその晩遅く、母は病室のベッドで息を引き取った。一旦名古屋に戻っていた私は早朝の電話で訃報を受け、朝イチの新幹線で東京に引き返した。その車内で私の頭に引っかかっていたのは、入院手続き時に緩和ケアの担当医師が話してくれた一言だった。何気なく余命の質問をしたとき、先生は医者としての見立てに限界を認めつつ「患者さんご自身の方が身体からのメッセージを正確に受け取っていることもあるんですよね」と呟いたのである。母があのとき突然入院を言い出したのは、死期を察した母の最期の身支度だったのか?
他界直前にあたかも死を悟っていたかのような言動をした人の話は少なくない。緩和ケアで多くの癌患者を見送ってきた医師が言った通り、迫り来る最期のときを無意識に感じ取ることはあるのかもしれない。でもそれは単に、身体が決めた死期を言われるがままに受け入れる受動的な感覚に過ぎないのだろうか?母は、離れて住む私と姉と立て続けに言葉を交わしてすぐ旅立った。もうそろそろこれで充分だ、ということだったように思えなくもない。不治の病の一番終わりの段階に至って、人はシャットダウンのタイミングを限定的ながら自分で選ぶ自由度が与えられることがあるのではないか。それは身体が特殊な状態にあるときのみ許される一時的な能力、死の恐怖に対峙するストレスを少しでも緩和する生物学的な防御反応なのではないか。後から聞いた話では、巡回の看護師が発見した最期の母は、神に祈るように胸元で両手を組んでいたという。まるで、来るべき死を進んで待ち受けていたかのように。
人は本当に自身の死期を少しだけ操ることができるのか?私にもいつか、その仮説の真偽を確かめる一生に一度きりの機会が訪れるだろう。自分自身の経験として人生最期の瞬間に秘められた秘密を目の当たりにするチャンスは、恐ろしくもあり少し楽しみでもある。残念なのは、その顛末を誰かに伝える術は永遠に与えられないことだ。
不気味の谷 [その他]
飛行機の離陸前には必ず、乗務員が機内安全設備と諸注意事項を足早に説明する。小型機の場合は小道具を駆使した昔ながらの実演が粛々と行われるが、機内モニターが装備された中大型機では予め用意されたビデオが流されるのが普通だ。いつ頃からか、このビデオに異変が起き始めた。どこの航空会社が最初に始めたか定かでないが、ありきたりの脚本どおりでは誰も目もくれないことに業を煮やしたか、各社が競って随所で笑いを取る仕掛けを仕込み始めたのである(実例はYoutubeで「airlines safety video」などと検索すればぞろぞろ出てくる)。土産話のネタには良いが、気が散って肝心の内容があまり頭に入ってこなくなった気がしないでもない。生真面目な日本の業界はこの手のブームに乗らないだろうと思っていたら、最近ANAが歌舞伎をモチーフにビデオの大改装を敢行した。海外(とくに非アジア圏)からの観光客に大いにウケているかもしれない。
ハメを外しつつある世界の航空業界を尻目にまったく動じる気配がないのが、ドイツが誇る老舗大手ルフトハンザ航空である。ちょうどドイツ出張から戻ったところなのでルフトハンザの安全解説ビデオを見る機会があったが、エンタメ要素を一切排したオーソドックスな作りで潔い。実写の代わりに登場人物を含め全編CGなのだが、人物の絵を精巧に作り込みすぎてすこしばかり薄気味悪いのが難だ。機内で並んで座る仲睦まじい父娘のはずが、サイコサスペンス映画の一コマのように見えてくる。
 ゆるキャラ的なロボットなら可愛いのにリアルに人型に寄せすぎたアンドロイドには不快感を感じる、という逆説的な心理作用は俗に「不気味の谷」として知られている。不気味の谷の深層がどの程度心理学的に解明されているか寡聞にして知らないが、よく似ているのに何かが違う相手に対する複雑な感情は、太古の昔から人類の脳裏奥深くに埋め込まれた本能の一部ではないか。おなじ人類なのに「仲間」と「敵」を区別することによって共同体の結束を育んできた私たちは、内と外の人間をかぎ分ける嗅覚が鋭敏だ。免疫システムの誤動作がアレルギーを引き起こすように、「外」を検知する嗅覚の過剰反応はときに同胞に向けられ暴走する。多様性の価値が広く認知された社会でも、ナショナリズムや人種差別やいじめが完全に絶えることはない。民族的背景や肌の色の違い、もしくは空気が読めないといったわずかな感性のズレすら、理不尽な不寛容の原因となる。
ゆるキャラ的なロボットなら可愛いのにリアルに人型に寄せすぎたアンドロイドには不快感を感じる、という逆説的な心理作用は俗に「不気味の谷」として知られている。不気味の谷の深層がどの程度心理学的に解明されているか寡聞にして知らないが、よく似ているのに何かが違う相手に対する複雑な感情は、太古の昔から人類の脳裏奥深くに埋め込まれた本能の一部ではないか。おなじ人類なのに「仲間」と「敵」を区別することによって共同体の結束を育んできた私たちは、内と外の人間をかぎ分ける嗅覚が鋭敏だ。免疫システムの誤動作がアレルギーを引き起こすように、「外」を検知する嗅覚の過剰反応はときに同胞に向けられ暴走する。多様性の価値が広く認知された社会でも、ナショナリズムや人種差別やいじめが完全に絶えることはない。民族的背景や肌の色の違い、もしくは空気が読めないといったわずかな感性のズレすら、理不尽な不寛容の原因となる。
アンドロイドが「私たちに似た別物」として疎外される悲劇は、映画や小説では昔から使い古されたテーマでもある。リドリー・スコットの『ブレード・ランナー』やスティーヴン・スピルバーグの『A.I.』がそうだし、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』に通底する重苦しさも根は同じだ。自由意思を持ったアンドロイドはフィクションの域を出ないが、人間そっくりに作られた実験的ロボットがぎこちなく喋っている様子を見ると、無害なヤツとわかっていてもどこか居心地の悪い気分がする。機内ビデオのCGキャラクターが醸し出す不気味さも、その心理的な延長線上にある。
スタジオジブリとか最近では新海誠監督の作品に代表されるように、日本アニメの風景描写は緻密で美しく実写と見まごうカットも少なくないが、人物に限っては伝統的なアニメ顔に徹し敢えてリアリティを抑制する。いろいろ技術的な事情が絡んでるのかもしれないが、不気味の谷への転落を回避する意図も間違いなくあるだろう。そのうち日本のどこかの航空会社が、機内安全ビデオをジブリに依頼する日がくるかもしれない。キキが箒を頭上に収納し、ナウシカが黙ってシートベルトを締め、カオナシが脱出シューターでアシストしている図とか、見てみたくはないか(ネタが古くて申し訳ない)。歌舞伎もよいが、アニメだって今や世界を魅了する日本文化の一部なのだから。
ハメを外しつつある世界の航空業界を尻目にまったく動じる気配がないのが、ドイツが誇る老舗大手ルフトハンザ航空である。ちょうどドイツ出張から戻ったところなのでルフトハンザの安全解説ビデオを見る機会があったが、エンタメ要素を一切排したオーソドックスな作りで潔い。実写の代わりに登場人物を含め全編CGなのだが、人物の絵を精巧に作り込みすぎてすこしばかり薄気味悪いのが難だ。機内で並んで座る仲睦まじい父娘のはずが、サイコサスペンス映画の一コマのように見えてくる。
 ゆるキャラ的なロボットなら可愛いのにリアルに人型に寄せすぎたアンドロイドには不快感を感じる、という逆説的な心理作用は俗に「不気味の谷」として知られている。不気味の谷の深層がどの程度心理学的に解明されているか寡聞にして知らないが、よく似ているのに何かが違う相手に対する複雑な感情は、太古の昔から人類の脳裏奥深くに埋め込まれた本能の一部ではないか。おなじ人類なのに「仲間」と「敵」を区別することによって共同体の結束を育んできた私たちは、内と外の人間をかぎ分ける嗅覚が鋭敏だ。免疫システムの誤動作がアレルギーを引き起こすように、「外」を検知する嗅覚の過剰反応はときに同胞に向けられ暴走する。多様性の価値が広く認知された社会でも、ナショナリズムや人種差別やいじめが完全に絶えることはない。民族的背景や肌の色の違い、もしくは空気が読めないといったわずかな感性のズレすら、理不尽な不寛容の原因となる。
ゆるキャラ的なロボットなら可愛いのにリアルに人型に寄せすぎたアンドロイドには不快感を感じる、という逆説的な心理作用は俗に「不気味の谷」として知られている。不気味の谷の深層がどの程度心理学的に解明されているか寡聞にして知らないが、よく似ているのに何かが違う相手に対する複雑な感情は、太古の昔から人類の脳裏奥深くに埋め込まれた本能の一部ではないか。おなじ人類なのに「仲間」と「敵」を区別することによって共同体の結束を育んできた私たちは、内と外の人間をかぎ分ける嗅覚が鋭敏だ。免疫システムの誤動作がアレルギーを引き起こすように、「外」を検知する嗅覚の過剰反応はときに同胞に向けられ暴走する。多様性の価値が広く認知された社会でも、ナショナリズムや人種差別やいじめが完全に絶えることはない。民族的背景や肌の色の違い、もしくは空気が読めないといったわずかな感性のズレすら、理不尽な不寛容の原因となる。アンドロイドが「私たちに似た別物」として疎外される悲劇は、映画や小説では昔から使い古されたテーマでもある。リドリー・スコットの『ブレード・ランナー』やスティーヴン・スピルバーグの『A.I.』がそうだし、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』に通底する重苦しさも根は同じだ。自由意思を持ったアンドロイドはフィクションの域を出ないが、人間そっくりに作られた実験的ロボットがぎこちなく喋っている様子を見ると、無害なヤツとわかっていてもどこか居心地の悪い気分がする。機内ビデオのCGキャラクターが醸し出す不気味さも、その心理的な延長線上にある。
スタジオジブリとか最近では新海誠監督の作品に代表されるように、日本アニメの風景描写は緻密で美しく実写と見まごうカットも少なくないが、人物に限っては伝統的なアニメ顔に徹し敢えてリアリティを抑制する。いろいろ技術的な事情が絡んでるのかもしれないが、不気味の谷への転落を回避する意図も間違いなくあるだろう。そのうち日本のどこかの航空会社が、機内安全ビデオをジブリに依頼する日がくるかもしれない。キキが箒を頭上に収納し、ナウシカが黙ってシートベルトを締め、カオナシが脱出シューターでアシストしている図とか、見てみたくはないか(ネタが古くて申し訳ない)。歌舞伎もよいが、アニメだって今や世界を魅了する日本文化の一部なのだから。
2019-09-15 23:21
nice!(0)
お値ごろホテルに見るお国柄 [海外文化]
 日本の主要都市にあまねく展開するビジネスホテルは、部屋の大きさは必要最小限でお洒落感も低いが、清潔で設備に無駄なく機能的によく考えられているので泊まるだけなら快適だ。もっとも、効率化はしばしば快適性の犠牲の上に成り立つ。ある有名大手チェーンの浴室はシンクとバスタブで給水を共有しており、蛇口をシンク側かバスタブ側かどちらか一方にグイッと回して使う造りになっている。風呂を貯めながら歯磨きを済ませたいと思うと不便だ。大した問題ではないが、微かな「イラッと感」が以後なんとなく同系列のホテルを敬遠する理由になることもある。別のディスカウント系チェーンでは、部屋に電話が引かれていない代わりに宿泊客への伝言がエレベータの壁一面にポストイットされていたことがあった。スマホ全盛の昨今部屋の電話を使うことは(フロントへの用事以外)ないし、とりたてて実際的な支障があるわけでもない。でもコスト削減の企業努力がかくもわかりやすく眼前に展開されると、ある種の感動と同時に一抹の物悲しさを禁じ得ない。
日本の主要都市にあまねく展開するビジネスホテルは、部屋の大きさは必要最小限でお洒落感も低いが、清潔で設備に無駄なく機能的によく考えられているので泊まるだけなら快適だ。もっとも、効率化はしばしば快適性の犠牲の上に成り立つ。ある有名大手チェーンの浴室はシンクとバスタブで給水を共有しており、蛇口をシンク側かバスタブ側かどちらか一方にグイッと回して使う造りになっている。風呂を貯めながら歯磨きを済ませたいと思うと不便だ。大した問題ではないが、微かな「イラッと感」が以後なんとなく同系列のホテルを敬遠する理由になることもある。別のディスカウント系チェーンでは、部屋に電話が引かれていない代わりに宿泊客への伝言がエレベータの壁一面にポストイットされていたことがあった。スマホ全盛の昨今部屋の電話を使うことは(フロントへの用事以外)ないし、とりたてて実際的な支障があるわけでもない。でもコスト削減の企業努力がかくもわかりやすく眼前に展開されると、ある種の感動と同時に一抹の物悲しさを禁じ得ない。欧米ではビジネス仕様に特化したホテル形態は見当たらないが、安価を売りにするブランドなら米国に無数にある。典型的なものはDays InnとかComfort Inn(後者のほうが多分ちょっと格上)などの大手モーテルで、車で長距離移動する客を想定した安宿で都会より郊外や田舎に多い。アメリカに住んでいた頃、休みを取って国立公園巡りをする道中などよく利用していた。基本的にフランチャイズ経営と思われ、同じブランドでも当たり外れが極端なのがアメリカ的で面白い。事前に予約するならTripAdvisorのような口コミサイトをチェックしておくことは必須と言えよう。もっとも口コミサイトにわざわざ投稿する人はよほど良い思いをしたか相当酷い目にあったかどちらかの場合が多いので、意見が真っ二つに割れることも珍しくない。慣れてくるとコメントの行間から大方実態が想像できるようになる。アメリカの安モーテルで多い苦情は、不潔だ、あれこれ壊れてる、部屋のエアコンが航空機エンジン並にうるさい、フロントスタッフに全くやる気がない、といったあたりが定番だ。米国に住み慣れてしまえばこの程度の難点は想定内だが、日本のサービス標準を当然と思って行くと腰を抜かすかもしれない。
欧米の都市部については、中価格帯のニッチを占めているのは有名チェーンより地元の独立系が多い気がする。二ツ星・三ツ星でも室内のデザイン性にこだわりを主張するホテルは多く、機能重視で殺風景な日本のビジネスホテルとは好対照である。パリやロンドンのような大都市は地価も高いのでお値ごろの部屋は東京のビジネスホテル並に手狭だが、小さな空間を少しでも粋に演出する努力を惜しまない。ヨーロッパは古い住居等をホテルに転用している場合も珍しくないせいか、二つとして同じ規格の部屋がないホテルもある。歴史的建造物を現代的なホテルのニーズに併せて改装するには悩みも多いようだ。大型のスーツケースを持ち込むと2人目が乗れなくなる超小型エレベータとか、内扉がなくて目の前で壁が迫り上がっていく恐怖のエレベータとか、そもそもエレベータがあれば良い方で荷物を引きずって急な狭い階段をよじ登らないと部屋に到達できないホテルとか、堅牢な石造りの建築をリフォームする苦労が偲ばれる。アメリカでもニューヨークとかサンフランシスコなど古い建築が多く残る街は、ヨーロッパ的な独自規格のホテルに出会うことが多い。
欧米とひとまとめに書いたが、ヨーロッパとアメリカのホテルで決定的に違うのは朝食のクオリティである。アメリカのモーテルでContinental Breakfastといえば、出来合いのベーグルとマフィンにパサパサの食パン、コリコリのスクランブルエッグや味気ないソーセージを紙皿に取り分けるスタイルが普通だ。もともとコンチネンタル朝食という言葉は、英国が大陸蔑視のニュアンスを込めEnglish Breakfastと差別化するための呼称だと推測するが、フランスやドイツのホテルが出す「本家」コンチネンタルは仕入れたてのパン各種にハムやチーズがどっさりならび、アメリカでは決してお目にかかれない贅沢な品揃えである。日本のホテルも朝食に相当に力の入ったビュッフェを用意することは多いから、食文化に限れば「こだわりの日欧」と「ジャンクな米国」という構図になる。これはホテルの朝食に限らず、学校給食から空港ラウンジまで一様に見られる文化格差と言えよう。
各国のホテル事情は、お国柄の縮図でもある。投宿先でどんな過ごし方をしたいか、旅の楽しみ方一つでホテルのあり方も変わる。ホテルで寝転んで本を読むだけのひと時を至高の休暇と考えるか、過密スケジュールを消化するツアーに疲れて寝るだけがホテルの役割か。一ヶ月近く平気で職場を休んでヴァカンスを満喫するヨーロッパ人と比ぶべくもなく、お盆の一週間に夏休みの全てをかける日本人にとってホテルで無為の時を過ごすという贅沢は夢のまた夢だろうか。ホテルは雨風をしのげれば良いと割り切れば、安くて機能的であるに越したことはない。ビジネスホテルという日本固有の宿泊文化は、ビジネスか観光かという区別以前に、勤勉な日本人らしい旅行の価値観が集約されているのかもしれない。



