研究費の取れ高 [科学・技術]
我が国はイグノーベル賞の受賞者を17年連続で輩出しているのだそうである。主流からかけ離れた異色の研究を許容する包容力がある限り、日本の研究体力は健在だ。ただ、国内ではあまり知られていなかった成果を海外の人がせっせと発掘してくれる構図が興味深い。(個人的な経験に照らしても)非主流の研究を一番面白がって聞いてくれるのは、大抵海外の人だ。国内とくに研究費を配分する立場にいる人たちには、あまりそういう思考文化がない。
生命科学・医学分野の科研費支給額とその成果の「取れ高」を調べた論文が話題を呼んだ(筑波大プレスリリース)。投資効率としては、高額研究費を少数精鋭に措置するより、少額課題を多数に振り分けるほうがコスパが良いそうである。見栄えの良い大木ばかり選んで植えても害虫が大発生すれば全滅してしまうが、多様なタネを少しずつ蒔いておけばそのどれかが生き延びやがて巨木に育つ。生物多様性と同じで、さまざまな種が共存する生態系のほうが環境の変化に強いのである。
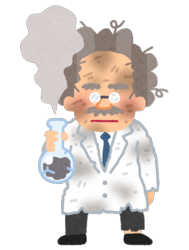 さらにこの論文によれば、研究費を受給する研究者にとっては額が大きい方が成果も上がるが、高額研究費(五千万円以上)になると頭打ちになり、ノーベル賞級の研究はむしろ創出されにくくなるという。億円単位のプロジェクトでしか実現できない研究ももちろんあるが、大型プロジェクトになると参加人数も増える。必然的に研究者はマネージメントに時間を取られ、サイエンスに割く知的投資は目減りする。
さらにこの論文によれば、研究費を受給する研究者にとっては額が大きい方が成果も上がるが、高額研究費(五千万円以上)になると頭打ちになり、ノーベル賞級の研究はむしろ創出されにくくなるという。億円単位のプロジェクトでしか実現できない研究ももちろんあるが、大型プロジェクトになると参加人数も増える。必然的に研究者はマネージメントに時間を取られ、サイエンスに割く知的投資は目減りする。
研究資金が無限にあるわけはないし、課題解決型の研究開発支援も大事なので、限定的な選択と集中はもちろん必要である。でも、選択と集中はやりすぎると費用対効果でむしろ逆効果というわけだ。
いわゆる10兆円ファンド(国際卓越研究大学)はかつてない規模の選択と集中で、一抜けした東北大はまだいいが、落選組は仕切り直しのために今後も膨大な時間と労力を費やすことだろう。そうやって国内の名立たる大学が疲弊していくかたわら、海外の研究コミュニティはどんどん先へ進んで行く。トップ論文の引用数で日本は今年も順位を下げたそうだが、鼻先のニンジンを追って鞭打ち走らされる現状を思えば、世界に水をあけられるのも無理もない。
誰もが「今」重要だと考えている研究ほど、賞味期限は短い。10年後や50年後の不確かな未来に備えるためには、モノになるかわからない研究に対する幅広い先行投資はどうしても必要なのである。
生命科学・医学分野の科研費支給額とその成果の「取れ高」を調べた論文が話題を呼んだ(筑波大プレスリリース)。投資効率としては、高額研究費を少数精鋭に措置するより、少額課題を多数に振り分けるほうがコスパが良いそうである。見栄えの良い大木ばかり選んで植えても害虫が大発生すれば全滅してしまうが、多様なタネを少しずつ蒔いておけばそのどれかが生き延びやがて巨木に育つ。生物多様性と同じで、さまざまな種が共存する生態系のほうが環境の変化に強いのである。
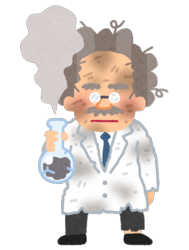 さらにこの論文によれば、研究費を受給する研究者にとっては額が大きい方が成果も上がるが、高額研究費(五千万円以上)になると頭打ちになり、ノーベル賞級の研究はむしろ創出されにくくなるという。億円単位のプロジェクトでしか実現できない研究ももちろんあるが、大型プロジェクトになると参加人数も増える。必然的に研究者はマネージメントに時間を取られ、サイエンスに割く知的投資は目減りする。
さらにこの論文によれば、研究費を受給する研究者にとっては額が大きい方が成果も上がるが、高額研究費(五千万円以上)になると頭打ちになり、ノーベル賞級の研究はむしろ創出されにくくなるという。億円単位のプロジェクトでしか実現できない研究ももちろんあるが、大型プロジェクトになると参加人数も増える。必然的に研究者はマネージメントに時間を取られ、サイエンスに割く知的投資は目減りする。研究資金が無限にあるわけはないし、課題解決型の研究開発支援も大事なので、限定的な選択と集中はもちろん必要である。でも、選択と集中はやりすぎると費用対効果でむしろ逆効果というわけだ。
いわゆる10兆円ファンド(国際卓越研究大学)はかつてない規模の選択と集中で、一抜けした東北大はまだいいが、落選組は仕切り直しのために今後も膨大な時間と労力を費やすことだろう。そうやって国内の名立たる大学が疲弊していくかたわら、海外の研究コミュニティはどんどん先へ進んで行く。トップ論文の引用数で日本は今年も順位を下げたそうだが、鼻先のニンジンを追って鞭打ち走らされる現状を思えば、世界に水をあけられるのも無理もない。
誰もが「今」重要だと考えている研究ほど、賞味期限は短い。10年後や50年後の不確かな未来に備えるためには、モノになるかわからない研究に対する幅広い先行投資はどうしても必要なのである。
Road to Perdition [映画・漫画]
 TBSの『VIVANT』最終話を見ていて、20年ほど前に見た映画『Road to Perdition』を思い出した。雑にまとめれば、大恐慌直後のアメリカ中西部を舞台に一匹狼の殺し屋がギャングと渡り合う話である。トム・ハンクスとポール・ニューマンに若き日のダニエル・クレイグ(まだジェームス・ボンドでなかったころ)が絡む、どこまでも渋く暗くそして哀しい映画である。
TBSの『VIVANT』最終話を見ていて、20年ほど前に見た映画『Road to Perdition』を思い出した。雑にまとめれば、大恐慌直後のアメリカ中西部を舞台に一匹狼の殺し屋がギャングと渡り合う話である。トム・ハンクスとポール・ニューマンに若き日のダニエル・クレイグ(まだジェームス・ボンドでなかったころ)が絡む、どこまでも渋く暗くそして哀しい映画である。ハンクス演じる凄腕の殺し屋サリヴァンは、孤児だった幼少時ニューマン演じるギャングのルーニーに引き取られ、我が子同然に育てられる。しかしそれが面白くないルーニーの実子コナーは、一計を案じサリヴァンを妻子もろとも消し去ろうとする。サリヴァン本人と長男マイケルは難を逃れるが、妻と次男は殺されてしまう。コナーへの復讐を誓うサリヴァンと、不良息子の蛮行に激怒しつつ実の息子を切り捨てられないルーニー。ギャングの非情な掟の中で、二人はやがてどちらも望んでいなかった直接対決へと追い込まれていく。
『Road to…』は、さまざまな父子の愛情と葛藤が交錯する映画だ。ルーニーとサリヴァン、ルーニーとコナー、そしてサリヴァンと幼いマイケル。よそよそしい父に孤独感を募らせていたマイケルだが、それが血塗られた己の道から息子を遠ざける父の想いに他ならないと気付くことになる。サリヴァンを追う刺客から父子二人で逃亡する道中の果て、ついに刺客と対峙した息子マイケル。しかし、彼は銃の引き金を引くことができない。マイケルが殺し屋の血を受け継がなかった事実を最期に目にしたサリヴァンは、息子の腕の中でホッとしたように息を引き取る。
物語の山場、息子同然のサリヴァンから銃口を向けられた絶体絶命のルーニーが、「I'm glad it's you=(俺を殺るのが)お前で良かった」と呟くシーンがある。『VIVANT』最終話でよく似た台詞が出てきたので、そこでふと『Road to…』を思い出したのである。実子と育ての子の確執というサイドストーリーも、二つの物語に共通している。
ただ『VIVANT』の作者は、国を守るためであれば手段を選ばない「別班」的哲学を、どちらかというと肯定的に描いている節がある。組織の掟が人間性を圧し潰す悲劇を描いた『Road to…』とは対照的だ。『VIVANT』はエンタメとしては破格に面白かったが、全体主義的な美学が無邪気に匂う甘さだけが、どこか喉に刺さった小骨のようにスッキリしない。
幸福の代償 その2 [社会]
コロナ禍が始まった3年半前の記事(これ)で、ル=グウィンの『オメラスから歩み去る者たち』のことを書いた。
 事件が大きく取り上げられたきっかけは、BBC制作のドキュメンタリー番組だった。海外ジャーナリズム発の告発がなかったら、日本の大手メディアは今なお沈黙を貫いていたかもしれない。ジャニー氏の性犯罪疑惑はかつて告発本でたびたび取り上げられ、民事訴訟の事実認定ではジャニーズ事務所が敗訴した。しかしテレビ局や新聞社は未必の故意により隠蔽に加担し続けた。その理由は、商業的にジャニタレを手放せないメディアの忖度と説明される。その要素はもちろんあるだろうが、問題の根源はもう少し深い気がする。
事件が大きく取り上げられたきっかけは、BBC制作のドキュメンタリー番組だった。海外ジャーナリズム発の告発がなかったら、日本の大手メディアは今なお沈黙を貫いていたかもしれない。ジャニー氏の性犯罪疑惑はかつて告発本でたびたび取り上げられ、民事訴訟の事実認定ではジャニーズ事務所が敗訴した。しかしテレビ局や新聞社は未必の故意により隠蔽に加担し続けた。その理由は、商業的にジャニタレを手放せないメディアの忖度と説明される。その要素はもちろんあるだろうが、問題の根源はもう少し深い気がする。
被害を訴えた元タレントに対する誹謗中傷が後を絶たないと言う。「知りたくもなかった事実」に苛立ちを感じる人が、ジャニーズのファンにすら(むしろファンだからこそ)一定数いるのである。自分の愛する心地よい世界が、おぞましい犯罪と引き換えに成立していると知った時、それを断罪するより必要悪として受け入れることを選ぶ。『オメラス』の世界で人知れず幽閉されていた子供は、日本に実在していたのである。
ジャニーズ問題をメディアがスルーし続けた理由の一部は、それが「社会が求めていない」報道だったからではないか。ストイックに真相を追求する心あるジャーナリストも少くないはずだが、メディアの大半は市場価値の薄いコンテンツに見向きもしない。結果として社会の沈黙は続き、犠牲者は救われなかった。事件を黙殺したメディアがジャニーズ事務所と共犯だとすれば、醜い現実を受け入れるより知らないフリを好む社会も、完全に潔白とは言えないはずだ。
『ゲド戦記』を書いたアメリカの作家アーシュラ・ル=グウィンの短編に『オメラスから歩み去る者たち』という不思議な作品がある。オメラスとは犯罪や戦争と無縁な平和に満たされた架空の街で、人々が思い思いに夏の到来を祝って集う華やいだ日常が綴られる。だがこの街の一角にただ一人、その幸福を分かち合うことの許されない孤独な子供がいる。子供は窓のない小部屋に幽閉されたまま劣悪な環境に放置され、気遣いの言葉一つかけてもらうことすら叶わない。オメラスで育つ少年少女は遅かれ早かれそんな街の秘密を知り、当然ながら憤りや悲しみに震える者もいる。だが彼らはやがて、子供が置かれた現実を直視することを止める。何故なら、不幸な子供の犠牲の上にこそ街の平穏な秩序が支えられていると気付いているからだ。もし子供を救い自由のもとに解き放てば、オメラスの人々が享受する幸福の日々は遠からず終わりを告げる。ハーバード大サンデル教授は、この物語を題材にベンサムが言う「最大多数の最大幸福」の是非を問いかけた。多数の幸福と引き換えに少数の犠牲を容認するベンサムの理論は、民主化が行き届いた現代社会では到底受け入れられない。しかし、ル=グウィンはベンサム理論の教材として『オメラス』を書いたわけではない。
ただ、ル=グウィンの思考の源泉はもっと深いところにある。オメラスの人々は賢人でも聖人でもなく、欲も弱さも併せ持った私たちと同じ人間だ。彼らは至上の幸福を手にしながら、心の底ではその幸福がいつ潰えるかと怖れている。御伽話のような桃源郷を信じるほどウブではないから、幸福を維持するには相応の代償が必要だと考える。作者は、幽閉された子供がどうやって社会の幸福に奉仕しているのか、その仕組みについては一切触れない。なぜなら、子供の犠牲が続く限り社会の安寧が担保されると人々が「信じている」こと、その盲目的な信念の裏に潜む秩序崩壊への怖れこそが、物語の本質だからだ。これを書いた時は、コロナ禍初期に社会を覆いつつあった漠然とした恐怖に『オメラス』を重ねていた。いま再びオメラスを持ち出したのは、最近巷を賑わせている全く別の事件を想起させるからだ。ジャニー喜多川氏の性加害問題である。
 事件が大きく取り上げられたきっかけは、BBC制作のドキュメンタリー番組だった。海外ジャーナリズム発の告発がなかったら、日本の大手メディアは今なお沈黙を貫いていたかもしれない。ジャニー氏の性犯罪疑惑はかつて告発本でたびたび取り上げられ、民事訴訟の事実認定ではジャニーズ事務所が敗訴した。しかしテレビ局や新聞社は未必の故意により隠蔽に加担し続けた。その理由は、商業的にジャニタレを手放せないメディアの忖度と説明される。その要素はもちろんあるだろうが、問題の根源はもう少し深い気がする。
事件が大きく取り上げられたきっかけは、BBC制作のドキュメンタリー番組だった。海外ジャーナリズム発の告発がなかったら、日本の大手メディアは今なお沈黙を貫いていたかもしれない。ジャニー氏の性犯罪疑惑はかつて告発本でたびたび取り上げられ、民事訴訟の事実認定ではジャニーズ事務所が敗訴した。しかしテレビ局や新聞社は未必の故意により隠蔽に加担し続けた。その理由は、商業的にジャニタレを手放せないメディアの忖度と説明される。その要素はもちろんあるだろうが、問題の根源はもう少し深い気がする。被害を訴えた元タレントに対する誹謗中傷が後を絶たないと言う。「知りたくもなかった事実」に苛立ちを感じる人が、ジャニーズのファンにすら(むしろファンだからこそ)一定数いるのである。自分の愛する心地よい世界が、おぞましい犯罪と引き換えに成立していると知った時、それを断罪するより必要悪として受け入れることを選ぶ。『オメラス』の世界で人知れず幽閉されていた子供は、日本に実在していたのである。
ジャニーズ問題をメディアがスルーし続けた理由の一部は、それが「社会が求めていない」報道だったからではないか。ストイックに真相を追求する心あるジャーナリストも少くないはずだが、メディアの大半は市場価値の薄いコンテンツに見向きもしない。結果として社会の沈黙は続き、犠牲者は救われなかった。事件を黙殺したメディアがジャニーズ事務所と共犯だとすれば、醜い現実を受け入れるより知らないフリを好む社会も、完全に潔白とは言えないはずだ。



