前の10件 | -
一平さんの事件 その5 [スポーツ]
 他に書くネタが見当たらないので、性懲りもなく水原一平事件を掘り下げたい。36ページに及ぶ告訴状(PDF)をつらつら眺めていたら、あまりメディアで取り上げられない細部で興味深い点がいくつか目に付いた。
他に書くネタが見当たらないので、性懲りもなく水原一平事件を掘り下げたい。36ページに及ぶ告訴状(PDF)をつらつら眺めていたら、あまりメディアで取り上げられない細部で興味深い点がいくつか目に付いた。G章(21ー23ページ)に水原さんが大谷選手を騙り銀行に電話した記録の具体例が載っている。一度目は2022年2月2日で、彼がオオタニ口座の連絡先を自分の管理下に変更した直後に当たる。自動車ローンと偽り送金を試みたが、チャレンジ失敗でオンライン取引がロックされた。同じ日に再び電話して別の担当者と話し、本人確認の質問事項をパスして凍結解除に成功した。数日後、再び電話して30万ドルの送金を試みたが、未遂(attempted)に終わったようである。
この3回に関しては、ロック解除の一度を除くと「大谷サンのフリ」作戦は基本的に失敗している。訴状の脚注には、大谷選手を騙る水原さんの音声は流暢な英語を喋っていたとある。大谷本人ならネイティブ並みの英語は話せないはずとピンときたかは定かでないが、対応に出た銀行員は何かがおかしいと判断した様子である。とはいえ、やがて同じ口座から水原さんによる高額送金(50万ドルずつ)が繰り返されるようになる。不審電話の履歴がありながら結果的に度重なる不正出金を見逃したのは、銀行側も脇が甘かったのではないか?
訴状のI章(26ー30ページ)で、大谷選手のエージェントや資産管理チームに聴収した結果が載っている。オオタニ口座へのアクセスを「大谷選手がプライバシーを望んでいる」という建前で水原さんが独占していたことは、すでに報道されているとおりだ。しかし、利子収入や贈与の出金があれば納税義務が発生する。大谷選手の経理担当者、フィナンシャルアドバイザー、税理士はいずれもこの点を指摘したが、水原さんはオオタニ口座に利子は発生せず贈与もなかったと説明したそうである。
それでチームが「ああそうですか」と引き下がったのなら、恐ろしくヤル気のない人たちである。高額資産を丸ごと無利子口座(Checking account)に放置しておくなど、常識では考えられない。フィナンシャルアドバイザーは、適切な資産運用をクライアントに勧めるのが仕事のはずだ。それに、Tax Return(米国の確定申告)の時期になると銀行は利子収入の証明書を発行するので、私が税理士ならせめてその書面だけでも見せて欲しいと言うだろう(そこに取引履歴は載らないのでプライバシーは漏れない)。それすら水原さんが却下したなら、さすがに不審に思うべきだ。下手をすれば大谷選手が脱税に問われかねない案件であり、そういうことが起こらないために税理士が付いているはずではないか。
訴状のK章(31ー33ページ)では、送金に大谷選手の同意を得ていたとする水原さんの証言に疑念を示す捜査官の意見が示されている。その最後の文章がこれだ。
Further, I do not find it credible that Victim A would have agreed to pay MIZUHARA’s gambling debts from the x5848 Account while allowing MIZUHARA to deposit the winnings from his gambling into MIZUHARA’s bank account.これを読んだ時なるほどと思ったのは、仮に大谷選手が水原さんのギャンブル損失を払ったなら、勝った儲けの分け前も要求するはずだ、という前提に捜査側は立っているのである。そういう視点で訴状を読み返すと、捜査官の言葉遣いにいろいろ納得がいく。(もともと金に執着のない)大谷さんが水原さんがギャンブルから足を洗えるようにと自腹で損失を埋めた、という当初ESPNから出て来た物語を、わざわざドライに再解釈した上で大谷選手の関与を否定しているのである。結論としては大谷選手の潔白を証明する訴状ではあるが、同時に日本人が考えるピュアな大谷像がアメリカでは共有されていない事実を図らずも象徴している点が面白い。
さらに、水原の賭博勝ち金がミズハラ口座に振り込まれることを許容しながら、賭博負債をx5848口座(=オオタニ口座)から支払うことに被害者A(=大谷選手)が同意するとは、考えられない。
一平さんの事件 その4 [スポーツ]
水原一平さんの事件が急に動いた。連邦検事の会見が行われ、水原さんが大谷選手を騙って銀行を欺こうとした電話記録とか、胴元との生々しいテキストメッセージの応酬とか、いろいろ闇の深い話が出てきた。何よりも、大谷口座から不正に出金された総額が1600万ドルとされ、今まで出ていた話からさらに数倍グレードアップした。庶民感覚ではもはや何のことやら訳がわからない。
白黒がハッキリしたのは前進だが、被害額が膨れ上がっただけに、大谷選手が一度たりとも異変に気付かなかった事件の特殊性はかえって際立った。水原さんがオオタニ口座の連絡先を自分宛に変えていた痕跡があるそうだ。普通そういう時は、あなた設定変えましたかという確認メールが元の(大谷選手の)アドレスに届く不正抑止措置がある。それに、正常な取引のアラートもある日を境にピタリと届かなくなれば、何かを疑うきっかけになっただろう。大谷選手にとって、銀行からの通知はもともと何の意味もなかったようである。
訴状によれば、大谷選手には専属の資産管理チームがいたが、水原さんは大谷選手の意向と称して彼らがオオタニ口座へアクセスするのを阻止していたそうである。資産管理担当者がクライアントの口座を見られないなんて、プロとして悲しくないのか。彼らの誰も、水原さんを怪しいと思わなかったのだろうか?
実はこういうことだったんじゃないかと最近思っていた一つの仮説がある。
 ギャンブルの損失に困った水原さんが、ある日ふと魔が差してオオタニ口座におそるおそる手を付けた。次の賭けに勝ったらこっそり埋め合わせておけばいい、と最初は思っていた。その時はまだ少額で、本人を騙って銀行を煙に巻くのも不可能ではなかった。だがあれよあれよと負けがかさみ、負債はみるみる隠しきれない規模に達した。万事窮した水原さんは、洗いざらい大谷選手に打ち明けた。大谷選手は当然ムッとしただろうが、見るに見かねて手を差し伸べることにし、白紙小切手委任の状態を事実上黙認した。その結果、送金に大谷選手は関与しない傍ら、もう賭けはやらないと改心したはずの水原さんに歯止めが利かなくなった。ギャンブル依存症の彼にとって、アルコール依存症患者が酒蔵の鍵を預けられるようなものだったわけである。
ギャンブルの損失に困った水原さんが、ある日ふと魔が差してオオタニ口座におそるおそる手を付けた。次の賭けに勝ったらこっそり埋め合わせておけばいい、と最初は思っていた。その時はまだ少額で、本人を騙って銀行を煙に巻くのも不可能ではなかった。だがあれよあれよと負けがかさみ、負債はみるみる隠しきれない規模に達した。万事窮した水原さんは、洗いざらい大谷選手に打ち明けた。大谷選手は当然ムッとしただろうが、見るに見かねて手を差し伸べることにし、白紙小切手委任の状態を事実上黙認した。その結果、送金に大谷選手は関与しない傍ら、もう賭けはやらないと改心したはずの水原さんに歯止めが利かなくなった。ギャンブル依存症の彼にとって、アルコール依存症患者が酒蔵の鍵を預けられるようなものだったわけである。
というのはもちろん単なる妄想だ。ただ、水原さんの二転三転した証言に説明がつくし、イッペイは本当に信用できるかと資産管理チームに問われた(としても不思議のない)大谷選手が事を荒立てなかった背景も理解できる。大谷選手のスマホに不審な記録が残っていなかった捜査結果とも矛盾はない(常に行動を共にしていたかつての二人の関係なら、電話など不要だったはずだ)。そして、今年2月ドジャーズのイベントで大谷選手が水原さんを「友達ではない、割り切って付き合っている」と言った発言の真意も想像がつく。
水原さんは数年にわたり不正送金を隠し通せるほど計画的犯罪の素質があるようには見えなかったし、大谷選手が足元で数十億円相当の預金が消えていくことにまるで気が付かないほどウブだとも思っていなかった。大谷選手自身が自己資産に無関心だったとしても、それを代わりに管理すべきプロ集団がギャンブル狂の一通訳にコロリと騙されるとも思わなかった。でも、落としどころはそういうことだったようである。事実は小説より奇なりということなのか、呆れるほど単純だったと言うべきなのか。
(大谷選手の金を)勝手に使い込んだわけではないんだろ、と念を押す胴元に対し、水原さんはこう答えたという。
白黒がハッキリしたのは前進だが、被害額が膨れ上がっただけに、大谷選手が一度たりとも異変に気付かなかった事件の特殊性はかえって際立った。水原さんがオオタニ口座の連絡先を自分宛に変えていた痕跡があるそうだ。普通そういう時は、あなた設定変えましたかという確認メールが元の(大谷選手の)アドレスに届く不正抑止措置がある。それに、正常な取引のアラートもある日を境にピタリと届かなくなれば、何かを疑うきっかけになっただろう。大谷選手にとって、銀行からの通知はもともと何の意味もなかったようである。
訴状によれば、大谷選手には専属の資産管理チームがいたが、水原さんは大谷選手の意向と称して彼らがオオタニ口座へアクセスするのを阻止していたそうである。資産管理担当者がクライアントの口座を見られないなんて、プロとして悲しくないのか。彼らの誰も、水原さんを怪しいと思わなかったのだろうか?
実はこういうことだったんじゃないかと最近思っていた一つの仮説がある。
 ギャンブルの損失に困った水原さんが、ある日ふと魔が差してオオタニ口座におそるおそる手を付けた。次の賭けに勝ったらこっそり埋め合わせておけばいい、と最初は思っていた。その時はまだ少額で、本人を騙って銀行を煙に巻くのも不可能ではなかった。だがあれよあれよと負けがかさみ、負債はみるみる隠しきれない規模に達した。万事窮した水原さんは、洗いざらい大谷選手に打ち明けた。大谷選手は当然ムッとしただろうが、見るに見かねて手を差し伸べることにし、白紙小切手委任の状態を事実上黙認した。その結果、送金に大谷選手は関与しない傍ら、もう賭けはやらないと改心したはずの水原さんに歯止めが利かなくなった。ギャンブル依存症の彼にとって、アルコール依存症患者が酒蔵の鍵を預けられるようなものだったわけである。
ギャンブルの損失に困った水原さんが、ある日ふと魔が差してオオタニ口座におそるおそる手を付けた。次の賭けに勝ったらこっそり埋め合わせておけばいい、と最初は思っていた。その時はまだ少額で、本人を騙って銀行を煙に巻くのも不可能ではなかった。だがあれよあれよと負けがかさみ、負債はみるみる隠しきれない規模に達した。万事窮した水原さんは、洗いざらい大谷選手に打ち明けた。大谷選手は当然ムッとしただろうが、見るに見かねて手を差し伸べることにし、白紙小切手委任の状態を事実上黙認した。その結果、送金に大谷選手は関与しない傍ら、もう賭けはやらないと改心したはずの水原さんに歯止めが利かなくなった。ギャンブル依存症の彼にとって、アルコール依存症患者が酒蔵の鍵を預けられるようなものだったわけである。というのはもちろん単なる妄想だ。ただ、水原さんの二転三転した証言に説明がつくし、イッペイは本当に信用できるかと資産管理チームに問われた(としても不思議のない)大谷選手が事を荒立てなかった背景も理解できる。大谷選手のスマホに不審な記録が残っていなかった捜査結果とも矛盾はない(常に行動を共にしていたかつての二人の関係なら、電話など不要だったはずだ)。そして、今年2月ドジャーズのイベントで大谷選手が水原さんを「友達ではない、割り切って付き合っている」と言った発言の真意も想像がつく。
水原さんは数年にわたり不正送金を隠し通せるほど計画的犯罪の素質があるようには見えなかったし、大谷選手が足元で数十億円相当の預金が消えていくことにまるで気が付かないほどウブだとも思っていなかった。大谷選手自身が自己資産に無関心だったとしても、それを代わりに管理すべきプロ集団がギャンブル狂の一通訳にコロリと騙されるとも思わなかった。でも、落としどころはそういうことだったようである。事実は小説より奇なりということなのか、呆れるほど単純だったと言うべきなのか。
(大谷選手の金を)勝手に使い込んだわけではないんだろ、と念を押す胴元に対し、水原さんはこう答えたという。
Technically I did steal from him. It’s all over for me.彼は「Technically」と前置きすることで、何を仄めかしたかったのか? そこを誰かに聞いてみたい。
厳密な意味では、盗みだったんだ。もう何もかもおしまいだ。
オッペンハイマー:映画編 [映画・漫画]
クリストファー・ノーラン監督の映画『オッペンハイマー』が日本で公開され、ようやく待望の大作を観る機会を得た。この作品に関しては、「広島と長崎の惨禍が描かれていないのがけしからん」という論評を時折り耳にするが、いささか的外れな批判である。被爆国目線で何か言っておくのが日本人の見識ということかもしれないが、映画はあくまでオッペンハイマーの半生を彼自身の内面に照らして描いたフィクションであり、原爆開発のドキュメンタリーではない。
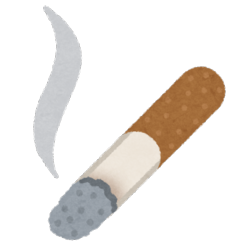 主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
映画の原案となった伝記本を読むと、内面が複雑に揺れ一筋縄では読み解き難いオッペンハイマー像が浮かび上がる(原著編で書いた)。映画『オッペンハイマー』はそんな彼の人物像を丁寧に再構築する。原爆開発を成功に導いた天才科学者が後に罪の意識から反核思想に転向する、といった直線的なヒューマンドラマでは全くない。象徴的なのは、原爆投下成功の報せに沸くロスアラモスの研究所で、オッペンハイマーが職場の同僚たちから拍手喝采で称えられる場面だ。歓喜に足を踏み鳴らす喧騒に迎えられ演壇に立った彼は、狂喜する聴衆の中に熱線が焼き尽くす被爆者の幻影を見る。以後オッペンハイマーにとって、英雄の栄光は破壊神の汚名と不可分になった。
オッペンハイマーが熱線の幻を見るシーンが、終盤にもう一度だけ登場する。原子力委員会の聴聞会で、22万人を超える広島と長崎の甚大な犠牲の事実を突きつけられ、彼が良心の呵責を認めた場面だ。ならばなぜ原爆の実戦使用に反対しなかったのか? 原爆を容認しながらなぜ戦後水爆開発に抵抗し続けたのか? 畳みかけられる詰問にオッペンハイマーは必死で正当化を試みるが、己の矛盾に心のどこかで気付いている。ひどく混乱した彼の頭中で観衆の踏み鳴らす靴音がフラッシュバックし、聴聞会の小さな部屋を眩い閃光が貫く。場面は上院公聴会の時間軸と目まぐるしく交差し、オッペンハイマーの偽善を罵るストロースの怒号がかぶる。史実の舞台装置を借りてオッペンハイマーを苛む心の軋みを鮮やかに可視化した、息を呑むクライマックスである。
オッペンハイマーを賞賛も非難もせず、彼の葛藤と矛盾を渾然一体のまま白日の下に晒すことが、この映画の着地点だ。幕切れの直前、ロスアラモスを勇退しプリンストンの高等研究所長に招かれたばかりのオッペンハイマーがアインシュタインと交わした会話が明かされる。当時のアインシュタインはすでに、本人が創始に関わった量子力学に背を向ける孤高の人であった。アインシュタインは、自ら生み出した魔物を持て余すオッペンハイマーに同じ運命の影を嗅ぎ取り、のちに訪れる試練を仄めかす暗い予言を告げる。この会話自体はおそらくフィクションだが、三時間にわたる長尺に深い余韻を残す見事なエンディングだ。
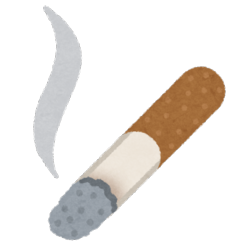 主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。映画の原案となった伝記本を読むと、内面が複雑に揺れ一筋縄では読み解き難いオッペンハイマー像が浮かび上がる(原著編で書いた)。映画『オッペンハイマー』はそんな彼の人物像を丁寧に再構築する。原爆開発を成功に導いた天才科学者が後に罪の意識から反核思想に転向する、といった直線的なヒューマンドラマでは全くない。象徴的なのは、原爆投下成功の報せに沸くロスアラモスの研究所で、オッペンハイマーが職場の同僚たちから拍手喝采で称えられる場面だ。歓喜に足を踏み鳴らす喧騒に迎えられ演壇に立った彼は、狂喜する聴衆の中に熱線が焼き尽くす被爆者の幻影を見る。以後オッペンハイマーにとって、英雄の栄光は破壊神の汚名と不可分になった。
オッペンハイマーが熱線の幻を見るシーンが、終盤にもう一度だけ登場する。原子力委員会の聴聞会で、22万人を超える広島と長崎の甚大な犠牲の事実を突きつけられ、彼が良心の呵責を認めた場面だ。ならばなぜ原爆の実戦使用に反対しなかったのか? 原爆を容認しながらなぜ戦後水爆開発に抵抗し続けたのか? 畳みかけられる詰問にオッペンハイマーは必死で正当化を試みるが、己の矛盾に心のどこかで気付いている。ひどく混乱した彼の頭中で観衆の踏み鳴らす靴音がフラッシュバックし、聴聞会の小さな部屋を眩い閃光が貫く。場面は上院公聴会の時間軸と目まぐるしく交差し、オッペンハイマーの偽善を罵るストロースの怒号がかぶる。史実の舞台装置を借りてオッペンハイマーを苛む心の軋みを鮮やかに可視化した、息を呑むクライマックスである。
オッペンハイマーを賞賛も非難もせず、彼の葛藤と矛盾を渾然一体のまま白日の下に晒すことが、この映画の着地点だ。幕切れの直前、ロスアラモスを勇退しプリンストンの高等研究所長に招かれたばかりのオッペンハイマーがアインシュタインと交わした会話が明かされる。当時のアインシュタインはすでに、本人が創始に関わった量子力学に背を向ける孤高の人であった。アインシュタインは、自ら生み出した魔物を持て余すオッペンハイマーに同じ運命の影を嗅ぎ取り、のちに訪れる試練を仄めかす暗い予言を告げる。この会話自体はおそらくフィクションだが、三時間にわたる長尺に深い余韻を残す見事なエンディングだ。
一平さんの事件 その3 [スポーツ]
このブログで水原事件を引っ張り続けるのもどうかと思ったが、日本メディアの分析が今一つ冴えないので、私が理解している限りの情報をメモ代わりに整理したい。別にMLBや違法ギャンブル事情に詳しいわけではないので、誤解もあるかもしれない。
 アメリカの国税局IRSや国土安全省DHS(最近報道で耳にするHSIはDHSの一部門である)が調査に乗り出しているという。これら連邦機関の調査対象は、専ら違法賭博の胴元Matthew Bowyer氏であって、賭博の顧客ではない。ただし胴元の資金洗浄に関与していた疑いが出れば、捜査の関心が向く。今回の事件では水原さんの負債の穴埋めに大谷選手の口座から送金されていたという話が出たため、レッドフラッグが立ってしまった。想像するに、賭博の支払いが別人名義で行われたことで、捜査機関にはあたかもギャンブル収入が脱税目的で資金洗浄されたように見えているのである。
アメリカの国税局IRSや国土安全省DHS(最近報道で耳にするHSIはDHSの一部門である)が調査に乗り出しているという。これら連邦機関の調査対象は、専ら違法賭博の胴元Matthew Bowyer氏であって、賭博の顧客ではない。ただし胴元の資金洗浄に関与していた疑いが出れば、捜査の関心が向く。今回の事件では水原さんの負債の穴埋めに大谷選手の口座から送金されていたという話が出たため、レッドフラッグが立ってしまった。想像するに、賭博の支払いが別人名義で行われたことで、捜査機関にはあたかもギャンブル収入が脱税目的で資金洗浄されたように見えているのである。
Bowyer氏が大谷選手とのつながりを自慢していたという裏話があり、顧客獲得の釣りにオオタニの名を利用していたとされる。一方、公式には弁護士を通じ大谷選手との接触は一度もなかったと断言している。後者が真実と思うが、わざわざそう強調した魂胆は、上記の理由でオオタニ名義の送金を表向き賭博ビジネスから切り離したいのではないか。現実には大谷選手や水原さんがBowyer氏の資金洗浄に関わったとは考えにくいので、捜査の過程でIRSとDHSは二人に対する関心を失うのではと思われる。
それと別に、MLBは独自に調査を進めるそうだ。MLBはもちろん法的な捜査権は持たないが、選手のスポーツ賭博に関しては厳しい内規がある。連邦捜査機関とは逆に、MLBの調査対象は胴元ではなく賭けた本人である。大谷選手が水原さんの賭博関与を知っていたのか、その違法性を認識していたのか、あたりの判断で処分の有無や重さが変わるとされる。大谷選手自身がギャンブルをやっていたわけではないので、処分があっても罰金程度だろうという見方が主流のようだ。とは言え、彼のクリーンなイメージが被るダメージは決して侮れない。そして案の定、大谷選手は胴元への送金を一切知らないという話で統一された。限りなくクロに近いクライアントでもシロに見せる能力が、米国で有能な弁護士の証である。基本的にホワイトな大谷選手を真っ白にするくらい、朝飯前だろう。
大谷選手側は、水原さんが口座に無断でアクセスしたと主張している。それがどうして可能だったか、大谷選手は何も語らなかった。もし水原さんが口座管理を丸投げされていて、二段階認証のアドレスにもアクセスできたなら、原理的に横領は容易だという見立てもある。ただ米国セレブ界の常識では、大谷選手ほどの資産家に危機管理チームがついていないとは信じがたいようである。それに、50万ドル規模の大金が何度も出金されれば、銀行側が必ず察知して然るべき確認作業が取られるという。米国メディアでは、大谷選手が何も知らなかったとする主張には懐疑的な論調が少なくない。
大谷選手サイドの告発に従えば、水原さんは窃盗ないし横領の容疑に問われることになる。ESPNはこの件に関する捜査状況を取材しようとしたが、関連当局の動きは未だに掴めていないという。被害をどこに報告したのかESPNが大谷選手の弁護士に繰り返し質問したものの、大谷選手の代理人は一貫して回答を拒んでいるらしい。拒否の理由は明らかにされておらず、憶測の余地を生んでいる。極端な話、窃盗の報告はどこにも提出されていないのではないか、という推察も成り立つ。
大谷選手は会見で、水原さんの「ウソ」を次から次へ指摘した。いずれもあまりに無計画で杜撰なウソばかりで、他人を騙し続ける才覚は微塵も感じさせない。水原さんが後先を考えない虚言癖の持ち主ということなら、確かにそういう人は世間に存在する。そうであれば、大谷選手ほど長い付き合いなら、折に触れ「コイツ時々言ってることおかしい」と虚言に疑念を持つ機会はなかったのか? それで友情が冷え切るとは限らないが、そういう人物に全幅の信頼を置き続けるとは考えにくいし、まして口座管理を丸投げするはずもない。それならどうやって水原さんに送金ができたのか、と結局同じ疑問に戻ってくる。本当に水原さんの「ウソ」はすべて嘘だったのか?
本当のことを言う人と嘘をつく人の二分論で整理しようとすると、どうしても辻褄が合わない。もし誰もが少しずつ真実でないことを語っているとするなら、パズルの断片から一枚の絵が浮かび上がってくる。最大の問題は、パズルが完成することを当事者の誰も望んでいないことである。
 アメリカの国税局IRSや国土安全省DHS(最近報道で耳にするHSIはDHSの一部門である)が調査に乗り出しているという。これら連邦機関の調査対象は、専ら違法賭博の胴元Matthew Bowyer氏であって、賭博の顧客ではない。ただし胴元の資金洗浄に関与していた疑いが出れば、捜査の関心が向く。今回の事件では水原さんの負債の穴埋めに大谷選手の口座から送金されていたという話が出たため、レッドフラッグが立ってしまった。想像するに、賭博の支払いが別人名義で行われたことで、捜査機関にはあたかもギャンブル収入が脱税目的で資金洗浄されたように見えているのである。
アメリカの国税局IRSや国土安全省DHS(最近報道で耳にするHSIはDHSの一部門である)が調査に乗り出しているという。これら連邦機関の調査対象は、専ら違法賭博の胴元Matthew Bowyer氏であって、賭博の顧客ではない。ただし胴元の資金洗浄に関与していた疑いが出れば、捜査の関心が向く。今回の事件では水原さんの負債の穴埋めに大谷選手の口座から送金されていたという話が出たため、レッドフラッグが立ってしまった。想像するに、賭博の支払いが別人名義で行われたことで、捜査機関にはあたかもギャンブル収入が脱税目的で資金洗浄されたように見えているのである。Bowyer氏が大谷選手とのつながりを自慢していたという裏話があり、顧客獲得の釣りにオオタニの名を利用していたとされる。一方、公式には弁護士を通じ大谷選手との接触は一度もなかったと断言している。後者が真実と思うが、わざわざそう強調した魂胆は、上記の理由でオオタニ名義の送金を表向き賭博ビジネスから切り離したいのではないか。現実には大谷選手や水原さんがBowyer氏の資金洗浄に関わったとは考えにくいので、捜査の過程でIRSとDHSは二人に対する関心を失うのではと思われる。
それと別に、MLBは独自に調査を進めるそうだ。MLBはもちろん法的な捜査権は持たないが、選手のスポーツ賭博に関しては厳しい内規がある。連邦捜査機関とは逆に、MLBの調査対象は胴元ではなく賭けた本人である。大谷選手が水原さんの賭博関与を知っていたのか、その違法性を認識していたのか、あたりの判断で処分の有無や重さが変わるとされる。大谷選手自身がギャンブルをやっていたわけではないので、処分があっても罰金程度だろうという見方が主流のようだ。とは言え、彼のクリーンなイメージが被るダメージは決して侮れない。そして案の定、大谷選手は胴元への送金を一切知らないという話で統一された。限りなくクロに近いクライアントでもシロに見せる能力が、米国で有能な弁護士の証である。基本的にホワイトな大谷選手を真っ白にするくらい、朝飯前だろう。
大谷選手側は、水原さんが口座に無断でアクセスしたと主張している。それがどうして可能だったか、大谷選手は何も語らなかった。もし水原さんが口座管理を丸投げされていて、二段階認証のアドレスにもアクセスできたなら、原理的に横領は容易だという見立てもある。ただ米国セレブ界の常識では、大谷選手ほどの資産家に危機管理チームがついていないとは信じがたいようである。それに、50万ドル規模の大金が何度も出金されれば、銀行側が必ず察知して然るべき確認作業が取られるという。米国メディアでは、大谷選手が何も知らなかったとする主張には懐疑的な論調が少なくない。
大谷選手サイドの告発に従えば、水原さんは窃盗ないし横領の容疑に問われることになる。ESPNはこの件に関する捜査状況を取材しようとしたが、関連当局の動きは未だに掴めていないという。被害をどこに報告したのかESPNが大谷選手の弁護士に繰り返し質問したものの、大谷選手の代理人は一貫して回答を拒んでいるらしい。拒否の理由は明らかにされておらず、憶測の余地を生んでいる。極端な話、窃盗の報告はどこにも提出されていないのではないか、という推察も成り立つ。
大谷選手は会見で、水原さんの「ウソ」を次から次へ指摘した。いずれもあまりに無計画で杜撰なウソばかりで、他人を騙し続ける才覚は微塵も感じさせない。水原さんが後先を考えない虚言癖の持ち主ということなら、確かにそういう人は世間に存在する。そうであれば、大谷選手ほど長い付き合いなら、折に触れ「コイツ時々言ってることおかしい」と虚言に疑念を持つ機会はなかったのか? それで友情が冷え切るとは限らないが、そういう人物に全幅の信頼を置き続けるとは考えにくいし、まして口座管理を丸投げするはずもない。それならどうやって水原さんに送金ができたのか、と結局同じ疑問に戻ってくる。本当に水原さんの「ウソ」はすべて嘘だったのか?
本当のことを言う人と嘘をつく人の二分論で整理しようとすると、どうしても辻褄が合わない。もし誰もが少しずつ真実でないことを語っているとするなら、パズルの断片から一枚の絵が浮かび上がってくる。最大の問題は、パズルが完成することを当事者の誰も望んでいないことである。
一平さんの事件 その2 [スポーツ]
 大谷翔平選手の会見が行われた。水原さんの違法賭博事件について、大谷選手は全く関知していないという「公式」版のストーリーを裏付ける証言に終始した。すなわち、水原さんが数か月から一年にわたり大谷選手の口座に無断アクセスを繰り返して大金をくすね、メディアの追及には(どう考えてもすぐにばれる)嘘を作り込んで語り、一方で大谷選手はつい先週までその異常に全く気付かなかった、ということである。もし水原さんが確信犯的な(しかし絶望的に詰めの甘い)詐欺師で、大谷選手が資金管理や身辺の異変にまるで無頓着な無類の野球バカであった、ということなら、(いろいろと残念だが)あり得ない話ではない。
大谷翔平選手の会見が行われた。水原さんの違法賭博事件について、大谷選手は全く関知していないという「公式」版のストーリーを裏付ける証言に終始した。すなわち、水原さんが数か月から一年にわたり大谷選手の口座に無断アクセスを繰り返して大金をくすね、メディアの追及には(どう考えてもすぐにばれる)嘘を作り込んで語り、一方で大谷選手はつい先週までその異常に全く気付かなかった、ということである。もし水原さんが確信犯的な(しかし絶望的に詰めの甘い)詐欺師で、大谷選手が資金管理や身辺の異変にまるで無頓着な無類の野球バカであった、ということなら、(いろいろと残念だが)あり得ない話ではない。だがどうにも腑に落ちないのは、大谷選手が真相を知ったのがドジャーズのチームミーティングの場だったという証言である。それに先立ち代理人が問題を把握していたことを、大谷選手自身が語っている。チームに対して話が明かされる前に、当事者である大谷選手に代理人から何の説明もなかったということがあり得るだろうか? チームミーティングで大谷選手が困惑したという話は既に報道で出ていて、彼が「知らなかった」ことを印象付ける演出めいた匂いを感じていた。大谷選手は水原さんがメディアの取材に応じたことを事前に聞いていなかったと会見で述べているので、彼がチームミーティングで知って驚いたのはそっちなのではないか、という憶測も成り立つ。
ところで、今回の騒動は大谷選手を巡る日米の温度差を図らずも浮き彫りにしたように思う。日本人の目に映る大谷選手は、野球の本場アメリカで頂点を競う国民的英雄である。日本のメディアはシーズン前から大谷選手の一挙手一投足に注目し、キャンプで勢い余ってトレーニング器具を引きちぎるだけでニュースになる。しかしアメリカ国内では、エンゼルスやドジャーズのコアなファンならともかく、大谷選手は数多いるメジャーリーガーの一人に過ぎない。野球にとりたてて関心のない多くの米国人は、名前は知っていても大谷選手に何ら特別の思い入れはない。
それはちょうど、日本人にとってのモンゴル人力士のようなものではないか。現役時代の朝青龍は、モンゴルの人たちには日本の国技に乗り込み横綱として君臨する英雄であった。だが、生粋の相撲ファンを別にすれば、日本人の大半にとって朝青龍は「ああ、あの力士ね」くらいの存在に過ぎなかったはずだ。いろいろとやんちゃな素行に事欠かなかったので、どちらかというとネガティブな印象を持つ人も多かったかもしれない。もしモンゴル力士が日本の角界で話題をさらうことを密かに快く思わない人がいたとすれば、同じことは大谷選手がアメリカでどう受容されるかについても言えるのである。
その意味で、水原さんの事件により大谷選手はかなり微妙な状況に追い込まれている。もし彼が水原さんの窮状を見かねて借金を肩代わりしたのが真相だったとしても、それが感涙の友情エピソードとして処理されるほど米国人は大谷選手に愛着はない。大谷選手の代理人はそこに美談を見なかったからこそ、大谷選手を水原事件から完全に切り離す作戦に打って出たのだと思っていた。大谷会見後の今も、その印象は払拭できていない。
或いは、大谷選手側の主張どおり一から十まで水原さんが水面下で仕組んだ犯行だったのかもしれない。だがいずれにせよ、質疑なし12分の会見が大谷選手の名誉回復にどれだけ寄与したか、その効果はあまり見えない。大谷選手に非がある話ではないのに、誠意に欠けるような印象を与えかねない対応戦略は大丈夫なのか、とか他人事ながらいろいろ心配している。
一平さんの事件 [スポーツ]
 水原一平さんのドジャーズ解雇という報道に仰天した。大谷翔平選手の専属通訳で良きバディだったはずの水原さんが、違法スポーツ賭博に手を出したばかりか、損失の穴埋めに総計数百万ドルに及ぶ大金が大谷選手名義で送金されたというのである。大リーグ開幕戦の祝祭感も吹っ飛ぶ、破壊力全開のニュースだ。ドジャーズお膝元のLos Angeles Timesとスポーツ系チャンネルESPNの記事をざっと読むと、だいたい次のような経緯が浮かび上がる。
水原一平さんのドジャーズ解雇という報道に仰天した。大谷翔平選手の専属通訳で良きバディだったはずの水原さんが、違法スポーツ賭博に手を出したばかりか、損失の穴埋めに総計数百万ドルに及ぶ大金が大谷選手名義で送金されたというのである。大リーグ開幕戦の祝祭感も吹っ飛ぶ、破壊力全開のニュースだ。ドジャーズお膝元のLos Angeles Timesとスポーツ系チャンネルESPNの記事をざっと読むと、だいたい次のような経緯が浮かび上がる。捜査機関はまだ表立った動きがなく、メディアのスクープが事件発覚のきっかけだった。大谷口座からの送金データに異変を察知したESPNの取材に対し、水原さんは初め大谷選手の同意のもと損失を埋め合わせてもらったと語った。そのとき大谷選手は明らかに不満げであったが、水原さんが足を洗えるならと送金に同意した、ということである。ところが取材の翌日、大谷選手は何も知らなかったと水原さんは前言を翻した。これを裏付けるように、大谷側の弁護士は大谷選手を水原さんによる「窃盗の被害者」とする声明を出した。胴元側は弁護士を通じ大谷選手と直接の接触はなかったと明言しており、大谷選手自身が賭博に関わっていない点では証言が一致している。
現時点では、相容れない二つのシナリオが共存する奇妙な状況にある。大谷選手が自らの意志で水原さんの擦った金を肩代わりしたという当初の説明と、そうではなくて水原さんが無断で大谷選手の金を使い込んだという話である。公式には、関係者の証言は後者のストーリーに収束する様相を見せている。これが事実なら、大谷選手が補填を承諾したという最初の説明が水原さんの真っ赤なウソだったことになり、破廉恥の誹りも免れない事態である。
しかし、窃盗説にはいろいろ不可解な点がある。ESPNが把握した送金記録は昨年の9月と10月(各50万ドル)だそうだが、それほどの規模の「窃盗」が持ち主に何カ月も気付かれずに済むだろうか? そもそも、プロのハッカーでもない一般人が他人の口座に手を付けられるだろうか? 水原さんが大谷選手の資産管理を一任されてでもいない限り、かなり無理のある話に聞こえる。
カリフォルニア州では、スポーツ賭博は違法である。水原さんは違法性を知らなかったと証言しているが、ドジャーズの一員であった立場を考えると妙に脇が甘い。あり得る可能性としては、彼のギャンブル癖に目をつけた胴元が、言葉巧みに合法性を装い水原さんを巻き込んだのかもしれない。スポーツ賭博の経営者からすれば、名門球団のインサイダーを取り込む旨味は大きいはずだ。水原さん自身はさすがにメジャーリーグの賭けには関与していなかったというが、大金を擦った弱みに付け込み情報提供者のように顧客を利用する下心が胴元側にあったとしても、不思議ではない気がする。
もし大谷選手が事情を承知で送金を許したのだとすれば、下手をすれば違法賭博に手を貸した嫌疑をかけられる。そのリスクを断ち切るため、大谷選手の弁護士は窃盗被害という落としどころで話を整理したがっているように見える。水原さんにとっては、賭博と無関係の大谷選手を道連れにするのは本意でないはずだから、自分が窃盗の罪を被る覚悟を決めたのかもしれない。ESPNに直撃された当初は、動揺のあまり大谷選手に降りかかる火の粉まで想像が及ばず、経緯をそのまま話してしまったのではないか。
大谷選手はたぶん、窮地に陥った友人を救いたかっただけなのではと想像する。結果として違法賭博に加担してしまうように見られるリスクが彼の頭によぎったかどうかは、わからない。ただ、二人の関係としてわれわれが知るパブリックイメージから察するに、進退窮まった水原さんが大谷選手を裏切り私財を着服したという物語より、リスクに思い至らず(あるいは承知で)大谷選手が水原さんに手を差し伸べたシナリオのほうが、何だかありそうな気がするのである。
安楽死の権利 [社会]
 テレビの報道番組を何気なく見ていたら、安楽死の特集をやっていた。日本では認められていないが、スイスのように一定の条件下で安楽死が合法とされている国もある。番組が取材したのは、事故の後遺症や進行性の難病に苦しみ安楽死を求めてスイスを訪れた人たちだ。親族や友人に見送られながら死を迎える人や独り静かに旅立つ人がいれば、直前に迷いを見せ中断を言い渡される人もいる。もちろん、余命幾ばくもない病を抱えながら、苦痛を受け入れ命を全うする道を選択する人もいる。
テレビの報道番組を何気なく見ていたら、安楽死の特集をやっていた。日本では認められていないが、スイスのように一定の条件下で安楽死が合法とされている国もある。番組が取材したのは、事故の後遺症や進行性の難病に苦しみ安楽死を求めてスイスを訪れた人たちだ。親族や友人に見送られながら死を迎える人や独り静かに旅立つ人がいれば、直前に迷いを見せ中断を言い渡される人もいる。もちろん、余命幾ばくもない病を抱えながら、苦痛を受け入れ命を全うする道を選択する人もいる。自殺を罪として裁く法律は日本にはないが、自殺幇助は犯罪である。犯罪でない行為をアシストしただけで罪に問われるのは非合理な気もするが、これにはいろいろ法学論争があるようだ。ざっと調べたところ、命の決定権に他者が介入すべきでない、という漠然とした倫理観に落ち着く解説が多い。だが見方を変えれば、本来は個人のものであるべき死生観に国家が恣意的に踏み込んでいる、という批判もあり得る。
仮に安楽死が合法化されると、安易に死を選ぶ人が増えるという指摘がある。ただ「安易」かどうかは当事者の訴えにじっくり耳を傾けないと判断できない話で、一般論として整理するのは難しい。また、安楽死の合法化は死を望まない難病患者に対する謂われなき偏見を生む、という懸念を上述の番組の中で聞いた。他者には何の脅威でもないはずの個人の権利が、同質性を指向する社会によって静かに排除される。同性婚や夫婦別姓の問題に似た同調圧力の陰が、ここにも垣間見える。
死の選択は重い決断である。安楽死の是非について、誰もが納得する回答は存在しない。だから安楽死が合法の国でも、耐え難い苦痛・治療の不可能性・本人の自発的な意思確認、などさまざまな条件をクリアする必要がある。社会の側が注意深くハードルを設定した上で、あとは個人の選択に委ねられる。先日、ALS患者に対する嘱託殺人で医師が京都地裁から懲役刑を言い渡される判決が出た。安楽死が違法の日本でそのニーズがアングラに潜り、結果として本来厳格に適用されるべき倫理規範が法で守られなかったのだとすれば、現行法制度の矛盾を示唆する皮肉な事件である。
安楽死の問題とは、究極的には当事者の死を選ぶ権利を社会が制度的に容認できるか、ということである。容認できない社会が未熟ということではないが、日本が少なくとも成熟した議論が成立する国であってほしいと思う。
オッペンハイマー:原著編 [科学・技術]
アカデミー賞の受賞者が発表され、日本では『君たちはどう生きるか』や『ゴジラ-1.0』の受賞が話題を呼んでいるが、今年最大の注目は何と言っても7部門を席巻した『オッペンハイマー』であった。原爆開発責任者の半生を描いた映画だけに、国内世論を気にしたか日本での配給が決まるまでかなり時間を要した(3月下旬にようやく封切られることになった)。映画のネタ本は、 Kai BirdとMartin J. Sherwin共著『American Prometheus』という大部で濃密な伝記である。映画は半月後まで見られないので、今回は原著の話を書きたい。
 『American Prometheus』はオッペンハイマーの誕生から死までを克明に描いたノンフィクションである。とてつもない量の資料から浮かび上がるオッペンハイマー像は、複雑で一筋縄では行かない人物だ。幼少期から早熟の秀才だったが、今で言う発達障害を思わせるぎこちない言動に事欠かなかった。マンハッタン計画を率いるオッペンハイマーは誰もが認めるカリスマ性に輝いていたが、極度のストレス下で冷静な判断を誤る危うさが彼自身をやがて苦境に追い込む。やわらかい物腰の中に暖かい思いやりを見せる時があれば、人を見下したような自信と傲慢さが同僚の反感を買うこともあった。終戦直後は時の人としてもてはやされるが、赤狩りの狂気が吹き荒れた1950年代、オッペンハイマーは政敵ルイス・ストロースの異常な敵意と執念に追い詰められる。
『American Prometheus』はオッペンハイマーの誕生から死までを克明に描いたノンフィクションである。とてつもない量の資料から浮かび上がるオッペンハイマー像は、複雑で一筋縄では行かない人物だ。幼少期から早熟の秀才だったが、今で言う発達障害を思わせるぎこちない言動に事欠かなかった。マンハッタン計画を率いるオッペンハイマーは誰もが認めるカリスマ性に輝いていたが、極度のストレス下で冷静な判断を誤る危うさが彼自身をやがて苦境に追い込む。やわらかい物腰の中に暖かい思いやりを見せる時があれば、人を見下したような自信と傲慢さが同僚の反感を買うこともあった。終戦直後は時の人としてもてはやされるが、赤狩りの狂気が吹き荒れた1950年代、オッペンハイマーは政敵ルイス・ストロースの異常な敵意と執念に追い詰められる。
マンハッタン計画は、ナチスドイツの原爆開発に対する強い危機感から始まった。ユダヤ人であったオッペンハイマーが感じていたであろう使命感は想像に難くない。だが彼を含め、マンハッタン計画のため米国全土から集められた頭脳は、本来は軍事産業と縁もゆかりもない自然科学者たちだった。核分裂の原理を兵器に応用する前代未聞のプロジェクトには、当時まだ黎明期であった現代原子物理学の深い知識を要したからである。もともとは自然の成り立ちを解き明かす純粋な目的のもとで育まれた叡智が、大量破壊兵器の開発に惜しげもなく注ぎ込まれた。トリニティ実験に立ち会った科学者たちは、彼らが解き放った魔物の恐ろしい破壊力を目にして、ただ言葉を失った。
ドイツ降伏後、日本に対する原爆投下の是非について科学者たちの意見は割れた。無警告で原爆を実戦使用することに反対する署名活動も行われた。オッペンハイマー自身は投下反対の立場ではなかったが、すでに敗戦が濃厚な敵国に原爆を用いる正当性に疑念を持っていたようである。しかしオッペンハイマー自身は、原爆投下の政治的決定に関与を許される立場にはなかった。
オッペンハイマーの心に、原爆開発の指揮を執った事実が生涯暗い影を落とし続けたことは疑いない。終戦後、トルーマン大統領との面会の場で「私の手は血塗られているような気がします」と呟いたと伝えられている。他方で、彼は原爆開発を主導した功績を恥じることはなかった。戦後日本を訪れたオッペンハイマーは、心情の変化について問われこう答えた。
被爆国に生まれ育ち広島と長崎の惨禍を知る私たちにとって、オッペンハイマーの評価は難しい。戦後の彼は戦術核論者ではあったが、米ソの対立を煽りかねない戦略核には懐疑的で、とくに水爆開発には明確に反対した。自身の信念ゆえ政府のタカ派に公然と異を唱えたオッペンハイマーは、その点で米国内に今も根強い素朴な原爆肯定論とは大きく立場が異なる。結果的にマッカーシズムの犠牲者として表舞台から姿を消したが、そうでなかったらオッペンハイマーはきな臭い冷戦の世界にどんな影響を与えていただろうか? それが光だったのか闇だったのかにわかに想像が及ばない曖昧さが、オッペンハイマーという人物の本質を物語っているように思える。
 『American Prometheus』はオッペンハイマーの誕生から死までを克明に描いたノンフィクションである。とてつもない量の資料から浮かび上がるオッペンハイマー像は、複雑で一筋縄では行かない人物だ。幼少期から早熟の秀才だったが、今で言う発達障害を思わせるぎこちない言動に事欠かなかった。マンハッタン計画を率いるオッペンハイマーは誰もが認めるカリスマ性に輝いていたが、極度のストレス下で冷静な判断を誤る危うさが彼自身をやがて苦境に追い込む。やわらかい物腰の中に暖かい思いやりを見せる時があれば、人を見下したような自信と傲慢さが同僚の反感を買うこともあった。終戦直後は時の人としてもてはやされるが、赤狩りの狂気が吹き荒れた1950年代、オッペンハイマーは政敵ルイス・ストロースの異常な敵意と執念に追い詰められる。
『American Prometheus』はオッペンハイマーの誕生から死までを克明に描いたノンフィクションである。とてつもない量の資料から浮かび上がるオッペンハイマー像は、複雑で一筋縄では行かない人物だ。幼少期から早熟の秀才だったが、今で言う発達障害を思わせるぎこちない言動に事欠かなかった。マンハッタン計画を率いるオッペンハイマーは誰もが認めるカリスマ性に輝いていたが、極度のストレス下で冷静な判断を誤る危うさが彼自身をやがて苦境に追い込む。やわらかい物腰の中に暖かい思いやりを見せる時があれば、人を見下したような自信と傲慢さが同僚の反感を買うこともあった。終戦直後は時の人としてもてはやされるが、赤狩りの狂気が吹き荒れた1950年代、オッペンハイマーは政敵ルイス・ストロースの異常な敵意と執念に追い詰められる。マンハッタン計画は、ナチスドイツの原爆開発に対する強い危機感から始まった。ユダヤ人であったオッペンハイマーが感じていたであろう使命感は想像に難くない。だが彼を含め、マンハッタン計画のため米国全土から集められた頭脳は、本来は軍事産業と縁もゆかりもない自然科学者たちだった。核分裂の原理を兵器に応用する前代未聞のプロジェクトには、当時まだ黎明期であった現代原子物理学の深い知識を要したからである。もともとは自然の成り立ちを解き明かす純粋な目的のもとで育まれた叡智が、大量破壊兵器の開発に惜しげもなく注ぎ込まれた。トリニティ実験に立ち会った科学者たちは、彼らが解き放った魔物の恐ろしい破壊力を目にして、ただ言葉を失った。
ドイツ降伏後、日本に対する原爆投下の是非について科学者たちの意見は割れた。無警告で原爆を実戦使用することに反対する署名活動も行われた。オッペンハイマー自身は投下反対の立場ではなかったが、すでに敗戦が濃厚な敵国に原爆を用いる正当性に疑念を持っていたようである。しかしオッペンハイマー自身は、原爆投下の政治的決定に関与を許される立場にはなかった。
オッペンハイマーの心に、原爆開発の指揮を執った事実が生涯暗い影を落とし続けたことは疑いない。終戦後、トルーマン大統領との面会の場で「私の手は血塗られているような気がします」と呟いたと伝えられている。他方で、彼は原爆開発を主導した功績を恥じることはなかった。戦後日本を訪れたオッペンハイマーは、心情の変化について問われこう答えた。
I do not think coming to Japan changed my sense of anguish about my part in this whole piece of history. Nor has it fully made me regret my responsibility for the technical success of the enterprise.これに続き、少し謎めいた言葉を残している。
この歴史的な出来事に関わり私が感じてきた苦悶が、日本を訪れたことで変わったとは思いません。(原爆開発)事業の技術的成功で果たした私の責任を後悔するに至ったということもありません。
It isn’t that I don’t feel bad. It is that I don’t feel worse tonight than last night.破格に明晰な頭脳に恵まれた彼すら、自身の内面が抱える矛盾を整理しあぐねていたようである。
申し訳ないと思う気持ちがないという意味ではありません。ただ、その気持ちが日々強くなっているわけではない、ということです。
被爆国に生まれ育ち広島と長崎の惨禍を知る私たちにとって、オッペンハイマーの評価は難しい。戦後の彼は戦術核論者ではあったが、米ソの対立を煽りかねない戦略核には懐疑的で、とくに水爆開発には明確に反対した。自身の信念ゆえ政府のタカ派に公然と異を唱えたオッペンハイマーは、その点で米国内に今も根強い素朴な原爆肯定論とは大きく立場が異なる。結果的にマッカーシズムの犠牲者として表舞台から姿を消したが、そうでなかったらオッペンハイマーはきな臭い冷戦の世界にどんな影響を与えていただろうか? それが光だったのか闇だったのかにわかに想像が及ばない曖昧さが、オッペンハイマーという人物の本質を物語っているように思える。
ほぼトラ [政治・経済]
 今年秋のアメリカ大統領選を控え、共和党予備選でトランプ氏が圧勝した。バイデン大統領にトランプ氏が挑む構図は、4年前と攻守が入れ替わっただけで一向に代わり映えがしない。世論調査ではトランプ氏の人気が上回り、巷では「もしトラ」とか「ほぼトラ」とか来るべきトランプ政権を見据えたさまざまな観測が飛び交っている。
今年秋のアメリカ大統領選を控え、共和党予備選でトランプ氏が圧勝した。バイデン大統領にトランプ氏が挑む構図は、4年前と攻守が入れ替わっただけで一向に代わり映えがしない。世論調査ではトランプ氏の人気が上回り、巷では「もしトラ」とか「ほぼトラ」とか来るべきトランプ政権を見据えたさまざまな観測が飛び交っている。トランプ氏の強さは、いくら失言をしようと支持率が下がらないことである。関税ボッタくり宣言とか、費用負担の少ないNATO加盟国はロシアにやられちまえ発言とか、とりわけ対外政策に関わるトランプ発言はハチャメチャ極まりない。つねに暴言だらけなのだが、暴言に溜飲を下げる人々が一定数おり、トランプ氏を熱狂的に支持しているのだ。彼のMAGA(Make America Great Again)思想は、支持者の耳にはたぶん「俺たちさえよければ、それでいいじゃないか」と聞こえているに違いない。耳に心地よいだけならまだしも、MAGAの延長上で何をやりだすかわからない予測不可能性がトランプ再選後のリスクである。
バイデン大統領はトランプ氏のような攻撃性はないが、この人はこの人で奇妙な失言が多い。ミッテランをドイツの大統領と言い間違え、慌ててフランスと言い直したが、「マクロンだろ」とツッコむ余地を残した見事なボケっぷりであった。期待値の低さという点では、トランプ氏とは別の意味でバイデン大統領は「これ以上がっかりすることはない」的な安定感がある。人口3億3千万を超える国で、なぜこの二人より人望のある大統領候補が現れないのか、と首を傾げているのは私だけではあるまい。
ロボット掃除機を買いに行ったら、中古品が2台だけ売れ残っていたしよう。一台は、自分の部屋はきれいに履き清めるが、溜まったゴミを他人の部屋にぶちまけ知らん顔をする。もう一台は、保証期間をとうに過ぎて掃除の最中に理解不能なエラーメッセージを吐く。どうしてもその場で掃除機を手に入れなければならないとしたら、どちらを選ぶべきか? いま米国市民に突きつけられているのは、そんな問いかもしれない。
セクハラ町長 [社会]
 岐南町町長のセクハラ・パワハラ問題が報道を賑わせている。岐南町ホームページに調査報告書が載っているが、問題発言・問題行為の指摘は99件に及ぶ。下の名前を「ちゃん」付けで呼ぶという微妙な案件から、抱きつく・尻を触るといった完全アウトな蛮行まで、この方お一人だけでセクハラ事例集完全版が出版できそうだ。
岐南町町長のセクハラ・パワハラ問題が報道を賑わせている。岐南町ホームページに調査報告書が載っているが、問題発言・問題行為の指摘は99件に及ぶ。下の名前を「ちゃん」付けで呼ぶという微妙な案件から、抱きつく・尻を触るといった完全アウトな蛮行まで、この方お一人だけでセクハラ事例集完全版が出版できそうだ。一般論としては、セクハラのラインを超えるかどうかは、受け止める側の心象次第だという意見もある。「ちゃん」付けで呼ばれた人が気分を害さなければ、たぶん誰も問題にしない。が、尻を触るような上司から「ちゃん」で呼ばれたら、大抵の人は気持ち悪がるだろう。セクハラをするから人望がないのと同時に、人望がないから何を言ってもハラスメントになるのである。
とはいえ、ハラスメント防止のガイドラインを決める以上、客観的に適用可能な善悪の基準を定めておく必要がある。基準が緩すぎると被害者が泣き寝入りする羽目になるし、逆に厳格すぎると冤罪につながりかねない。ハラスメント被害者に寄り添う時代の流れは基本的に正しいと思うが、際限なくコンプラのハードルを上げ続けることで社会の正義が自ずと実現するわけでもない。
問題の町長は昭和の価値観から抜けられない人物とあちこちで評されており、ある意味ではその通りだが、別に昭和の時代がこういう人ばかりだったわけではない。件の町長の問題は、そもそも人間として「ちゃんとしてない」ことに尽きる。人として真っ当であることの価値は、昭和も令和も基本は何も変わっていない。
前の10件 | -



