ルドルフの憂鬱(後編) [フィクション]
(前編からつづく)
「去年の大きなお家から引っ越してたんだね。注文票の住所を確かめなかったら、間違えるところじゃった。」
カップを片手にサンタが言うと、少女は目を伏せたまま答えた。
「ママが私を連れてパパのお家を出たから。ご覧のとおりちっちゃいマンションだけど、まあまあ快適かな。」
ルドルフとサンタは顔を見合せた。
「サンタさんとトナカイさん、呼びつけたりして迷惑だった? 何であたし、エスプレッソごちそうしますなんて書いちゃったんだろ。」
サンタが慌てて言葉を継いだ。
「いや、全然かまわんよ。話し相手にわざわざ呼んでくれるなんて、サンタには最高のご褒美じゃ。」
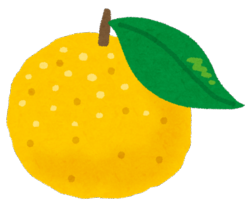 少女が顔を上げて言った。
少女が顔を上げて言った。
「ね、ゆず湯って知ってる?サンタさんたちのお国にはないかもしれないけど。」
ポカンとしているサンタの隣で、ルドルフが言った。
「お風呂に柚子を浮かべるやつかい? 日本の冬至の風習だとか聞いたことあるけど。」
「うん、トナカイさん物知りね。柚子ってなんでお湯に浮かぶんだと思う?」
サンタが首を捻った。
「それはあれかな、柚子が水より軽いからかな? アルキメデスの原理とか言われとるんじゃったか。」
「そういうのよくわからないけど、このあいだお風呂で浮かぶ柚子を見てふと思ったの。あたしは川底に沈んでいる柚子なんだって。」
サンタとルドルフは再び顔を見合せた。
「底から見上げるとね、ほかの柚子たちはみんな川面にぷかぷか浮いているのよ。陽射しを浴びて、きれいなオレンジ色に輝いて、澄んだ水の流れに身を任せてみな一緒に去っていくの。あたしはひとり、暗い川底でじっとして、それを見てるだけ。」
サンタは口を開いたが、かける言葉が見つからず、また口を閉じた。
「学校も楽しくないわけじゃないんだけどさ。でもみんな水面でコツコツぶつかり合う柚子みたいに仲良く盛り上がってるのに、あたしだけ独り別の世界にいるみたいな。」
ルドルフが言った。
「でもさ、見方を変えれば、他の子たちは流れに逆らえず漂っていくだけなのに、君だけが自分の居場所で踏ん張っているわけだ。それって、簡単なことじゃないと思うな。」
少女は少し考えてから、軽く頷いた。
「みんなが楽しそうでうらやましいって思うのと、あたしはそうじゃなくていいっていう気持ちが、ずっとぶつかってるの。でも、いつまでもこうやって川底に沈んだまま、コケまみれの大人になっていくのかなって思うと、イヤになっちゃうんだよね。」
膝に置いた手を見つめる少女に、ルドルフは優しく語りかけた。
「柚子は何で水に浮くのかってさっき聞いたよね? それはさ、浮かび上がろうとする力がもともと備わっているからだよ。今は眠っているかもしれないけど、もちろん君のなかにも。」
夜の静寂を破る冷たい北風が、つかのま窓を揺らした。
「そうかな…。」
「今はそう思えなくてもいいんだ。君がいつか水面に浮かび上がりたいと思ったときに、ちゃんと体のなかから湧いてくるから。」
膝の上でぎゅっと組まれた少女の両手が、かすかに震えた。少女はうつむいたまま、聞きとれないくらい小さな声で呟いた。
「なんだか、疲れちゃった。あたし、もう寝るね。勝手ばかり言って、ごめんなさい。でも、来てくれてほんとにありがとう。」
クリスマス配送を終えた深夜、北極圏某所の自宅でサンタは暖炉に薪をくべながら言った。
「なあルドルフ、もしかしておまえも、昔あの子みたいに感じていた頃があるのかい?」
疲労困憊で横になっていたルドルフは、火かき棒で薪をつつくサンタの背中を見やった。
「あの子? ああ、柚子の話っすか?」
そう言って何気なく伸びをしたルドルフは、前脚の痛みに顔をしかめた。
「トナカイはマイノリティなんです、絶滅危惧種ですから。暗い川底から遠い陽射しを見上げるような想いをしたのは、うちらの仲間じゃ珍しくないと思いますよ。」
静かに煌めく暖炉の炎を見つめながら、サンタは小さく溜息をついた。
「おまえとは長い付き合いだが、まだ知らないことがたくさんある。自分が人にとって何をできる人間なのか、わしはいまでも時々よくわからなくなるんじゃ。」
ルドルフはソファからゆっくり起き上がった。
「サンタ先輩ほど世の役に立っている人はなかなかいませんよ。ただせっかくそう仰るんなら、もう一つ役に立ってもらっていいっすか? あっしの前脚の湿布、取り替えて欲しいんですけど。」
(おわり)
※ 2人の前日譚はこちら。
1. 北極圏某所にて
2. 北極圏某所にて 2021
3. サンタの憂鬱(前編)
4. サンタの憂鬱(中編)
5. サンタの憂鬱(後編)
6. ルドルフの憂鬱(前編)
「去年の大きなお家から引っ越してたんだね。注文票の住所を確かめなかったら、間違えるところじゃった。」
カップを片手にサンタが言うと、少女は目を伏せたまま答えた。
「ママが私を連れてパパのお家を出たから。ご覧のとおりちっちゃいマンションだけど、まあまあ快適かな。」
ルドルフとサンタは顔を見合せた。
「サンタさんとトナカイさん、呼びつけたりして迷惑だった? 何であたし、エスプレッソごちそうしますなんて書いちゃったんだろ。」
サンタが慌てて言葉を継いだ。
「いや、全然かまわんよ。話し相手にわざわざ呼んでくれるなんて、サンタには最高のご褒美じゃ。」
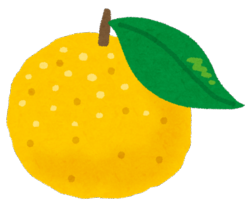 少女が顔を上げて言った。
少女が顔を上げて言った。「ね、ゆず湯って知ってる?サンタさんたちのお国にはないかもしれないけど。」
ポカンとしているサンタの隣で、ルドルフが言った。
「お風呂に柚子を浮かべるやつかい? 日本の冬至の風習だとか聞いたことあるけど。」
「うん、トナカイさん物知りね。柚子ってなんでお湯に浮かぶんだと思う?」
サンタが首を捻った。
「それはあれかな、柚子が水より軽いからかな? アルキメデスの原理とか言われとるんじゃったか。」
「そういうのよくわからないけど、このあいだお風呂で浮かぶ柚子を見てふと思ったの。あたしは川底に沈んでいる柚子なんだって。」
サンタとルドルフは再び顔を見合せた。
「底から見上げるとね、ほかの柚子たちはみんな川面にぷかぷか浮いているのよ。陽射しを浴びて、きれいなオレンジ色に輝いて、澄んだ水の流れに身を任せてみな一緒に去っていくの。あたしはひとり、暗い川底でじっとして、それを見てるだけ。」
サンタは口を開いたが、かける言葉が見つからず、また口を閉じた。
「学校も楽しくないわけじゃないんだけどさ。でもみんな水面でコツコツぶつかり合う柚子みたいに仲良く盛り上がってるのに、あたしだけ独り別の世界にいるみたいな。」
ルドルフが言った。
「でもさ、見方を変えれば、他の子たちは流れに逆らえず漂っていくだけなのに、君だけが自分の居場所で踏ん張っているわけだ。それって、簡単なことじゃないと思うな。」
少女は少し考えてから、軽く頷いた。
「みんなが楽しそうでうらやましいって思うのと、あたしはそうじゃなくていいっていう気持ちが、ずっとぶつかってるの。でも、いつまでもこうやって川底に沈んだまま、コケまみれの大人になっていくのかなって思うと、イヤになっちゃうんだよね。」
膝に置いた手を見つめる少女に、ルドルフは優しく語りかけた。
「柚子は何で水に浮くのかってさっき聞いたよね? それはさ、浮かび上がろうとする力がもともと備わっているからだよ。今は眠っているかもしれないけど、もちろん君のなかにも。」
夜の静寂を破る冷たい北風が、つかのま窓を揺らした。
「そうかな…。」
「今はそう思えなくてもいいんだ。君がいつか水面に浮かび上がりたいと思ったときに、ちゃんと体のなかから湧いてくるから。」
膝の上でぎゅっと組まれた少女の両手が、かすかに震えた。少女はうつむいたまま、聞きとれないくらい小さな声で呟いた。
「なんだか、疲れちゃった。あたし、もう寝るね。勝手ばかり言って、ごめんなさい。でも、来てくれてほんとにありがとう。」
クリスマス配送を終えた深夜、北極圏某所の自宅でサンタは暖炉に薪をくべながら言った。
「なあルドルフ、もしかしておまえも、昔あの子みたいに感じていた頃があるのかい?」
疲労困憊で横になっていたルドルフは、火かき棒で薪をつつくサンタの背中を見やった。
「あの子? ああ、柚子の話っすか?」
そう言って何気なく伸びをしたルドルフは、前脚の痛みに顔をしかめた。
「トナカイはマイノリティなんです、絶滅危惧種ですから。暗い川底から遠い陽射しを見上げるような想いをしたのは、うちらの仲間じゃ珍しくないと思いますよ。」
静かに煌めく暖炉の炎を見つめながら、サンタは小さく溜息をついた。
「おまえとは長い付き合いだが、まだ知らないことがたくさんある。自分が人にとって何をできる人間なのか、わしはいまでも時々よくわからなくなるんじゃ。」
ルドルフはソファからゆっくり起き上がった。
「サンタ先輩ほど世の役に立っている人はなかなかいませんよ。ただせっかくそう仰るんなら、もう一つ役に立ってもらっていいっすか? あっしの前脚の湿布、取り替えて欲しいんですけど。」
(おわり)
※ 2人の前日譚はこちら。
1. 北極圏某所にて
2. 北極圏某所にて 2021
3. サンタの憂鬱(前編)
4. サンタの憂鬱(中編)
5. サンタの憂鬱(後編)
6. ルドルフの憂鬱(前編)
ルドルフの憂鬱(前編) [フィクション]
 「サンタ先輩、あっしはもうダメです。老いぼれトナカイなぞ見捨てて、先輩だけで行ってください。」
「サンタ先輩、あっしはもうダメです。老いぼれトナカイなぞ見捨てて、先輩だけで行ってください。」「ルドルフ、何を大袈裟なこと言っておるのだ。しばらく休めば大丈夫だ。そもそも、お前がいなければソリを動かせないじゃないか。」
サンタはそう言いながら、道の駅のコーヒースタンドで買ったカプチーノをルドルフに差し出した。ルドルフはカップにほんの少し口をつけた途端、目を白黒させた。
「あちっ。人間って何でこんなに熱いもの飲むんすか?」
「慌てなくていい。ゆっくり飲めば体が温まる。」
カプチーノを恐るおそるすすり、ルドルフはふぅっとため息をついた。口の周りに付いたミルクの泡を見て、サンタが笑った。
「わしの髭みたいだな。一回り老けたように見えるぞ。」
ルドルフは恨めしそうにサンタを見つめた。
「実際、すっかり老けた気分ですよ。若い頃は、こんな風に配達の途中で脚にガタがくるなんてこと、なかったのに。」
サンタはルドルフの痩せた前脚をそっとさすった。
「無理をさせて悪かったな。おまえもぼちぼち引退を考えて不思議はない歳なのに。」
「一晩で配達を終えないといけないんで、無理を押すのは仕方ないっす。でも、来年以降はやりくり大変ですよ。2024年問題とか言って、この国では物流ドライバーの時間外労働が厳しく制限されるそうじゃないすか。あっしも法的には運送業の労働者ですからね。」
サンタは自分のカフェラテをぐいっと飲んだ。
「実はな、そろそろお前に楽をさせたいと思って、秋ごろから新人を数頭スカウトしようとしたんじゃ。でも求人にさっぱり応募がない。どこも人手不足なんじゃな。」
「トナカイに関して言えば、人手不足どころじゃないですよ。2016年には絶滅危惧種のレッドリスト入りしましたからね。」
サンタはルドルフをまじまじと見つめた。
「おまえ、そんな希少動物だったのか?」
「シーラカンス見つけたみたいな顔しないで下さいよ。あっしの同業仲間も、軒並み高齢化が進んでますよ。皆ソリを自力で引くのが辛くなったんで、エンジン・アシスト付きのモデルに新調してもらったりとか、いろいろ対策打ってるみたいですし。」
それを聞いたサンタはポンと膝を打ち、ポケットから丸めてしわくちゃになった冊子を取り出した。
「忘れるところじゃった。わしもおまえのために高齢トナカイ仕様のソリを見繕っておるところでな。このカタログの最初のページを見てみろ。最新のエンジンアシスト技術を搭載したハイテクモデルだ。ハイブリッド車だから、地球温暖化対策にもなる。」
ルドルフはカタログを手に取りしばらく興味深げに見つめていたが、胡散臭そうな目でサンタを見上げた。
「ってか、エンジンとモーターじゃなくて、エンジンとトナカイのハイブリッドですよね。ちっともエコじゃないっすよ。これまではあっしらの肉体労働だけに頼っていて、もともとCO2排出量ゼロだったんだから。」
「まあ、そう細かいこと言うな。カプチーノ、気に入ったか?もう一杯買って来てやろうかの?」
ルドルフはミルクの泡だけになったカップを覗き込んだ。
「そういえば、去年エスプレッソマシンをプレゼントに頼んだ女の子、いましたよね。今年は何を注文したんだろう。」
サンタはスマホを取り出し、納品リストのスプレッドシートを指先でスクロールした。
「どれどれ。ああ、この子だな。・・・ふむ、これは面白い。」
サンタが差し出したスマホをルドルフは覗き込んだ。
「あれ?品物の項目が空欄っすね。コメント欄に何か書いてあるな。『今年は何もいりません。でも、サンタさんとトナカイさんにエスプレッソをごちそうしたいので、立ちよってください。』珍しいリクエストですね。行きましょうか?」
「ああ、この子はちょっと気になってたからな。ルドルフ、ぼちぼち走れそうか? あまりのんびりしてると、せっかくのエスプレッソが冷めてしまうかもしれん。」
「脚の痛みはだいぶ回復しましたよ。でも、ゆっくり走ってもいいっすかね? エスプレッソなら、適度に冷めてくれたほうがあっしには助かりますんで。」
(後編へ続く)
小説の映画化 [映画・漫画]
大ヒットした小説が鳴り物入りで映画化されることは多いが、映像化された作品が原作に匹敵する評価を得ることは稀だ。評価が割れるならまだ良い方で、大コケすることも少なくない。
 文学は文字情報だけで成り立っているので、登場人物の外見や風景など視覚情報は読者の想像力に委ねられる。先に原作を読んでしまうと読者なりの世界観が確立されてしまうので、映像化作品に違和感を感じると没入できない。例外は『ハリーポッター』のようにシリーズ初期に映画がヒットしたケースで、今やダニエル・ラドクリフのハリーやエマ・ワトソンのハーマイオニーを思い浮かべずに小説版を読むほうが難しい。
文学は文字情報だけで成り立っているので、登場人物の外見や風景など視覚情報は読者の想像力に委ねられる。先に原作を読んでしまうと読者なりの世界観が確立されてしまうので、映像化作品に違和感を感じると没入できない。例外は『ハリーポッター』のようにシリーズ初期に映画がヒットしたケースで、今やダニエル・ラドクリフのハリーやエマ・ワトソンのハーマイオニーを思い浮かべずに小説版を読むほうが難しい。
キューブリック監督の『シャイニング』を原作者スティーブヴン・キングが「エンジンを積んでいないキャデラックのようだ」と酷評したのはよく知られた話である。映像は壮麗だが物語の推進力が根本的に欠けている、と言うわけだ。『シャイニング』に関しては監督と原作者の美学が違いすぎるわけで必ずしも良し悪しでは整理できないが、一般にキングのホラー作品の映画化は原作の魅力にはるか及ばない。もともとキングのホラーはハロウィン的なB級テイストが基本なので、そのまま映像化するとチープに見えるのはむしろ必然である。
スティーヴン・キングを初めて読む人は、ホラー要素の薄い作品から入った方がいい。その方が、キング本来の魅力である物語の圧倒的な面白さと人物造形のリアリティ、そして読後感の深い余韻に没入しやすい。キングには『デッドゾーン』『スタンドバイミー』『ショーシャンクの空に』『グリーンマイル』といった非ホラーの名作がいくつもある。邪悪なモンスターが登場しないおかげでキング本来の文学的魅力が輝いているためか、各々映画版も高く評価されている傑作ばかりだ。彼のホラー作品の映像化で成功した数少ない例は『ミザリー』だが、この物語は実質的に登場人物二人の駆け引きで読者を引き込む密室劇で、もともと高度に文学的な題材なのである。
アンソニー・ホプキンスとエマ・トンプソンの燻し銀のごとき共演が光った『日の名残り』のように、映画としても最上級の賞賛を浴びた文学作品も存在する。とは言え、この映画はカズオ・イシグロの同名小説とは別物と考えた方がいいかもしれない。語り手の言いよどみや隠しごとが見えない真実を紡いでゆくイシグロの小説は、原理的に映像化が困難だからである。執事としての職業的な誇りと、その陰で自ら封印し続けた恋心の葛藤が、奇しくも同じ晩にクライマックスを迎え主人公の心中で混線し一体化する。イシグロが『日の名残り』に仕掛けたこの離れ業は、行間を読者の想像力に委ねる小説の中でしか体験することができない。
言葉はある意味で視覚情報より雄弁である。ディーリア・オーウェンズの小説『ザリガニの鳴くところ』は、主人公の少女が暮らす森と湿地の描写が濃密で、文面から音や匂いまでもが立ち昇るかのようだ。小説で描かれる大自然は、普段は優しく美しく、しかし時に不吉で荒々しく、人への渇望と恐れに揺れる孤独な少女の心象をなぞるように千変万化する。本作の映画版は雄大な風景の映像が堪能できる美しい一編だが、本を読んでから映画を見ると、むしろ映像表現の限界に思いが及ぶ。
原作モノの映画は、未知の文学世界に扉を開くきっかけだと思えばいい。一冊の長編が上手に編集され二時間にダイジェストされているから、手軽に要約を知る手段としてコスパがいい。一見して気に入らなければスルーすればいいし、気に入れば原作を読んでみるのもいい。私は映画の『ショーシャンクの空に』を見て小説を手に取って以来、いまも変わらぬスティーヴン・キングのファンになった。
 文学は文字情報だけで成り立っているので、登場人物の外見や風景など視覚情報は読者の想像力に委ねられる。先に原作を読んでしまうと読者なりの世界観が確立されてしまうので、映像化作品に違和感を感じると没入できない。例外は『ハリーポッター』のようにシリーズ初期に映画がヒットしたケースで、今やダニエル・ラドクリフのハリーやエマ・ワトソンのハーマイオニーを思い浮かべずに小説版を読むほうが難しい。
文学は文字情報だけで成り立っているので、登場人物の外見や風景など視覚情報は読者の想像力に委ねられる。先に原作を読んでしまうと読者なりの世界観が確立されてしまうので、映像化作品に違和感を感じると没入できない。例外は『ハリーポッター』のようにシリーズ初期に映画がヒットしたケースで、今やダニエル・ラドクリフのハリーやエマ・ワトソンのハーマイオニーを思い浮かべずに小説版を読むほうが難しい。キューブリック監督の『シャイニング』を原作者スティーブヴン・キングが「エンジンを積んでいないキャデラックのようだ」と酷評したのはよく知られた話である。映像は壮麗だが物語の推進力が根本的に欠けている、と言うわけだ。『シャイニング』に関しては監督と原作者の美学が違いすぎるわけで必ずしも良し悪しでは整理できないが、一般にキングのホラー作品の映画化は原作の魅力にはるか及ばない。もともとキングのホラーはハロウィン的なB級テイストが基本なので、そのまま映像化するとチープに見えるのはむしろ必然である。
スティーヴン・キングを初めて読む人は、ホラー要素の薄い作品から入った方がいい。その方が、キング本来の魅力である物語の圧倒的な面白さと人物造形のリアリティ、そして読後感の深い余韻に没入しやすい。キングには『デッドゾーン』『スタンドバイミー』『ショーシャンクの空に』『グリーンマイル』といった非ホラーの名作がいくつもある。邪悪なモンスターが登場しないおかげでキング本来の文学的魅力が輝いているためか、各々映画版も高く評価されている傑作ばかりだ。彼のホラー作品の映像化で成功した数少ない例は『ミザリー』だが、この物語は実質的に登場人物二人の駆け引きで読者を引き込む密室劇で、もともと高度に文学的な題材なのである。
アンソニー・ホプキンスとエマ・トンプソンの燻し銀のごとき共演が光った『日の名残り』のように、映画としても最上級の賞賛を浴びた文学作品も存在する。とは言え、この映画はカズオ・イシグロの同名小説とは別物と考えた方がいいかもしれない。語り手の言いよどみや隠しごとが見えない真実を紡いでゆくイシグロの小説は、原理的に映像化が困難だからである。執事としての職業的な誇りと、その陰で自ら封印し続けた恋心の葛藤が、奇しくも同じ晩にクライマックスを迎え主人公の心中で混線し一体化する。イシグロが『日の名残り』に仕掛けたこの離れ業は、行間を読者の想像力に委ねる小説の中でしか体験することができない。
言葉はある意味で視覚情報より雄弁である。ディーリア・オーウェンズの小説『ザリガニの鳴くところ』は、主人公の少女が暮らす森と湿地の描写が濃密で、文面から音や匂いまでもが立ち昇るかのようだ。小説で描かれる大自然は、普段は優しく美しく、しかし時に不吉で荒々しく、人への渇望と恐れに揺れる孤独な少女の心象をなぞるように千変万化する。本作の映画版は雄大な風景の映像が堪能できる美しい一編だが、本を読んでから映画を見ると、むしろ映像表現の限界に思いが及ぶ。
原作モノの映画は、未知の文学世界に扉を開くきっかけだと思えばいい。一冊の長編が上手に編集され二時間にダイジェストされているから、手軽に要約を知る手段としてコスパがいい。一見して気に入らなければスルーすればいいし、気に入れば原作を読んでみるのもいい。私は映画の『ショーシャンクの空に』を見て小説を手に取って以来、いまも変わらぬスティーヴン・キングのファンになった。
悪くありませんから [社会]
 日大アメフト部の大麻問題を巡り、廃部まで取りざたされている。連帯責任を取らされる学生が可哀想、という街の声を聞きながら、ふと山一證券の社長会見を思い出した。1997年秋、当時の野澤社長が山一の自主廃業を発表する会見の中で「私らが悪いんであって、社員は悪くありませんから!」と涙したアレである。
日大アメフト部の大麻問題を巡り、廃部まで取りざたされている。連帯責任を取らされる学生が可哀想、という街の声を聞きながら、ふと山一證券の社長会見を思い出した。1997年秋、当時の野澤社長が山一の自主廃業を発表する会見の中で「私らが悪いんであって、社員は悪くありませんから!」と涙したアレである。違法薬物だけならただちに廃部の話が持ち上がることもなかっただろうが、危険タックル問題で組織のあり方を問われた経緯があるだけに、相変わらずの隠蔽体質にもはや弁解の余地なしと批判されている。違法薬物に手を出したのは当該学生個人の犯罪だが、それを把握した大学側が情報をなかなか表に出さなかったのは組織が抱える問題である。社員は悪くなくとも経営陣がダメなら会社が持たないのと同じで、仮に大半の学生が悪くなくても大学運営がグダグダであれば廃部という話が出るのも不思議ではない。
学生に連帯責任を負わせるのはおかしいから廃部に反対という議論は、部員の心情を慮れば共感したくなるものの、問題の本質はそこではない。アメフト部は組織としては日大に属し、学生は大学運営に関与しない。学生は部の存続問題に何ら(連帯)責任を問われる筋合いはないが、廃部という経営判断を阻止できる立場にもない。山一の時は、社員が気の毒だから廃業はおかしいという問題提起は(少なくとも社会の側からは)なかった。それと同じで、学生が不憫だから廃部を止めろという理屈も組織論としては成立しない。
山一證券社長の「社員は悪くありませんから」発言は、会見を見た当時は何じゃこりゃと思ったが、少なくとも社長自ら上層部の非を認め一般社員をかばおうとしたわけである。日大執行部が会見で泣き出すカオスを見たいわけではないが、廃部するにせよしないにせよ、翻弄される学生に寄り添う人間味のカケラくらいは示してもいいんじゃないかと思う。
サカバンバスピス [動物]
 4億年以上前に絶滅した古代魚が、いま静かなブームを呼んでいるらしい。その名をサカバンバスピスといい、化石が最初に発見されたボリビアのサカバンバ村に由来する。古生代オルドビス紀に生息していた無顎類の一属だそうである。
4億年以上前に絶滅した古代魚が、いま静かなブームを呼んでいるらしい。その名をサカバンバスピスといい、化石が最初に発見されたボリビアのサカバンバ村に由来する。古生代オルドビス紀に生息していた無顎類の一属だそうである。舌を噛みそうな名の古代魚が脚光を浴びた経緯がまた謎めいている。ヘルシンキ自然史博物館の片隅にひっそり展示されていたサカバンバスピスの復元模型を、古生物学を研究する大学院生がX(旧ツイッター)に上げた。すると、そのすっとぼけた愛らしいビジュアルが、なぜかフィンランドから遠く離れた日本でバズった。試しにググってみると、イラストやぬいぐるみからTシャツのプリントに至るまで、ゆるキャラ化したサカバンパンピスがそこかしこに溢れている。
ヘルシンキ自然史博物館の模型やそれをもとにした図案では、サカバンパンピスの体の終端は団扇状の尾鰭で終わっている。不完全な化石資料から再現した初期の想像図なのかもしれないが、実際にはその先に細長い尾が伸びていたようだ(参考←このサイトのイラストも絶妙な愛嬌が憎い)。胸鰭を持たない寸胴な体つきから察して、泳ぎは上手くなかったであろうと推測されている。サカバンパンピス本人にしてみれば、余計なお世話かもしれない。
無顎類という名の通り顎をもたず、サカバンパンピスの口はいつも開けっ放しであったらしい。その不器用さが、じわじわくるルックスの秘密と思われる。無顎類は現代ではその大半が絶滅してしまい、円口類に属する二類(ヌタウナギとヤツメウナギ)だけが現存している。ウナギという名が付いているが似ているのは細長い見た目だけで、いわゆる鰻とはまったく別の生物だ。円口類は脊椎動物の中でもっとも原始的な部類で、遺伝的には鰻とヤツメウナギより鰻とヒトのほうがまだ近縁だとどこかで聞いた記憶がある。
初期の人類が地球上に現れたのは、せいぜい数百万年前くらいだ。私たちは、46憶年の地球史でごく最近になって表れた新参者に過ぎない。サカバンパンピスは、想像を超える太古の昔、地球史にいっとき名を刻んだ遥か大先輩である。とぼけた顔をしているからと言って、侮ってはいけない。



