ルドルフの憂鬱(後編) [フィクション]
(前編からつづく)
「去年の大きなお家から引っ越してたんだね。注文票の住所を確かめなかったら、間違えるところじゃった。」
カップを片手にサンタが言うと、少女は目を伏せたまま答えた。
「ママが私を連れてパパのお家を出たから。ご覧のとおりちっちゃいマンションだけど、まあまあ快適かな。」
ルドルフとサンタは顔を見合せた。
「サンタさんとトナカイさん、呼びつけたりして迷惑だった? 何であたし、エスプレッソごちそうしますなんて書いちゃったんだろ。」
サンタが慌てて言葉を継いだ。
「いや、全然かまわんよ。話し相手にわざわざ呼んでくれるなんて、サンタには最高のご褒美じゃ。」
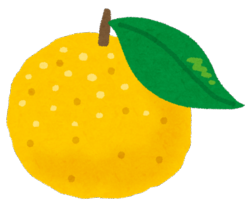 少女が顔を上げて言った。
少女が顔を上げて言った。
「ね、ゆず湯って知ってる?サンタさんたちのお国にはないかもしれないけど。」
ポカンとしているサンタの隣で、ルドルフが言った。
「お風呂に柚子を浮かべるやつかい? 日本の冬至の風習だとか聞いたことあるけど。」
「うん、トナカイさん物知りね。柚子ってなんでお湯に浮かぶんだと思う?」
サンタが首を捻った。
「それはあれかな、柚子が水より軽いからかな? アルキメデスの原理とか言われとるんじゃったか。」
「そういうのよくわからないけど、このあいだお風呂で浮かぶ柚子を見てふと思ったの。あたしは川底に沈んでいる柚子なんだって。」
サンタとルドルフは再び顔を見合せた。
「底から見上げるとね、ほかの柚子たちはみんな川面にぷかぷか浮いているのよ。陽射しを浴びて、きれいなオレンジ色に輝いて、澄んだ水の流れに身を任せてみな一緒に去っていくの。あたしはひとり、暗い川底でじっとして、それを見てるだけ。」
サンタは口を開いたが、かける言葉が見つからず、また口を閉じた。
「学校も楽しくないわけじゃないんだけどさ。でもみんな水面でコツコツぶつかり合う柚子みたいに仲良く盛り上がってるのに、あたしだけ独り別の世界にいるみたいな。」
ルドルフが言った。
「でもさ、見方を変えれば、他の子たちは流れに逆らえず漂っていくだけなのに、君だけが自分の居場所で踏ん張っているわけだ。それって、簡単なことじゃないと思うな。」
少女は少し考えてから、軽く頷いた。
「みんなが楽しそうでうらやましいって思うのと、あたしはそうじゃなくていいっていう気持ちが、ずっとぶつかってるの。でも、いつまでもこうやって川底に沈んだまま、コケまみれの大人になっていくのかなって思うと、イヤになっちゃうんだよね。」
膝に置いた手を見つめる少女に、ルドルフは優しく語りかけた。
「柚子は何で水に浮くのかってさっき聞いたよね? それはさ、浮かび上がろうとする力がもともと備わっているからだよ。今は眠っているかもしれないけど、もちろん君のなかにも。」
夜の静寂を破る冷たい北風が、つかのま窓を揺らした。
「そうかな…。」
「今はそう思えなくてもいいんだ。君がいつか水面に浮かび上がりたいと思ったときに、ちゃんと体のなかから湧いてくるから。」
膝の上でぎゅっと組まれた少女の両手が、かすかに震えた。少女はうつむいたまま、聞きとれないくらい小さな声で呟いた。
「なんだか、疲れちゃった。あたし、もう寝るね。勝手ばかり言って、ごめんなさい。でも、来てくれてほんとにありがとう。」
クリスマス配送を終えた深夜、北極圏某所の自宅でサンタは暖炉に薪をくべながら言った。
「なあルドルフ、もしかしておまえも、昔あの子みたいに感じていた頃があるのかい?」
疲労困憊で横になっていたルドルフは、火かき棒で薪をつつくサンタの背中を見やった。
「あの子? ああ、柚子の話っすか?」
そう言って何気なく伸びをしたルドルフは、前脚の痛みに顔をしかめた。
「トナカイはマイノリティなんです、絶滅危惧種ですから。暗い川底から遠い陽射しを見上げるような想いをしたのは、うちらの仲間じゃ珍しくないと思いますよ。」
静かに煌めく暖炉の炎を見つめながら、サンタは小さく溜息をついた。
「おまえとは長い付き合いだが、まだ知らないことがたくさんある。自分が人にとって何をできる人間なのか、わしはいまでも時々よくわからなくなるんじゃ。」
ルドルフはソファからゆっくり起き上がった。
「サンタ先輩ほど世の役に立っている人はなかなかいませんよ。ただせっかくそう仰るんなら、もう一つ役に立ってもらっていいっすか? あっしの前脚の湿布、取り替えて欲しいんですけど。」
(おわり)
※ 2人の前日譚はこちら。
1. 北極圏某所にて
2. 北極圏某所にて 2021
3. サンタの憂鬱(前編)
4. サンタの憂鬱(中編)
5. サンタの憂鬱(後編)
6. ルドルフの憂鬱(前編)
「去年の大きなお家から引っ越してたんだね。注文票の住所を確かめなかったら、間違えるところじゃった。」
カップを片手にサンタが言うと、少女は目を伏せたまま答えた。
「ママが私を連れてパパのお家を出たから。ご覧のとおりちっちゃいマンションだけど、まあまあ快適かな。」
ルドルフとサンタは顔を見合せた。
「サンタさんとトナカイさん、呼びつけたりして迷惑だった? 何であたし、エスプレッソごちそうしますなんて書いちゃったんだろ。」
サンタが慌てて言葉を継いだ。
「いや、全然かまわんよ。話し相手にわざわざ呼んでくれるなんて、サンタには最高のご褒美じゃ。」
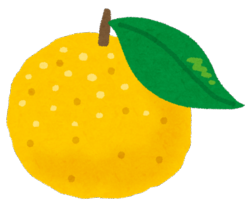 少女が顔を上げて言った。
少女が顔を上げて言った。「ね、ゆず湯って知ってる?サンタさんたちのお国にはないかもしれないけど。」
ポカンとしているサンタの隣で、ルドルフが言った。
「お風呂に柚子を浮かべるやつかい? 日本の冬至の風習だとか聞いたことあるけど。」
「うん、トナカイさん物知りね。柚子ってなんでお湯に浮かぶんだと思う?」
サンタが首を捻った。
「それはあれかな、柚子が水より軽いからかな? アルキメデスの原理とか言われとるんじゃったか。」
「そういうのよくわからないけど、このあいだお風呂で浮かぶ柚子を見てふと思ったの。あたしは川底に沈んでいる柚子なんだって。」
サンタとルドルフは再び顔を見合せた。
「底から見上げるとね、ほかの柚子たちはみんな川面にぷかぷか浮いているのよ。陽射しを浴びて、きれいなオレンジ色に輝いて、澄んだ水の流れに身を任せてみな一緒に去っていくの。あたしはひとり、暗い川底でじっとして、それを見てるだけ。」
サンタは口を開いたが、かける言葉が見つからず、また口を閉じた。
「学校も楽しくないわけじゃないんだけどさ。でもみんな水面でコツコツぶつかり合う柚子みたいに仲良く盛り上がってるのに、あたしだけ独り別の世界にいるみたいな。」
ルドルフが言った。
「でもさ、見方を変えれば、他の子たちは流れに逆らえず漂っていくだけなのに、君だけが自分の居場所で踏ん張っているわけだ。それって、簡単なことじゃないと思うな。」
少女は少し考えてから、軽く頷いた。
「みんなが楽しそうでうらやましいって思うのと、あたしはそうじゃなくていいっていう気持ちが、ずっとぶつかってるの。でも、いつまでもこうやって川底に沈んだまま、コケまみれの大人になっていくのかなって思うと、イヤになっちゃうんだよね。」
膝に置いた手を見つめる少女に、ルドルフは優しく語りかけた。
「柚子は何で水に浮くのかってさっき聞いたよね? それはさ、浮かび上がろうとする力がもともと備わっているからだよ。今は眠っているかもしれないけど、もちろん君のなかにも。」
夜の静寂を破る冷たい北風が、つかのま窓を揺らした。
「そうかな…。」
「今はそう思えなくてもいいんだ。君がいつか水面に浮かび上がりたいと思ったときに、ちゃんと体のなかから湧いてくるから。」
膝の上でぎゅっと組まれた少女の両手が、かすかに震えた。少女はうつむいたまま、聞きとれないくらい小さな声で呟いた。
「なんだか、疲れちゃった。あたし、もう寝るね。勝手ばかり言って、ごめんなさい。でも、来てくれてほんとにありがとう。」
クリスマス配送を終えた深夜、北極圏某所の自宅でサンタは暖炉に薪をくべながら言った。
「なあルドルフ、もしかしておまえも、昔あの子みたいに感じていた頃があるのかい?」
疲労困憊で横になっていたルドルフは、火かき棒で薪をつつくサンタの背中を見やった。
「あの子? ああ、柚子の話っすか?」
そう言って何気なく伸びをしたルドルフは、前脚の痛みに顔をしかめた。
「トナカイはマイノリティなんです、絶滅危惧種ですから。暗い川底から遠い陽射しを見上げるような想いをしたのは、うちらの仲間じゃ珍しくないと思いますよ。」
静かに煌めく暖炉の炎を見つめながら、サンタは小さく溜息をついた。
「おまえとは長い付き合いだが、まだ知らないことがたくさんある。自分が人にとって何をできる人間なのか、わしはいまでも時々よくわからなくなるんじゃ。」
ルドルフはソファからゆっくり起き上がった。
「サンタ先輩ほど世の役に立っている人はなかなかいませんよ。ただせっかくそう仰るんなら、もう一つ役に立ってもらっていいっすか? あっしの前脚の湿布、取り替えて欲しいんですけど。」
(おわり)
※ 2人の前日譚はこちら。
1. 北極圏某所にて
2. 北極圏某所にて 2021
3. サンタの憂鬱(前編)
4. サンタの憂鬱(中編)
5. サンタの憂鬱(後編)
6. ルドルフの憂鬱(前編)
ルドルフの憂鬱(前編) [フィクション]
 「サンタ先輩、あっしはもうダメです。老いぼれトナカイなぞ見捨てて、先輩だけで行ってください。」
「サンタ先輩、あっしはもうダメです。老いぼれトナカイなぞ見捨てて、先輩だけで行ってください。」「ルドルフ、何を大袈裟なこと言っておるのだ。しばらく休めば大丈夫だ。そもそも、お前がいなければソリを動かせないじゃないか。」
サンタはそう言いながら、道の駅のコーヒースタンドで買ったカプチーノをルドルフに差し出した。ルドルフはカップにほんの少し口をつけた途端、目を白黒させた。
「あちっ。人間って何でこんなに熱いもの飲むんすか?」
「慌てなくていい。ゆっくり飲めば体が温まる。」
カプチーノを恐るおそるすすり、ルドルフはふぅっとため息をついた。口の周りに付いたミルクの泡を見て、サンタが笑った。
「わしの髭みたいだな。一回り老けたように見えるぞ。」
ルドルフは恨めしそうにサンタを見つめた。
「実際、すっかり老けた気分ですよ。若い頃は、こんな風に配達の途中で脚にガタがくるなんてこと、なかったのに。」
サンタはルドルフの痩せた前脚をそっとさすった。
「無理をさせて悪かったな。おまえもぼちぼち引退を考えて不思議はない歳なのに。」
「一晩で配達を終えないといけないんで、無理を押すのは仕方ないっす。でも、来年以降はやりくり大変ですよ。2024年問題とか言って、この国では物流ドライバーの時間外労働が厳しく制限されるそうじゃないすか。あっしも法的には運送業の労働者ですからね。」
サンタは自分のカフェラテをぐいっと飲んだ。
「実はな、そろそろお前に楽をさせたいと思って、秋ごろから新人を数頭スカウトしようとしたんじゃ。でも求人にさっぱり応募がない。どこも人手不足なんじゃな。」
「トナカイに関して言えば、人手不足どころじゃないですよ。2016年には絶滅危惧種のレッドリスト入りしましたからね。」
サンタはルドルフをまじまじと見つめた。
「おまえ、そんな希少動物だったのか?」
「シーラカンス見つけたみたいな顔しないで下さいよ。あっしの同業仲間も、軒並み高齢化が進んでますよ。皆ソリを自力で引くのが辛くなったんで、エンジン・アシスト付きのモデルに新調してもらったりとか、いろいろ対策打ってるみたいですし。」
それを聞いたサンタはポンと膝を打ち、ポケットから丸めてしわくちゃになった冊子を取り出した。
「忘れるところじゃった。わしもおまえのために高齢トナカイ仕様のソリを見繕っておるところでな。このカタログの最初のページを見てみろ。最新のエンジンアシスト技術を搭載したハイテクモデルだ。ハイブリッド車だから、地球温暖化対策にもなる。」
ルドルフはカタログを手に取りしばらく興味深げに見つめていたが、胡散臭そうな目でサンタを見上げた。
「ってか、エンジンとモーターじゃなくて、エンジンとトナカイのハイブリッドですよね。ちっともエコじゃないっすよ。これまではあっしらの肉体労働だけに頼っていて、もともとCO2排出量ゼロだったんだから。」
「まあ、そう細かいこと言うな。カプチーノ、気に入ったか?もう一杯買って来てやろうかの?」
ルドルフはミルクの泡だけになったカップを覗き込んだ。
「そういえば、去年エスプレッソマシンをプレゼントに頼んだ女の子、いましたよね。今年は何を注文したんだろう。」
サンタはスマホを取り出し、納品リストのスプレッドシートを指先でスクロールした。
「どれどれ。ああ、この子だな。・・・ふむ、これは面白い。」
サンタが差し出したスマホをルドルフは覗き込んだ。
「あれ?品物の項目が空欄っすね。コメント欄に何か書いてあるな。『今年は何もいりません。でも、サンタさんとトナカイさんにエスプレッソをごちそうしたいので、立ちよってください。』珍しいリクエストですね。行きましょうか?」
「ああ、この子はちょっと気になってたからな。ルドルフ、ぼちぼち走れそうか? あまりのんびりしてると、せっかくのエスプレッソが冷めてしまうかもしれん。」
「脚の痛みはだいぶ回復しましたよ。でも、ゆっくり走ってもいいっすかね? エスプレッソなら、適度に冷めてくれたほうがあっしには助かりますんで。」
(後編へ続く)
サンタの憂鬱(後編) [フィクション]
(中編からつづく)(初めから読む)
 北極圏に向かう夜空をソリで駆け抜けながら、サンタがルドルフに話しかけた。
北極圏に向かう夜空をソリで駆け抜けながら、サンタがルドルフに話しかけた。
「おませでドライな子じゃったな。現代っ子って、あんなものか?わしらをコスプレ宅配業者扱いしおったぞ。」
ルドルフはしばらく黙ってソリを引いていたが、やがてボソッと呟いた。
「あの子、先輩が本物のサンタだって、ちゃんとわかってたと思いますよ。」
サンタは驚いた。
「え、どういうことじゃ?サンタなんて端から信じていない様子だったじゃないか。」
「あの子がスマホを手に取って持ち上げた時、画面が見えちゃったんですよ。一瞬でしたけど、間違いないです。」
「もったいぶらんでいい。何を見たんじゃ?」
「サンタ先輩のYouTubeチャンネルですよ。ソリで世界を巡りながら先輩が撮りためた風景動画を編集したやつ。きっと、それを見ながらぼくたち二人が来るのをずっと待っていたんです。」
サンタは言葉を失った。ルドルフが続けた。
「あの子、何も欲しいものはないって言いましたよね。たぶん、大抵のものは買い与えられて、何でも持ってるんです。でも、あの子が本当に欲しいのは、どこかで買って来られるようなものじゃないんです。ただ誰かに気持ちを満たしてもらいたいんですよ。心の底から信じられる何かが欲しいんです。」
くだらないケンカはいい加減やめてくれってこと、と少女が言い捨てたときの表情を、サンタは思い出した。口調は厳しかったが、そう言いながら瞳が悲しそうに曇るのを少女は隠し切れなかった。
「先輩のYouTube見ながら、本当に来てくれるのか不安だったはずです。でも、サンタは約束通り現れた。態度には出しませんでしたけど、本心ではあの子、ものすごく嬉しかったと思いますよ。」
二人はしばらく黙ってソリを進めた。満点の星空の下、鈴の音が静かにリズミカルな響きを奏で続ける。やがてサンタが口を開いた。
「丘の上の公園で一人座っていた時、クリスマスの配送はもう廃業しようかと半ば本気で考えておった。でもあと1、2年くらいは続けてみようかのう。歳は取ったが、当面はまだ体も動きそうじゃし。」
ルドルフが軽くため息をついた。
「お忘れかもしれませんけど、あっしもそこそこの歳ですよ。ソリを引くのは肉体労働だし、きついのはきついっす。でも、サンタ先輩がそう言うなら、とことん付き合いますよ。」
前方の地平線上に、緑白色に輝くオーロラがうっすらと浮かび上がって来た。じきに北極圏に入る。黙々とソリを引くルドルフの背中を見ながら、帰宅したらこいつをどんなふうにねぎらってやろうかとサンタは考えていた。
(おわり)
※ 2人の前日譚はこちら。
1. 北極圏某所にて
2. 北極圏某所にて 2021。
 北極圏に向かう夜空をソリで駆け抜けながら、サンタがルドルフに話しかけた。
北極圏に向かう夜空をソリで駆け抜けながら、サンタがルドルフに話しかけた。「おませでドライな子じゃったな。現代っ子って、あんなものか?わしらをコスプレ宅配業者扱いしおったぞ。」
ルドルフはしばらく黙ってソリを引いていたが、やがてボソッと呟いた。
「あの子、先輩が本物のサンタだって、ちゃんとわかってたと思いますよ。」
サンタは驚いた。
「え、どういうことじゃ?サンタなんて端から信じていない様子だったじゃないか。」
「あの子がスマホを手に取って持ち上げた時、画面が見えちゃったんですよ。一瞬でしたけど、間違いないです。」
「もったいぶらんでいい。何を見たんじゃ?」
「サンタ先輩のYouTubeチャンネルですよ。ソリで世界を巡りながら先輩が撮りためた風景動画を編集したやつ。きっと、それを見ながらぼくたち二人が来るのをずっと待っていたんです。」
サンタは言葉を失った。ルドルフが続けた。
「あの子、何も欲しいものはないって言いましたよね。たぶん、大抵のものは買い与えられて、何でも持ってるんです。でも、あの子が本当に欲しいのは、どこかで買って来られるようなものじゃないんです。ただ誰かに気持ちを満たしてもらいたいんですよ。心の底から信じられる何かが欲しいんです。」
くだらないケンカはいい加減やめてくれってこと、と少女が言い捨てたときの表情を、サンタは思い出した。口調は厳しかったが、そう言いながら瞳が悲しそうに曇るのを少女は隠し切れなかった。
「先輩のYouTube見ながら、本当に来てくれるのか不安だったはずです。でも、サンタは約束通り現れた。態度には出しませんでしたけど、本心ではあの子、ものすごく嬉しかったと思いますよ。」
二人はしばらく黙ってソリを進めた。満点の星空の下、鈴の音が静かにリズミカルな響きを奏で続ける。やがてサンタが口を開いた。
「丘の上の公園で一人座っていた時、クリスマスの配送はもう廃業しようかと半ば本気で考えておった。でもあと1、2年くらいは続けてみようかのう。歳は取ったが、当面はまだ体も動きそうじゃし。」
ルドルフが軽くため息をついた。
「お忘れかもしれませんけど、あっしもそこそこの歳ですよ。ソリを引くのは肉体労働だし、きついのはきついっす。でも、サンタ先輩がそう言うなら、とことん付き合いますよ。」
前方の地平線上に、緑白色に輝くオーロラがうっすらと浮かび上がって来た。じきに北極圏に入る。黙々とソリを引くルドルフの背中を見ながら、帰宅したらこいつをどんなふうにねぎらってやろうかとサンタは考えていた。
(おわり)
※ 2人の前日譚はこちら。
1. 北極圏某所にて
2. 北極圏某所にて 2021。
サンタの憂鬱(中編) [フィクション]
(前編からつづく)
ルドルフがスマホのGoogleマップを見つめて言った。
「今年最後の配達先、ここです。ずいぶん大きな家っすね。」
サンタは魅せられたように豪邸を見上げた。
「まちがいなくセコムが入っておるな。まさか、おまえまたわしにドッキリを仕掛けるつもりじゃ・・・」
「いえいえいえ。今回は前もってセキュリティ切ってもらうようにちゃんと頼んでありますよ。」
「子供部屋の窓はどこじゃ?これだけ大きな家だと見当もつかんな。」
そのとき3階の窓がガラリと開いて、少女が顔を出した。
「あら、サンタさん。あなた本物?」
サンタは少女を見上げた。
「もちろんじゃ。偽物に見えるかい?」
「知らない人を家に入れるなってパパとママが言うから、念のため確かめたの。どうぞ入って、サンタさんとトナカイさん。」
少女の部屋に入ると、ルドルフがサンタにこっそり囁いた。
「ほら、ちゃんとサンタを信じている子もまだいるじゃないですか。」
少女はそれを聞き逃さなかった。
「まさか、そんな子供じゃないわよ。あなた方、宅配便の人でしょ。こんなにちゃんとコスプレしてくると思ってなかったから、ちょっとびっくりしたけど。」
サンタは面食らった。
「コスプレって・・・。正真正銘のサンタスーツなんじゃがの。」
少女がクスクス笑った。
「良かった、プロ意識高めの人たちで。ちょっと重たくてかさばる物をたのんじゃったから、本当に届けてくれるか気になってたの。」
サンタは白い大袋から大きな箱を両手で引っ張り出した。
「メリークリスマス!ふぅ、確かに重たいな。いったい何をお願いしたんだい?」
「エスプレッソマシン。流行りの上位機種なの。」

少女がそう言うと、ルドルフが思わず口を挟んだ。
「お嬢ちゃん、エスプレッソ好きなの?好みが渋いな。」
少女はケラケラと笑った。
「お嬢ちゃんなんて呼ばれたの、初めて。私が飲むわけじゃないの。これを頼んだのはね、ママが淹れたコーヒーをパパがいつもマズいとかケチつけて、朝から二人で言い合いばかりしてるから。全自動のエスプレッソマシンならカートリッジ入れてスイッチ押すだけだから、旨いも不味いもないでしょ。」
それを聞いてサンタが感心した。
「なんて優しい子なんだ。自分の欲しいプレゼントより、ご両親のことを気に掛けているなんて。」
すると少女が口をとがらせた。
「別に、パパとママのためじゃないよ。ふたりが険悪になるとわたしもとばっちりを食らうから、くだらないケンカはいい加減やめてくれってこと。そもそもわたし、別に欲しいものなんてないし。」
少女を見つめ絶句するサンタに代わって、ルドルフが訊いた。
「欲しいもの、本当にないの?スマホとかさ、今の子だったら絶対持ちたいでしょ。」
「スマホなら、とっくに持ってる。ほら。」
少女は机の上に載っていたスマホをひょいと取り上げ、黄門様の印籠のように掲げた。が、何を思い出したか急に顔を赤らめ、慌ててスマホを伏せて机上に戻した。
「とにかく今日はありがとう。重たいもの頼んじゃってごめんなさい。」
なぜか急にしおらしくなった少女に、サンタは言った。
「いやなに。じゃ、素敵なクリスマスを!さ、ルドルフ行くぞ。」
窓から外に出ると、サンタは空っぽになった大袋を小脇に抱えてソリに乗り込んだ。夜空を駆けて行くサンタとルドルフの姿はみるみる小さくなり、やがて微かな点になって消えた。二人が見えなくなってずいぶん経ってから、子供部屋の窓が静かに閉まった。
(後編へつづく)
ルドルフがスマホのGoogleマップを見つめて言った。
「今年最後の配達先、ここです。ずいぶん大きな家っすね。」
サンタは魅せられたように豪邸を見上げた。
「まちがいなくセコムが入っておるな。まさか、おまえまたわしにドッキリを仕掛けるつもりじゃ・・・」
「いえいえいえ。今回は前もってセキュリティ切ってもらうようにちゃんと頼んでありますよ。」
「子供部屋の窓はどこじゃ?これだけ大きな家だと見当もつかんな。」
そのとき3階の窓がガラリと開いて、少女が顔を出した。
「あら、サンタさん。あなた本物?」
サンタは少女を見上げた。
「もちろんじゃ。偽物に見えるかい?」
「知らない人を家に入れるなってパパとママが言うから、念のため確かめたの。どうぞ入って、サンタさんとトナカイさん。」
少女の部屋に入ると、ルドルフがサンタにこっそり囁いた。
「ほら、ちゃんとサンタを信じている子もまだいるじゃないですか。」
少女はそれを聞き逃さなかった。
「まさか、そんな子供じゃないわよ。あなた方、宅配便の人でしょ。こんなにちゃんとコスプレしてくると思ってなかったから、ちょっとびっくりしたけど。」
サンタは面食らった。
「コスプレって・・・。正真正銘のサンタスーツなんじゃがの。」
少女がクスクス笑った。
「良かった、プロ意識高めの人たちで。ちょっと重たくてかさばる物をたのんじゃったから、本当に届けてくれるか気になってたの。」
サンタは白い大袋から大きな箱を両手で引っ張り出した。
「メリークリスマス!ふぅ、確かに重たいな。いったい何をお願いしたんだい?」
「エスプレッソマシン。流行りの上位機種なの。」

少女がそう言うと、ルドルフが思わず口を挟んだ。
「お嬢ちゃん、エスプレッソ好きなの?好みが渋いな。」
少女はケラケラと笑った。
「お嬢ちゃんなんて呼ばれたの、初めて。私が飲むわけじゃないの。これを頼んだのはね、ママが淹れたコーヒーをパパがいつもマズいとかケチつけて、朝から二人で言い合いばかりしてるから。全自動のエスプレッソマシンならカートリッジ入れてスイッチ押すだけだから、旨いも不味いもないでしょ。」
それを聞いてサンタが感心した。
「なんて優しい子なんだ。自分の欲しいプレゼントより、ご両親のことを気に掛けているなんて。」
すると少女が口をとがらせた。
「別に、パパとママのためじゃないよ。ふたりが険悪になるとわたしもとばっちりを食らうから、くだらないケンカはいい加減やめてくれってこと。そもそもわたし、別に欲しいものなんてないし。」
少女を見つめ絶句するサンタに代わって、ルドルフが訊いた。
「欲しいもの、本当にないの?スマホとかさ、今の子だったら絶対持ちたいでしょ。」
「スマホなら、とっくに持ってる。ほら。」
少女は机の上に載っていたスマホをひょいと取り上げ、黄門様の印籠のように掲げた。が、何を思い出したか急に顔を赤らめ、慌ててスマホを伏せて机上に戻した。
「とにかく今日はありがとう。重たいもの頼んじゃってごめんなさい。」
なぜか急にしおらしくなった少女に、サンタは言った。
「いやなに。じゃ、素敵なクリスマスを!さ、ルドルフ行くぞ。」
窓から外に出ると、サンタは空っぽになった大袋を小脇に抱えてソリに乗り込んだ。夜空を駆けて行くサンタとルドルフの姿はみるみる小さくなり、やがて微かな点になって消えた。二人が見えなくなってずいぶん経ってから、子供部屋の窓が静かに閉まった。
(後編へつづく)
サンタの憂鬱(前編) [フィクション]
「先輩、こんなところにいたんですか。ホント探しましたよ。」
丘のてっぺんまで夜道を登りきったルドルフが、息を整えながらサンタに話しかけた。ポツンと佇む街灯の明かりの下で、ベンチに座るサンタの背中がかすかに揺れた。
「サンタ先輩?」
ルドルフがベンチに駆け寄った。丘から望む街の夜景が、真冬の澄んだ大気ごしに冷たく煌めいている。
サンタがうつむいたままポツリと答えた。
「ルドルフ、探させてすまなかった。少しのあいだ、どうしても一人になりたくてな。」
「どうしたんすか、急に?道の駅でトイレから出たら先輩の姿が見えなくて、いつまで待っても戻って来ないから、心配しましたよ。」
ルドルフはそう言いながら、サンタの隣に腰を下ろした。
 サンタはそっとため息をついた。
サンタはそっとため息をついた。
「パンデミックの出口が見えてきて、ようやくクリスマス配送が再開できるようになったのはいいが、コロナ前と比べて受注が激減したじゃないか。3年ぶりに張り切っておったのに、なんだか淋しいというか、無性に空しい気分になってな。」
ルドルフは驚いた顔でサンタを見つめた。
「それは先輩が望んだことじゃなかったんですか?コロナで籠っていた2回のクリスマスはすっかりアマゾンに頼って、おかげでサンタ先輩も時間にゆとりができたじゃないですか。今や、いっぱしのユーチューバーだし。」
「お前の言うとおり、確かにわしが自分で仕込んだことじゃ。」
サンタは顔を上げルドルフを見つめた。
「でもな、わし程度のユーチューバーなんて世間に掃いて捨てるほどおる。しかしサンタ配送業のライセンスを持っている者は、世界に十数人しかいない。わしはやはりサンタでいることだけが取り柄なんじゃよ。」
世間的にはサンタは一人ってことになってますけどね、とルドルフは言いかけて、止めた。
「なあ、ルドルフ。コロナ禍に見舞われた3年弱の間に、どれだけ多くの店が街から消えたじゃろうか?生計に困って自ら命を絶った個人経営者もいる。」
ルドルフは黙って頷いた。
「でもな、絶望の理由は、単なる経済的な困窮だけじゃなかったはずだ。」
街灯の明かりが一瞬心許なく揺らいだ。サンタは頭上を見上げた。
「足繫く訪れていた客がパタリと途絶え、ガランとした店内で来ない客を待つ店主の気持ちが、今わしにはわかる気がするんじゃ。自分は社会から必要とされていない、真っ先に切り捨てられあっさり忘れ去られる、そんな風に感じていたんじゃないだろうか?何年もかけてコツコツと築いてきた仕事が、他人にとっては何の価値もないと宣告されたみたいに。」
ルドルフは再び黙って頷いた。
「自分で言うのもなんだが、サンタは世界中の子供たちがクリスマス前に待ち焦がれる大スターだとずっと思っておった。でも、独りよがりの思い込みに過ぎなかったのかもしれんな。幼い子供たちすら、クリスマスプレゼントがネット通販で届くのが当たり前になってしまったんだとしたら、サンタの出番はもうどこにもない。」
ルドルフがおずおずと口を開いた。
「そんなことはないですよ。今でも、えっと、子供たちはみんなサンタさん大好きだと思いますよ。」
「ルドルフ、お前はいい奴だが、相変わらずウソが下手じゃのう。」
「嘘じゃないですよ。今も世界の子供たちから、たくさん手紙が届くじゃないですか。」
「年に一度しか働かなくていいからサンタになりたいです、ってやつか?」
そう言ってサンタが笑った。ルドルフもぎこちなく笑顔になった。
「さて、お前に愚痴ったおかげで、少し気が晴れた。最後の配送品がまだ一つが残っておるから、さっさと片付けてしまおう。ほら行くぞ。」
「ほら行くぞって、サンタ先輩がバックレてたんじゃないですか。でもいいですよ、ソリは丘の下のパーキングに移動してあります。言っときますけど、駐車料金は先輩持ちですからね。」
(中編へつづく)
丘のてっぺんまで夜道を登りきったルドルフが、息を整えながらサンタに話しかけた。ポツンと佇む街灯の明かりの下で、ベンチに座るサンタの背中がかすかに揺れた。
「サンタ先輩?」
ルドルフがベンチに駆け寄った。丘から望む街の夜景が、真冬の澄んだ大気ごしに冷たく煌めいている。
サンタがうつむいたままポツリと答えた。
「ルドルフ、探させてすまなかった。少しのあいだ、どうしても一人になりたくてな。」
「どうしたんすか、急に?道の駅でトイレから出たら先輩の姿が見えなくて、いつまで待っても戻って来ないから、心配しましたよ。」
ルドルフはそう言いながら、サンタの隣に腰を下ろした。
 サンタはそっとため息をついた。
サンタはそっとため息をついた。「パンデミックの出口が見えてきて、ようやくクリスマス配送が再開できるようになったのはいいが、コロナ前と比べて受注が激減したじゃないか。3年ぶりに張り切っておったのに、なんだか淋しいというか、無性に空しい気分になってな。」
ルドルフは驚いた顔でサンタを見つめた。
「それは先輩が望んだことじゃなかったんですか?コロナで籠っていた2回のクリスマスはすっかりアマゾンに頼って、おかげでサンタ先輩も時間にゆとりができたじゃないですか。今や、いっぱしのユーチューバーだし。」
「お前の言うとおり、確かにわしが自分で仕込んだことじゃ。」
サンタは顔を上げルドルフを見つめた。
「でもな、わし程度のユーチューバーなんて世間に掃いて捨てるほどおる。しかしサンタ配送業のライセンスを持っている者は、世界に十数人しかいない。わしはやはりサンタでいることだけが取り柄なんじゃよ。」
世間的にはサンタは一人ってことになってますけどね、とルドルフは言いかけて、止めた。
「なあ、ルドルフ。コロナ禍に見舞われた3年弱の間に、どれだけ多くの店が街から消えたじゃろうか?生計に困って自ら命を絶った個人経営者もいる。」
ルドルフは黙って頷いた。
「でもな、絶望の理由は、単なる経済的な困窮だけじゃなかったはずだ。」
街灯の明かりが一瞬心許なく揺らいだ。サンタは頭上を見上げた。
「足繫く訪れていた客がパタリと途絶え、ガランとした店内で来ない客を待つ店主の気持ちが、今わしにはわかる気がするんじゃ。自分は社会から必要とされていない、真っ先に切り捨てられあっさり忘れ去られる、そんな風に感じていたんじゃないだろうか?何年もかけてコツコツと築いてきた仕事が、他人にとっては何の価値もないと宣告されたみたいに。」
ルドルフは再び黙って頷いた。
「自分で言うのもなんだが、サンタは世界中の子供たちがクリスマス前に待ち焦がれる大スターだとずっと思っておった。でも、独りよがりの思い込みに過ぎなかったのかもしれんな。幼い子供たちすら、クリスマスプレゼントがネット通販で届くのが当たり前になってしまったんだとしたら、サンタの出番はもうどこにもない。」
ルドルフがおずおずと口を開いた。
「そんなことはないですよ。今でも、えっと、子供たちはみんなサンタさん大好きだと思いますよ。」
「ルドルフ、お前はいい奴だが、相変わらずウソが下手じゃのう。」
「嘘じゃないですよ。今も世界の子供たちから、たくさん手紙が届くじゃないですか。」
「年に一度しか働かなくていいからサンタになりたいです、ってやつか?」
そう言ってサンタが笑った。ルドルフもぎこちなく笑顔になった。
「さて、お前に愚痴ったおかげで、少し気が晴れた。最後の配送品がまだ一つが残っておるから、さっさと片付けてしまおう。ほら行くぞ。」
「ほら行くぞって、サンタ先輩がバックレてたんじゃないですか。でもいいですよ、ソリは丘の下のパーキングに移動してあります。言っときますけど、駐車料金は先輩持ちですからね。」
(中編へつづく)
北極圏某所にて 2021 [フィクション]
「先輩、結局やっぱりクリスマスはステイホームになっちゃいましたね。今年は配達行けるかとちょっと期待しましたけど、オミクロンのやつのせいでどこの国にも入りづらくなりましたし。」
「ああ、去年と同じでクリスマスプレゼントはAmazonに任せた。ま、いいさ。わしのYouTubeチャンネルは視聴数がぐんぐん伸びてるし、プロユーチューバーへの道は近い。昔から配達のかたわら動画を撮りためた甲斐があったな。」
「サンタ先輩の動画、フライトシミュレーターみたいでかっこいいって声が多いっすね。ソリで飛んでいる間、スマホのカメラつけっぱなしだったんですか?」
「というか、電源を切るのをつい忘れてな。おかげで北極海上空でスマホがバッテリー切れして、チャージする術もなく困ったことが何度もあった。」
「あ、飛行中に突然画面が真っ暗になった動画ありましたよね。サンタ墜落か、ってコメ欄が大騒ぎになってましたよ。」
「そうじゃったな。それにしても、今年の春に公開し始めてしばらくはほとんど反応がなかったのが、8月くらいから急に『いいね』が付き始めてな。世界的にコロナの波が揺り戻していたから、旅行系のチャンネルでステイホームのつれづれを紛らす人が多かったんじゃろうか。」
「それで暇つぶしにコメ欄を丁寧に読んでおったんだが、『あのお茶目なサンタさんだ!』とか『チャンネルドルフからここに来ました!』とか不可解なコメントが次々に出てきてな。おまえ、何のことかわかるか?」
「え?いや、さぁ、何でしょうね。」
「チャンネルドルフってのを検索してみたら、こんなのが出てきたぞ。これ、お前のチャンネルか?」
「え、えっと、ルドルフっていう名のトナカイ、他にもいるんじゃないかな。はは。」
「赤の他人が撮った動画だったら、なぜわしが登場しておるんじゃ?煙突のない家だったから窓からそっと部屋に入ってプレゼントを届けようとしたんだが、セコムの警報機が鳴った一部始終がばっちり写っておる。『サンタ、セコムに追われる。草』みたいなコメントがごろごろ並んで、視聴数は1万を超えてたぞ。」
「ええまあ、あれはかなりヒットした回で・・・」
「それだけじゃないぞ。スピード違反で切符来られそうになったときの動画も、かなりアクセス数稼いだじゃろうが。恥さらしじゃないか。パトカーの前で調子こいて暴走したのはお前だぞ、ルドルフ。」
「いやいや、あれは同情的なコメばかりでしたよ。『サンタさん一晩で全部届けないといけないから、そりゃ焦るわ。お巡りさん許してあげて!』みたいな。」
「白状したようだから、まあ許してやるか。いったいいつからチャンネルドルフなんて立ち上げておったんじゃ?」
「えっと、東京オリンピック見ながら動画編集してたから、7月終わりから8月にかけてですかね。」
「8月?もしかして、サンタチャンネルのアクセスが急増したのは、おまえの動画からリンクで飛んできた輩ばかりだったのか?サンタチャンネルの人気が急浮上したわけじゃなかったのか・・・。」
「先輩、そんなにがっかりしないで下さい。サンタチャンネル、すごい好評ですよ。チャンネルドルフみたいにドッキリ系じゃなくて、正統派の旅番組としてちゃんと成立してますから。」
「今日はやたら気を遣うんだな。まあ、お前のおかげでファンがたくさん付いたと思えばむしろ感謝だな。ん、ちょっと待て。いまドッキリ系って言ったか?」
「あ・・・。いや別に、ぼく言いました、そんなこと?」
「イブの晩にサンタがプレゼント持って来るのはみんな分かってるから、大抵セコムは切っておくはずなのに、あちこちで警報が鳴って何かおかしいと思ってたんじゃ。スピード違反のときも、確かお前が・・・」
「いやいやいや、誤解です誤解。それにいいじゃないですか、先輩お茶目キャラで人気も出たし、結果オーライで・・・」
「ん?そのお前のスマホ、なんでレンズがこっちに向いておるんじゃ?まさか、いまそれで撮っているんじゃ・・・おいおい、そんな勢いで逃げ出すなよ。別に怒っておらん。長い付き合いだから、お前のやりそうなことはだいたい見当がついておる。このチャンネルドルフにしたって可愛いものじゃ。ん?新しい動画アップしたのか?どれどれ・・・。何だこれは!?ルドルフ、おい!戻ってこい!!」
※ 2人の前日譚はこちら。
スーパー五輪ブラザーズ [フィクション]
 20XX年、東京で再びオリンピック・パラリンピックが開催されることとなった。しかし折り悪く、毒キノコによる疫病が世界に蔓延し、オリンピックの開催形態に大幅な見直しを余儀なくされる。侃々諤々の議論の末ようやくその方針がまとまり、IOC会長と日本の首相による共同会見が催される運びとなった。以下はその全容である。
20XX年、東京で再びオリンピック・パラリンピックが開催されることとなった。しかし折り悪く、毒キノコによる疫病が世界に蔓延し、オリンピックの開催形態に大幅な見直しを余儀なくされる。侃々諤々の議論の末ようやくその方針がまとまり、IOC会長と日本の首相による共同会見が催される運びとなった。以下はその全容である。
司会「みなさま、お集まり下さりありがとうございます。では、まずIOCバッカ会長からオリンピックの新たな形式についてご発表いただきます。」
IOC「このようなキノコ禍の状況ですので、大会の大幅な簡素化が必要と決断しました。そこで、思い切ってオリンピックを一種目だけに限定することとしました。」
(会場ざわつく)
司会「一種目といいますと?人気種目を残すなら、100m走か何か?」
IOC「いえいえ、公平を期してすべての種目を取りやめ、全くの新種目を設けます。ルールはとても簡単ですよ。選手には、拳を頭上にまっすぐ突き上げ、その状態でジャンプしてもらいます。」
司会「・・・。それだけですか?」
IOC「いえ、箱が空中に浮いていまして、選手が拳で箱を叩くと金貨が飛び出す仕掛けなんです。コインを一番たくさん叩き出した人が、金メダルです。どうです?盛り上がるでしょう。」
司会「それなんだか見覚えが。もしかして、土管に潜り込んだり、甲羅を蹴飛ばしたりするヤツですか?」
IOC「ええ、障害物競走も検討しました。が、舞台装置が大変なので採用しませんでした。」
司会「叩き出したコインは、選手への賞金になる仕組みなんですね?」
IOC「まさか。コインはもちろん、IOCが全額回収します。つまるところ、オリンピックはカネを産み出すことが価値なのです、私どもにとっては。」
司会「はあ。では、会場から質問をお受けします。はい、どうぞ。」
記者「キノコ禍再拡大の懸念から、東京は再び緊急事態宣言下にあります。このような状況下でのオリンピック開催を、どうお考えですか?」
IOC「私たちは緊急開会宣言と題して、開会式に臨席するIOCファミリーで乾杯する企画を温めてますよ。」
記者「スカ総理はいかがお考えでしょうか?国内のワクチン接種率はまだ10%台の状況ですが。」
(筆者注:記者が言及したのは、毒キノコを体内でスーパーキノコに変質させ無敵の抗体を作る、新しいワクチンのことである。)
首相「私は、安心安全のオリンピック開催に向け、全力を尽くしてまいります。」
司会「では次の方、質問どうぞ。」
記者「首都圏の無観客開催を受け、想定されていたチケット収入は大幅な減収が予想されます。赤字の穴埋めに、多額の税金が投入されるのでしょうか?」
IOC「個人的には、皆さんにはご自宅からご覧いただいた方がスポンサーの放送局は喜びますので、無観客のほうが良いと初めから思っていました。」
記者「えっと、総理に伺ったのですが。」
首相「私ですか?とにかく、安心安全の大会にしてまいります。」
司会「では、次の方。」
記者「IOCやスポンサーは無観客でも収益が保証されるかも知れませんが、キノコ禍のせいで開催国・開催都市は持ち出しばかりで大損ですよね。このようなオリンピックのあり方について、どのようにお考えですか?」
IOC「オリンピックはIOCのビジネスですから、我々がガッツリ儲かるよう契約するのは当然です。開催都市を脅したりはしませんよ。選んであげた途端みんな有頂天になって、契約に署名するときは子犬のように聞きわけが良いですからね。今回は想定外のキノコ禍のため、いつもより開催都市の弱みが目立ってしまいましたけど、これまで多額の出費に苦しんだ都市は東京だけではありませんよ。」
記者「何の気休めにもなりませんが。」
IOC「ははは。でも、東京には感謝していますよ。前回のオリンピック閉会式でスカ首相の前任者がゲームのキャラに扮して登場してくれたおかげで、今回新種目のアイディアが生まれたわけですから。」
司会「スカ首相、いかがですか?」
首相「ですから、私としては先程申しましたとおり、安心安全の大会に尽力してまいります。」
司会「では、最後に一言お願いします。」
IOC「選手の皆さん、ご健闘をお祈りします。皆さんのおかげで、私は老後も良い暮らしができそうです。IOC幹部と大口スポンサーを代表して、深くお礼申し上げます。」
首相「私としましては、安全安心の・・・えと、安心安全か。安全安心?安心安全?あれ、どっちだったっけ?」
司会「ありがとうございました。では皆さん、どうかステイホームでテレビをウォッチしながらアスリートたちにエールをシャウトしオリンピックをエンジョイして下さい。司会の湖池ユリ子でした。」
火星某所にて [フィクション]

「こんにちは。君はだれ?」
「うわっ、びっくりした。こんなところで人に出会うと思ってなかった。」
「そう?ぼくはあちこちの星で変テコな人たちに会ってきたよ。君は面白い姿をしてるね。」
「火星探査機なんて、だいたいこんな見てくれだよ。あちこちの星って、君はどこから来たんだい?こんな辺境で、ずいぶんオシャレな格好して。」
「ぼくは地球から故郷の星に帰る途中さ。ヘビに噛まれた足が腫れて痛くてさ、ちょっとここで一休みしようと思って。君はここに不時着したのかい?」
「不時着?いやいや、現地調査でわざわざ来たのさ。迷子で困ってるように見えたかい?」
「いや、アフリカの砂漠で壊れた飛行機に八つ当たりする人に会ったばかりでね。ここも似たような景色だし・・・。調査って、何を探してるの?」
「土や石ころを集めているんだよ。ずっと昔この辺りに海や川があって、小さな生き物が棲んでたかもって話があってさ。その痕跡を見つけたいんだ。」
「へえ。でも、昔ってことは今は誰も住んでいないんだね。君はひとりぼっちなの?」
「まあね、仕事だからさ。でも、こうやって集めたものを地球に持ち帰るために、そのうち仲間が回収に来るよ。5年後くらいかな。」
「5年後?さっき誰か降りてくるの見たけど。」
「ああ、それは中国の探査機だね。そいつは、別に知り合いじゃないよ。」
「ははぁ、ケンカしたんだね?」
「え?ケンカっていうか・・・。」
「いやいや、わかるよ。ぼくも故郷でちょっとモメてさ。大切にしていたバラの花があるんだけど、彼女いつもツンとして、要求ばっかりで。なんか居づらくなって、飛び出してきちゃったんだ。」
「花とケンカしたの?ま、モメてると言えば、確かにアメリカと中国はいま経済や安全保障で緊張が高まってるけど。」
「君、急に大人みたいな口のきき方するね。あのね、ぼくはいま後悔してるんだ、バラの本当の気持ちに気付いてあげられなくて、独り置いてきぼりにしてしまったから。君のチューゴクだって、ツンとしてても本心はわからないよ。」
「話が見えないんだけど・・・。ま、どちらにせよ科学と政治は別だから、持ち帰ったサンプルは国を問わず世界の研究者が分析するんじゃないかな。」
「難しくてわからないよ。ブンセキって何だい?」
「見た目は単なる石ころでも、目に見えないくらい小さな生き物の痕跡を、あの手この手で探し出すってことさ。」
「ああ!それならわかるよ。一番だいじなものは目に見えないって、キツネが教えてくれたし。」
「キツネ?君の言うことって、ほんと突拍子ないね。さて、そろそろ仕事に戻らないと。じゃあ・・・」
「你好!」
「うわ、またびっくりした。何でみんな急に出て来るの。」
「我推測 星之王子様?我読了 仏蘭西的童話。」
「君、もしかして中国の探査機?」
「是!你 米国探査機?米国火星探査有長大歴史!你 大先輩。我見倣 米国的探査方式。」
「仲直りできそうで、よかったね。ぼくも故郷のバラがいっそう恋しくなったよ。じゃ、またね。」
「え?ちょっと。あ、行っちゃった・・・。えっと、君、そんなじっと見つめないでよ。わかったよ、じゃあ仕事始めようか。まずアームを伸ばして、ここの地面をそっと掘り起こして・・・」
お断り)文中の漢語はもちろん私の勝手な創作であって、文法も語彙も全く体を成していません。お許し下さい。
3月11日の花火 [フィクション]
浜を見下ろす小高い丘のてっぺんに着くと、いつものように大きく息を吸って、眼下に広がる海を見つめる。若い時分は何でもなかった短い上り坂なのに、今では慎重に登らないと息が切れる。かつて所狭しと軒を連ねていた街の面影をつぶさに思い浮かべるのが、年々難儀になってくる。生まれ育った街並みを思い出せない日が来るなんて、昔は考えもしなかった。湿った潮風の感触はちっとも変わらないのに、ここから眺める景色の変わりようは、今でも奇異な感じがする。
 草むらに腰を下ろすと、胸ポケットから携帯を取り出す。画面を開けて、しばらく待つ。15年もののガラケーなので、スクリーンが灯るにもいちいち時間がかかる。バッテリーが弱っているのは確かだけど、接触もおかしい。携帯ショップに持ち込んだら、ずいぶん古い機種で修理も交換も無理ですねと、にべもなく言われた。普段用にはスマホに乗り換えて久しいから不便はないけれど、このガラケーは捨てられない。刺すような冬の空気に混じって、かすかに春の暖かみを運ぶ海風がそっと頬をかすめる。
草むらに腰を下ろすと、胸ポケットから携帯を取り出す。画面を開けて、しばらく待つ。15年もののガラケーなので、スクリーンが灯るにもいちいち時間がかかる。バッテリーが弱っているのは確かだけど、接触もおかしい。携帯ショップに持ち込んだら、ずいぶん古い機種で修理も交換も無理ですねと、にべもなく言われた。普段用にはスマホに乗り換えて久しいから不便はないけれど、このガラケーは捨てられない。刺すような冬の空気に混じって、かすかに春の暖かみを運ぶ海風がそっと頬をかすめる。
画面上にアイコンが出揃うのを辛抱強く待って、SMSアプリを立ち上げる。『大丈夫?これからそっち行く』幾度となく見返した最後の着信は、10年前のあの日で止まっている。あのときすぐに返信したけど、それきりレスはなかった。この丘の上でずっと待っていたけど、再会は叶わなかった。そのあといろいろなことがあって、海の見えない遠くの街で新しい仕事を見つけた。それでも毎月この日にはこの丘にやって来て同じように海を見つめ、草むらの同じ場所に座ってガラケーを開き、届くあてのないメールを出す。とりとめのない近況報告を書き連ねることもあれば、「どうして?」しか書けない日もあった。わざわざこの丘まで足を運んでくるのは、毎夏一緒に花火を見に来た思い出の場所だからでもあるけれど、本当の理由は別にある。
LINEじゃないから既読は付かないし(あの頃LINEはまだなかった)、もちろん返事が来るわけもない。宛先の番号はもう解約されているから送信エラーが返ってくるだけ、と誰かに言われたが、一度もエラーなんて戻ってこなかった。たぶん向こうの世界とつながる秘密の基地局が、丘の近くどこかに佇んでいるのだと思う。そこで目に見えないアンテナを天まで伸ばして、送ったメールを黙々と届けてくれる。そんなことはあり得ないと頭ではわかっているけど、心は自然にそう受け入れている。いま暮らす街で家からショートメールを送ろうとしたこともあるけれど、取り返しのつかない過ちのような気がして止めた。1時間半の道のりを独りでドライブし、海の見える丘に登ってガラケーの電源を入れるのが、毎月のささやかな儀式のようになった。
レスが来ないのはもちろん今でも寂しい。でもメールを書いているあいだだけ、ほんの少しだけど心が鎮まる。いくら年月が経ってもつらさが癒えることなんてないけれど、ずっとこぎ続けていないと倒れてしまう自転車のように、日々やるべきことを淡々とこなしていくしかない。初めは補助輪を外したばかりの子供みたいに転んで泣いてばかりだったけど、今はよろけつつも少しずつ前に進めるようになったよ、まだまだ自信はないけどね。そんなことをとりとめもなく綴って、送信ボタンを押す。空を見上げ、ゆっくり海の方へ流される雲の群れに見入る。ずっと上空を旋回していた鳶の声が、いつの間にか聞こえなくなっている。画面の時計を見ると思いのほか時間が経っていたことに気づき、ガラケーをパチンと畳む。すると、まるでその瞬間を待っていたかのように、携帯が手中でブルブルと鳴った。
ひどく驚いたせいで、携帯が手から滑り落ちる。慌ててつかみ取ろうと手を伸ばしたら逆に跳ね飛ばしてしまい、携帯は前方の草むらに着地し丘の斜面を転がり落ちていく。それを追って、自分も転がるように斜面を駆け下りる。このガラケーの番号を知っている人はもういない、少なくとも「こっち」の世界には。勢いのついた携帯は地面から突き出した石にぶつかり、ガツンと嫌な音を立ててようやく止まる。飛びつくようにガラケーを拾って開けると、新着一件を知らせるロゴが点いている。ウソみたいに指が震えて、うまく押せない。ようやく開封ボタンを押した瞬間、画面いっぱいに色とりどりの光が花火のように輝き、それきりフッと真っ暗になった。
呆然と携帯を見つめたまま、どれほど時間が経ったかわからない。われに返って、カバーを閉めたり開けたり、電源を入れたり切ったりする。いつもはそれで接触不良が治るのに、何度試しても画面は黒いままだ。よりによってなぜいま壊れるんだ?やり場のない怒りが頭の中を駆け巡る。やがて怒りが引いてくると、あまりの間の悪さに今度は場違いな笑いの衝動がこみ上げる。笑ったせいで舌の上にしょっぱい雫が流れ込んできて、自分がさっきから泣いていたことに初めて気づいた。涙のこびりついた顔に夕刻の冷気を感じて視線を上げると、水平線に接する空が濃紺のグラデーションに沈みはじめている。
すっかり日が落ちた帰路を運転しながら、携帯の画面で最後に煌めいた光のことをずっと考えている。着信を確認する前にガラケーの回路が飛んだと思っていたけど、そうじゃない。あのとき返事はちゃんと届いていた。いつもあの丘から二人で眺めていた花火の、あれは最後の一輪だったのだ。まだまだ自信はないけどって送ったから、背中をそっと押してくれたんだね。大丈夫、補助輪はなくても、たぶんもう一人でどこまでも進んで行ける。
東日本大震災から10年目を迎えた。真正面から向き合うにはあまりに重く、被災者でない私が下手に評論じみた随想を綴ると、何を書いても皮相的でウソっぽくなってしまう。そこで、どうせウソならいっそフィクションにしてしまおう、と思い立った。あの日から10年を耐え抜いた無数の人たちを想い、乏しい想像力を精一杯絞った拙い産物である。
 草むらに腰を下ろすと、胸ポケットから携帯を取り出す。画面を開けて、しばらく待つ。15年もののガラケーなので、スクリーンが灯るにもいちいち時間がかかる。バッテリーが弱っているのは確かだけど、接触もおかしい。携帯ショップに持ち込んだら、ずいぶん古い機種で修理も交換も無理ですねと、にべもなく言われた。普段用にはスマホに乗り換えて久しいから不便はないけれど、このガラケーは捨てられない。刺すような冬の空気に混じって、かすかに春の暖かみを運ぶ海風がそっと頬をかすめる。
草むらに腰を下ろすと、胸ポケットから携帯を取り出す。画面を開けて、しばらく待つ。15年もののガラケーなので、スクリーンが灯るにもいちいち時間がかかる。バッテリーが弱っているのは確かだけど、接触もおかしい。携帯ショップに持ち込んだら、ずいぶん古い機種で修理も交換も無理ですねと、にべもなく言われた。普段用にはスマホに乗り換えて久しいから不便はないけれど、このガラケーは捨てられない。刺すような冬の空気に混じって、かすかに春の暖かみを運ぶ海風がそっと頬をかすめる。画面上にアイコンが出揃うのを辛抱強く待って、SMSアプリを立ち上げる。『大丈夫?これからそっち行く』幾度となく見返した最後の着信は、10年前のあの日で止まっている。あのときすぐに返信したけど、それきりレスはなかった。この丘の上でずっと待っていたけど、再会は叶わなかった。そのあといろいろなことがあって、海の見えない遠くの街で新しい仕事を見つけた。それでも毎月この日にはこの丘にやって来て同じように海を見つめ、草むらの同じ場所に座ってガラケーを開き、届くあてのないメールを出す。とりとめのない近況報告を書き連ねることもあれば、「どうして?」しか書けない日もあった。わざわざこの丘まで足を運んでくるのは、毎夏一緒に花火を見に来た思い出の場所だからでもあるけれど、本当の理由は別にある。
LINEじゃないから既読は付かないし(あの頃LINEはまだなかった)、もちろん返事が来るわけもない。宛先の番号はもう解約されているから送信エラーが返ってくるだけ、と誰かに言われたが、一度もエラーなんて戻ってこなかった。たぶん向こうの世界とつながる秘密の基地局が、丘の近くどこかに佇んでいるのだと思う。そこで目に見えないアンテナを天まで伸ばして、送ったメールを黙々と届けてくれる。そんなことはあり得ないと頭ではわかっているけど、心は自然にそう受け入れている。いま暮らす街で家からショートメールを送ろうとしたこともあるけれど、取り返しのつかない過ちのような気がして止めた。1時間半の道のりを独りでドライブし、海の見える丘に登ってガラケーの電源を入れるのが、毎月のささやかな儀式のようになった。
レスが来ないのはもちろん今でも寂しい。でもメールを書いているあいだだけ、ほんの少しだけど心が鎮まる。いくら年月が経ってもつらさが癒えることなんてないけれど、ずっとこぎ続けていないと倒れてしまう自転車のように、日々やるべきことを淡々とこなしていくしかない。初めは補助輪を外したばかりの子供みたいに転んで泣いてばかりだったけど、今はよろけつつも少しずつ前に進めるようになったよ、まだまだ自信はないけどね。そんなことをとりとめもなく綴って、送信ボタンを押す。空を見上げ、ゆっくり海の方へ流される雲の群れに見入る。ずっと上空を旋回していた鳶の声が、いつの間にか聞こえなくなっている。画面の時計を見ると思いのほか時間が経っていたことに気づき、ガラケーをパチンと畳む。すると、まるでその瞬間を待っていたかのように、携帯が手中でブルブルと鳴った。
ひどく驚いたせいで、携帯が手から滑り落ちる。慌ててつかみ取ろうと手を伸ばしたら逆に跳ね飛ばしてしまい、携帯は前方の草むらに着地し丘の斜面を転がり落ちていく。それを追って、自分も転がるように斜面を駆け下りる。このガラケーの番号を知っている人はもういない、少なくとも「こっち」の世界には。勢いのついた携帯は地面から突き出した石にぶつかり、ガツンと嫌な音を立ててようやく止まる。飛びつくようにガラケーを拾って開けると、新着一件を知らせるロゴが点いている。ウソみたいに指が震えて、うまく押せない。ようやく開封ボタンを押した瞬間、画面いっぱいに色とりどりの光が花火のように輝き、それきりフッと真っ暗になった。
呆然と携帯を見つめたまま、どれほど時間が経ったかわからない。われに返って、カバーを閉めたり開けたり、電源を入れたり切ったりする。いつもはそれで接触不良が治るのに、何度試しても画面は黒いままだ。よりによってなぜいま壊れるんだ?やり場のない怒りが頭の中を駆け巡る。やがて怒りが引いてくると、あまりの間の悪さに今度は場違いな笑いの衝動がこみ上げる。笑ったせいで舌の上にしょっぱい雫が流れ込んできて、自分がさっきから泣いていたことに初めて気づいた。涙のこびりついた顔に夕刻の冷気を感じて視線を上げると、水平線に接する空が濃紺のグラデーションに沈みはじめている。
すっかり日が落ちた帰路を運転しながら、携帯の画面で最後に煌めいた光のことをずっと考えている。着信を確認する前にガラケーの回路が飛んだと思っていたけど、そうじゃない。あのとき返事はちゃんと届いていた。いつもあの丘から二人で眺めていた花火の、あれは最後の一輪だったのだ。まだまだ自信はないけどって送ったから、背中をそっと押してくれたんだね。大丈夫、補助輪はなくても、たぶんもう一人でどこまでも進んで行ける。
東日本大震災から10年目を迎えた。真正面から向き合うにはあまりに重く、被災者でない私が下手に評論じみた随想を綴ると、何を書いても皮相的でウソっぽくなってしまう。そこで、どうせウソならいっそフィクションにしてしまおう、と思い立った。あの日から10年を耐え抜いた無数の人たちを想い、乏しい想像力を精一杯絞った拙い産物である。
雛壇の楽屋にて [フィクション]
囃子(太鼓)「お前、聞いてないのか。今年は三密回避とかで、俺たち全員は雛壇に乗れないんだとさ。」
囃子(笛)「嫌な予感はしてたんだけどさ・・・。去年はどこの祭りも中止ばかりで仕事さっぱりだったし。でも、ひな祭りもダメ出しなんて・・・。」
囃子(小鼓)「鼓のぼくらは黙々と叩いてれば飛沫リスクがないから、出ていいらしいんだけど。でもパーカスだけでパコパコお囃子やっても、様にならないよね。」
囃子(太鼓)「俺たちの前を一列空けてもらえれば、笛もいけるんじゃないかと思ってさ。それとなくマネージャーに言ってみたんだけど、渋い顔されたよ。」
囃子(大皮鼓)「前の列って言えば、大臣二人か?右大臣はいいやつだけど、左大臣はちょっと偏屈だしな。」
囃子(笛)「あの左大臣にネチッと言われたよ。菱餅とか食い物が並んでいる目の前で唾飛ばすのか?ってさ・・・」
囃子(謡)「左大臣のじいさん、確かに口悪いけど、根は悪い人じゃないよ。俺は席が近いから、残った雛あられこっそりくれたこともあるし。」
囃子(大皮鼓)「要は食べ物くれるのが良い人ってことか。わかり易いやつだな。」
囃子(小鼓)「ぼくは、背後の官女たちのほうが苦手なんだけど。とくに真ん中の人、見るからにお局っぽくてさ。ぜったい陰で仕切ってるよね。」
囃子(太鼓)「三人官女もソーシャル・ディタンシングで二人にしろとか言われて、誰を外すかで相当揉めてるらしいぞ。どうなるか見ものだな。」
囃子(謡)「例年どおりに乗れるのは、最上段のカップルだけってこと?あ、噂をすれば・・・」
女雛「あら、5人で何コソコソ話してるの?」
囃子(太鼓)「これはこれはお姫様。ご機嫌も麗しく。」
女雛「もちろん、気分はいいわよ。今年はあいつとの間にアクリル板立ててくれるって言うし。」
囃子(小鼓)「あいつってお殿様ですか?嬉しいんですか、仕切りがある方が?」
女雛「あいつ、なんかキモいのよね。やたら話しかけてくるし、『お殿様とお姫様、仲睦まじいわねえ』とか誰かに言われたときなんて、調子に乗って手握ろうしてきたのよ。単にお仕事で並んでるだけなのに、勘違いしてるんじゃないかしら。」
囃子(太鼓)「そんなご苦労があったとは。うちらは、人員削減で困ってるんですよ。」
女雛「あら、生バンドのメンバーが欠けたら盛り上がらないわね。あたしからもマネージャーに言っておくわ。じゃあね。」
囃子(太鼓)「ありがとうございます。・・・さて、うちらもそろそろ出番だ。とりあえず3人でスタメンやるしかないが、もし5人集合の許可が出たら後から合流してくれ。」
囃子(謡)「いよいよか、腕が鳴るな。ん、いま3人って言った?笛とあと1人ベンチ組がいるってこと?」
囃子(大皮鼓)「謡、お前だよ。笛がダメなのに、ボーカルが出られるわけないじゃないか。」
囃子(謡)「え?え?聞いてないよ。俺もこの一年ほとんど仕事なかったから、久しぶりで嬉しくて、すごい張り切ってコソ練してきたのに。」
囃子(太鼓)「悪いな、いろいろ手を尽くしたんだが、当面どうしようも無い。では行くぞ。あ、これはこれはお殿様、一足お先に失礼します。」
男雛「よう、久しぶりだな。ところで見たか、愛しい姫とこの私を隔てるあの忌々しい透明板を。いくらコロナ禍とはいえ、ずいぶん無粋な計らいじゃないか。桃の節句といえば姫とこの私こそ・・・おいおい聞いてるか、そんな逃げるように出て行くなよ。おや、笛と謡、お前たちは出ないのか?」
囃子(笛)「(ため息)今年は管楽器と声楽はNGらしいです。」
男雛「それは気の毒なことだな。おお、そうだ!お前たちにあのアクリル板をくれてやろうか。そうすれば五人囃子揃って並ぶのを許されるかもしれんぞ。姫もあんな邪魔物は迷惑がっているに決まっている。」
囃子(笛)「えっと・・・有り難いお言葉ですが、私どもは自力で何とかいたしますので、どうかお気遣いなく。」
男雛「そうか。まあ、この私にできることがあれば、何でも言ってくれ。じゃあな。」
囃子(謡)「(ヒソヒソ声で)何で断るんだよ!せっかく渡りに船のチャンスだったのに。」
囃子(笛)「脳天気なやつだな。お姫様の身になってみろよ。」
囃子(謡)「みんな、お姫様びいきだな。俺は、お殿様がそんなひどい人だとは思わないけど。」
囃子(笛)「お前が殿様派とは知らなかったよ。何か恩義でもあるのか?」
囃子(謡)「恩義っていうか、普通にいい人だよ。ずっと欲しかった菱餅のピンク色のとこ、分けてくれたことあったし。」
2021-03-02 07:44





