10年問題 [科学・技術]
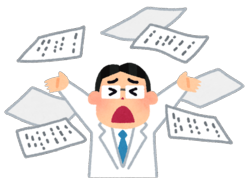 任期付き研究職の10年問題が議論になっている。有期雇用が5年(研究職は特例で10年)を超えると無期転換申込権を得る改正労働契約法が2013年に施行され、その当時から有期雇用であった研究者は10年目を迎える今年3月にその節目を迎える。しかし一部の研究機関ではその直前で契約を終了する「雇い止め」を行い、結果として相当数の任期付き研究者が職を失うと懸念されている。
任期付き研究職の10年問題が議論になっている。有期雇用が5年(研究職は特例で10年)を超えると無期転換申込権を得る改正労働契約法が2013年に施行され、その当時から有期雇用であった研究者は10年目を迎える今年3月にその節目を迎える。しかし一部の研究機関ではその直前で契約を終了する「雇い止め」を行い、結果として相当数の任期付き研究者が職を失うと懸念されている。雇い止めは、誰も得をしない。研究者当人は職を失い、雇用機関は貴重な研究戦力を失い、中長期的には日本全体にとって科学技術力の衰退を意味する。もともと有期労働者の雇用を守るのが法改正の趣旨だったが、大学や研究機関としては無期転換を認めたくても無い袖は振れない。任期付き研究者の雇用財源は科研費などの外部資金であり、資金に年限が切られているから原理的に無期雇用を保証できない。一方、国から大学に下りてくる基盤的経費は毎年1%ずつ減らされ続けているから、大学が自前で人件費を拡充する余裕はない。国の政策と立法が噛み合わない矛盾が、10年問題の本質である。
アメリカの大学に勤めていた時、初めの2年をポスドクとして過ごした後、同じ職場でリサーチサイエンティストに昇格した。これは外部資金による半無期雇用の研究職で、研究機関によって呼称は違うが米国では一般的なポジションである。「半無期」の意味は、安定的な雇用は保証されていないが決められた任期もないということだ。資金が途切れたら失職するリスクは契約に明記されているが(契約時に説明してくれた事務担当者から「私も同じ立場だし普通のことよ」と言われた)、ボスや自分自身の外部資金をつないで人件費を賄い続けられる限り、ポストが継続的に与えられる。もちろん、10年後に問答無用で追い出されるようなことはない。
このように米国の研究現場には有期でも無期でもないグレーゾーンで働く無数の研究者がいて、研究の生産性に少なからぬ貢献を果たしている。対して日本はというと、終身雇用を指向する文化が今なお根強いせいなのか、半無期雇用システムがあまり歓迎されていない気配がある。その空気感がおそらく10年前の労働契約法改正の背景にあった。
研究費の規模とか、外部資金で自分自身の給与が捻出できる慣習など、日米間にはいろいろ制度的な違いがある。アメリカの仕組みがそのまま日本で通用するわけではないが、少なくとも10年縛りの弊害は明らかだから、早急に労働契約法を再改正したほうがいいんじゃないか。



