オッペンハイマー:映画編 [映画・漫画]
クリストファー・ノーラン監督の映画『オッペンハイマー』が日本で公開され、ようやく待望の大作を観る機会を得た。この作品に関しては、「広島と長崎の惨禍が描かれていないのがけしからん」という論評を時折り耳にするが、いささか的外れな批判である。被爆国目線で何か言っておくのが日本人の見識ということかもしれないが、映画はあくまでオッペンハイマーの半生を彼自身の内面に照らして描いたフィクションであり、原爆開発のドキュメンタリーではない。
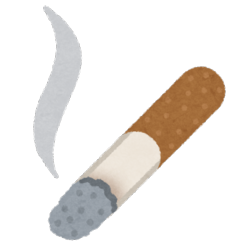 主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
映画の原案となった伝記本を読むと、内面が複雑に揺れ一筋縄では読み解き難いオッペンハイマー像が浮かび上がる(原著編で書いた)。映画『オッペンハイマー』はそんな彼の人物像を丁寧に再構築する。原爆開発を成功に導いた天才科学者が後に罪の意識から反核思想に転向する、といった直線的なヒューマンドラマでは全くない。象徴的なのは、原爆投下成功の報せに沸くロスアラモスの研究所で、オッペンハイマーが職場の同僚たちから拍手喝采で称えられる場面だ。歓喜に足を踏み鳴らす喧騒に迎えられ演壇に立った彼は、狂喜する聴衆の中に熱線が焼き尽くす被爆者の幻影を見る。以後オッペンハイマーにとって、英雄の栄光は破壊神の汚名と不可分になった。
オッペンハイマーが熱線の幻を見るシーンが、終盤にもう一度だけ登場する。原子力委員会の聴聞会で、22万人を超える広島と長崎の甚大な犠牲の事実を突きつけられ、彼が良心の呵責を認めた場面だ。ならばなぜ原爆の実戦使用に反対しなかったのか? 原爆を容認しながらなぜ戦後水爆開発に抵抗し続けたのか? 畳みかけられる詰問にオッペンハイマーは必死で正当化を試みるが、己の矛盾に心のどこかで気付いている。ひどく混乱した彼の頭中で観衆の踏み鳴らす靴音がフラッシュバックし、聴聞会の小さな部屋を眩い閃光が貫く。場面は上院公聴会の時間軸と目まぐるしく交差し、オッペンハイマーの偽善を罵るストロースの怒号がかぶる。史実の舞台装置を借りてオッペンハイマーを苛む心の軋みを鮮やかに可視化した、息を呑むクライマックスである。
オッペンハイマーを賞賛も非難もせず、彼の葛藤と矛盾を渾然一体のまま白日の下に晒すことが、この映画の着地点だ。幕切れの直前、ロスアラモスを勇退しプリンストンの高等研究所長に招かれたばかりのオッペンハイマーがアインシュタインと交わした会話が明かされる。当時のアインシュタインはすでに、本人が創始に関わった量子力学に背を向ける孤高の人であった。アインシュタインは、自ら生み出した魔物を持て余すオッペンハイマーに同じ運命の影を嗅ぎ取り、のちに訪れる試練を仄めかす暗い予言を告げる。この会話自体はおそらくフィクションだが、三時間にわたる長尺に深い余韻を残す見事なエンディングだ。
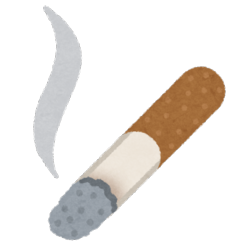 主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。
主役から脇役まで俳優陣の充実ぶりは今さら言うまでもないが(数分しか出番のないクセ強めのトルーマン大統領役が、まさかのゲイリー・オールドマンだったりとか)、史実をなぞりながら随所にフィクションを忍ばせる脚本の手練が際立っている。バークレー在籍時からマンハッタン計画までのオッペンハイマー最盛期、事実無根のソ連スパイ疑惑で追い詰められる原子力委員会の聴聞、その裏で暗躍したストロースの入閣可否を問う上院の公聴会、という主に3つの時間軸を、物語は縦横無尽に行き来する。歴史的背景の予備知識なしに観ると、迷子になるかもしれない。映画の原案となった伝記本を読むと、内面が複雑に揺れ一筋縄では読み解き難いオッペンハイマー像が浮かび上がる(原著編で書いた)。映画『オッペンハイマー』はそんな彼の人物像を丁寧に再構築する。原爆開発を成功に導いた天才科学者が後に罪の意識から反核思想に転向する、といった直線的なヒューマンドラマでは全くない。象徴的なのは、原爆投下成功の報せに沸くロスアラモスの研究所で、オッペンハイマーが職場の同僚たちから拍手喝采で称えられる場面だ。歓喜に足を踏み鳴らす喧騒に迎えられ演壇に立った彼は、狂喜する聴衆の中に熱線が焼き尽くす被爆者の幻影を見る。以後オッペンハイマーにとって、英雄の栄光は破壊神の汚名と不可分になった。
オッペンハイマーが熱線の幻を見るシーンが、終盤にもう一度だけ登場する。原子力委員会の聴聞会で、22万人を超える広島と長崎の甚大な犠牲の事実を突きつけられ、彼が良心の呵責を認めた場面だ。ならばなぜ原爆の実戦使用に反対しなかったのか? 原爆を容認しながらなぜ戦後水爆開発に抵抗し続けたのか? 畳みかけられる詰問にオッペンハイマーは必死で正当化を試みるが、己の矛盾に心のどこかで気付いている。ひどく混乱した彼の頭中で観衆の踏み鳴らす靴音がフラッシュバックし、聴聞会の小さな部屋を眩い閃光が貫く。場面は上院公聴会の時間軸と目まぐるしく交差し、オッペンハイマーの偽善を罵るストロースの怒号がかぶる。史実の舞台装置を借りてオッペンハイマーを苛む心の軋みを鮮やかに可視化した、息を呑むクライマックスである。
オッペンハイマーを賞賛も非難もせず、彼の葛藤と矛盾を渾然一体のまま白日の下に晒すことが、この映画の着地点だ。幕切れの直前、ロスアラモスを勇退しプリンストンの高等研究所長に招かれたばかりのオッペンハイマーがアインシュタインと交わした会話が明かされる。当時のアインシュタインはすでに、本人が創始に関わった量子力学に背を向ける孤高の人であった。アインシュタインは、自ら生み出した魔物を持て余すオッペンハイマーに同じ運命の影を嗅ぎ取り、のちに訪れる試練を仄めかす暗い予言を告げる。この会話自体はおそらくフィクションだが、三時間にわたる長尺に深い余韻を残す見事なエンディングだ。



