火星人との付き合い方 [文学]
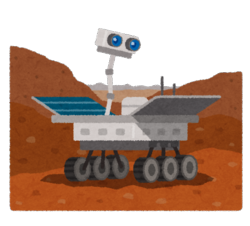 NASA JPLの火星探査機Perseverance Roverが、無事現地に着陸した。着陸船からローバーが紐で吊るされそろりそろりと降下される様子は、まるでドローンが宅配便を送り届けているかのようだ。前回の探査機Curiosityから採用された手法のようだが、ちょっと昔の火星ミッション(Mars Pathfinder)はエアバッグにローバーを包んで突き落とし、手荒くバウンドさせていた記憶がある。もし火星人がその様子に出くわしていたら、地球も文明が進んで少しは洗練された着陸ができるようになったか、と感心したかもしれない。
NASA JPLの火星探査機Perseverance Roverが、無事現地に着陸した。着陸船からローバーが紐で吊るされそろりそろりと降下される様子は、まるでドローンが宅配便を送り届けているかのようだ。前回の探査機Curiosityから採用された手法のようだが、ちょっと昔の火星ミッション(Mars Pathfinder)はエアバッグにローバーを包んで突き落とし、手荒くバウンドさせていた記憶がある。もし火星人がその様子に出くわしていたら、地球も文明が進んで少しは洗練された着陸ができるようになったか、と感心したかもしれない。H.G.ウェルズが『宇宙戦争』を発表したのは1898年、当時は人類がいつか火星に探査機を送り込むなど想像もしていなかったかもしれない。代わりに火星人の方が出向いてきて、地球の侵略を試みた。圧倒的な技術力を誇る火星人の襲撃に人類は為すすべもなかったが、最後は火星人が地球の伝染病にやられてコロリと全滅する。『宇宙戦争』の原題は『The War of the Worlds』で、直訳すれば世界と世界の戦争ということになる。ウェルズは地球対火星という構図に加え、ミクロとマクロの生態系が交える世界間決戦という寓意も重ねたかったのかも知れない。コロナとの付き合い方を暗中模索する今、ウェルズの火星人が舐めた辛酸を、今度は私たちが味わう羽目になっている。
『宇宙戦争』からおよそ半世紀後、レイ・ブラッドベリの代表作『火星年代記(Martian Chronicles)』が誕生する。短編集のようであり一大叙事詩のようでもあり、皮肉とユーモアと詩情が交叉する不可思議な魅力に溢れた作品だ。宇宙開発時代の黎明期に書かれたこの物語では、地球の文明は火星に人類を送り込むまでに発展している。しかし一大スペクタクルが繰り広げられるウェルズの『宇宙戦争』に比べ、ブラッドベリが描くファースト・コンタクトは拍子抜けするほどあっけない。
『火星年代記』の幕開けは、倦怠期の火星人夫婦が織りなす冷めた家庭劇だ。夢の中で王子様のような地球人飛行士の来訪を察知し胸が高鳴る妻と、無関心を装いながらそれが面白くない夫。居ても立っても居られない妻を家に置いて、夫が銃器を片手に一人猟に出る。やがて遠くから銃声が聞こえ、妻が待ち望んだ地球人の痕跡はテレパシーから突如途絶える。SF版レイモンド・カーヴァーとでも言えそうな夫婦の乾いた会話劇が、記念すべき人類の第一次先遣隊を見舞った悲運を暗示する。続く第二次先遣隊は地球からの使者と誰からも真に受けてもらえず、精神病棟に送られた挙句やはりあっさりと片付けられてしまう。
しかし、程なく火星人は自ずと全滅する。『宇宙戦争』の結末と同じく、彼らは訪問者が持ち込んだウイルスに無力だった。ただウェルズの火星人が悪意に満ちた侵略者であったのと対照的に、ブラッドベリの火星人にとっては地球人のほうが侵入者だ。かつて新大陸の先住民が欧州人の持ち込んだ伝染病で苦しんだように、『火星年代記』は無邪気に火星に押し寄せる地球人を植民地主義の再興として描く。
1970年代に人類が送った探査機が初めて火星に着陸し、そこが知的生命体など一切存在しない不毛の荒野であることを確認した。それから半世紀近くを経た現在、例え原始的な単細胞生物のカケラであるにせよ、私たちは火星に生命の痕跡を見つけ出す可能性を諦めていない。ウェルズやブラッドベリが危惧したような火星人との不幸な邂逅は杞憂だったが、人類は宇宙の果てしない闇にポツリと佇む孤独がどうしても耐えられないようである。



