エアロかアエロか [語学]
 エアロビやエアロゾルは元の英語ではaerobics/aerosolと綴り、字面だけ見ると「ア」と「エ」の順序がひっくり返っている。しかし英語圏の人が発音すると、私たちの耳には確かに「エアロビクス」と「エアロゾル」のように聞こえる。aeroはairと同じ語源で、空気や風などに関連する接頭語だ。「NASA」のA(2つのうち初めの方)はAeronautics(航空)の頭文字で、発音はこれも綴りと裏腹に「エアロノティクス」になる。視覚と聴覚情報が逆転していて、どことなく気持ち悪い。
エアロビやエアロゾルは元の英語ではaerobics/aerosolと綴り、字面だけ見ると「ア」と「エ」の順序がひっくり返っている。しかし英語圏の人が発音すると、私たちの耳には確かに「エアロビクス」と「エアロゾル」のように聞こえる。aeroはairと同じ語源で、空気や風などに関連する接頭語だ。「NASA」のA(2つのうち初めの方)はAeronautics(航空)の頭文字で、発音はこれも綴りと裏腹に「エアロノティクス」になる。視覚と聴覚情報が逆転していて、どことなく気持ち悪い。必ずしも日本人の耳の問題ではなくて、英語特有の癖と言ったほうがいい。なぜなら仏語では字面どおり「アエロ」であって、そう発音させるためわざわざアクサンを付けて「aéro」と綴る。例えばaéroport(空港)はアエロポールだ。スイスの老舗時計ブランドAerowatchは、(watchが英語なのに)和名は仏語流にアエロと呼ばれる。エアロとアエロ、本当はどちらが正しいのか?
なぜ今この話題かというと、英語の発音がエアロである理由がさっき突然閃いたからだ。Aとeをアとエだと思いこんでいたのが、そもそもの間違いなのである。aesthetics(美学)をエステティクスと言うように、英語の「ae」はふつう二文字まとめて「エ」と発音する(ちなみに日本で言う「エステ」はたぶん仏語起源で、英語のaestheticに美容関係の含意はない)。従って「a・e・ro=ア・エ・ロ」とはならずに、「ae・ro=エ・アロ」なのである。アはアール(r)からきているのだ。冒頭のaeからrに移行する際、舌を巻き込みながら発せられる一瞬の母音が、私たちの耳には「ア」のように聞こえる。フランス語はrの発音に舌を巻かないから、このアが忍び込む余地がない。
似たような「母音からのr」で始まる英単語の例として、errorがある。でもカタカナ表記でerrorは常にエラーであって、エアラーとは書かない。これに準ずるなら、aerobicsとaeronauticsは本来エロビクス・エロノティクスと表記すべきだ。でも「今日これからエロビ教室なの」では、口に出すには響きがあまりに艶っぽい。私たちの耳がaeroをエ「ア」ロと聞きとっている深層には、日本人の奥ゆかしい美意識もちょっと手伝っているかも知れない。
「主食」は英語で? [語学]
 「主食」は英語でなんと言うの?と尋ねられ、うまい訳語が思い浮かばなかった。一見すると語感が近そうな「main dish」は、コース料理等の主菜のことなので意味が違う。日本人の主食は何かと聞かれれば大抵の人は米ですと答えると思うが、メインディッシュに皿いっぱい白米が盛られて出されたりはしない。考えてみると、英語圏の人たちにとっての主食は何か、パンかもしれないしイモかもしれないが、コメに匹敵するほど自明な鉄板食品が思い至らない。たぶん、主食という概念がそもそも希薄なのではないか。辞書的に訳すならstaple foodだそうだが、日常会話であまり耳にしない言葉だ。この話題は調べてみるとネットのあちこちに転がっているので、同じく疑問に思っている人は多いらしい。
「主食」は英語でなんと言うの?と尋ねられ、うまい訳語が思い浮かばなかった。一見すると語感が近そうな「main dish」は、コース料理等の主菜のことなので意味が違う。日本人の主食は何かと聞かれれば大抵の人は米ですと答えると思うが、メインディッシュに皿いっぱい白米が盛られて出されたりはしない。考えてみると、英語圏の人たちにとっての主食は何か、パンかもしれないしイモかもしれないが、コメに匹敵するほど自明な鉄板食品が思い至らない。たぶん、主食という概念がそもそも希薄なのではないか。辞書的に訳すならstaple foodだそうだが、日常会話であまり耳にしない言葉だ。この話題は調べてみるとネットのあちこちに転がっているので、同じく疑問に思っている人は多いらしい。主食の対語は副食(おかず)だが、おかずの英訳もまた厄介だ。「side dish」と訳す翻訳エンジンもあるが、主食がmain dishでない以上これも正しくない。side dishは「付け合せ」であっておかずではない。ステーキがメインディッシュなら、脇に控えるポテトがサイドディッシュだ。同じ炭水化物どうし、白米がポテトの立ち位置ということなら、主食のライスがside dishでおかずがmain dishということになる。ますますよくわからない。
和食においてご飯は至高の地位にある。ホクホクに炊きあがった白飯の程よい歯ごたえとほのかな甘み、決して出しゃばらずどんなおかずとも相性が良い慎ましさ、しかしそこに無いと絶対に困る食卓の要。米は農家が八十八の手間を惜しまず育てた賜物、などと言われると茶碗のむこうに後光が差して見える。こだわりの強さではフランス人にとってのバゲットも相当なものだが、フランス語にもたぶん日本の「主食」に相当する概念はない。フランスパンはあくまで前菜やスープやメインディッシュのサポートだ。一汁一菜という言葉に象徴されるように、ご飯とおかずが対等に渡り合う緊張関係は和食独特の美学ではないか。
おかずがないと物足りないが、おかずだけでは成り立たない。主役であって脇役でもあり、そこにいるのが当たり前ながらひときわ格別の存在でもある。その全てを凝縮し表現した言葉が、日本の「主食」だ。一言で翻訳できるわけがない。
Embarrassmentは「恥」か? [語学]
バイデン次期大統領が、敗北を認めず抵抗するトランプ氏の言動を「恥ずべきこと/恥ずかしいこと」と述べたと複数の日本メディアが報じている。しかし、実際にバイデン氏が会見で言ったのは「I just think it's an embarrassment.」である。「困った話だ」とか「厄介なことだね」とでも訳すほうが自然ではないだろうか。I'm embarrassed.を「恥ずかしい」と訳すことがあるが、これは例えば男性が間違えて女性用トイレに入りそうになった、みたいなシチュエーションの「恥ずかしい」である(トイレの話は昔アメリカ人が私にembarrassedの意味を解説してくれたとき実際使った喩え)。「恥ずべき」と言うならたぶんshamefulであって、embarrassmentにそこまで強い糾弾のニュアンスはない。
ついでにもう一つ。ポンペオ国務長官がバイデン勝利を認めない発言をした、という報道があった。トランプ政権の中枢にいる人なので不思議ではないが、その会見の様子が少し面白い。政権移行が滞るのは安全保障上どうなのか?と記者に聞かれて、「第二期トランプ政権への移行は順調であろう」と確かに言った。ただしそれに続いて長々と国務長官が答えた本題は、行政機構は機能しており「1月20日正午すぎに執務室にいるであろう大統領」にとって何ら問題はない、票の集計は公正に行われなければならない、といった一般論だ。トランプ発言を擁護しているようでもあるし、原則論に徹してあからさまな援護射撃は巧みに避けているようでもある。
冒頭の「第二期トランプ」発言は、実はジョークだったのではという観測もある。確かにこれを言った直後、ポンペオ氏は会場の反応を確かめるように一瞬の間を取り、ニヤリと笑っている。ポンペオ氏はかつて金正恩と会談した際、「あなたがCIA長官時代に私を暗殺しようとしたというのは本当か」と聞かれ「ええ、今でもそのつもりですよ」と答えたと噂されている。もともとヤバめの冗談がお好きな人のようである。
ついでにもう一つ。ポンペオ国務長官がバイデン勝利を認めない発言をした、という報道があった。トランプ政権の中枢にいる人なので不思議ではないが、その会見の様子が少し面白い。政権移行が滞るのは安全保障上どうなのか?と記者に聞かれて、「第二期トランプ政権への移行は順調であろう」と確かに言った。ただしそれに続いて長々と国務長官が答えた本題は、行政機構は機能しており「1月20日正午すぎに執務室にいるであろう大統領」にとって何ら問題はない、票の集計は公正に行われなければならない、といった一般論だ。トランプ発言を擁護しているようでもあるし、原則論に徹してあからさまな援護射撃は巧みに避けているようでもある。
冒頭の「第二期トランプ」発言は、実はジョークだったのではという観測もある。確かにこれを言った直後、ポンペオ氏は会場の反応を確かめるように一瞬の間を取り、ニヤリと笑っている。ポンペオ氏はかつて金正恩と会談した際、「あなたがCIA長官時代に私を暗殺しようとしたというのは本当か」と聞かれ「ええ、今でもそのつもりですよ」と答えたと噂されている。もともとヤバめの冗談がお好きな人のようである。
天気のうつろい、時の流れ [語学]
今年は7月にやたらと雨が降り、8月に入ると今度はずっと暑い。日照不足の冷夏では農作物が不作になり、かんかん照りの酷暑では熱中症の危険が増す。気温が高すぎても低すぎても、何かと厄介だ。
temperature(温度)という言葉は、気質や気候が穏やかで程よいことを示すtemperateとよく似ている。熱すぎる風呂を冷水で埋めるように、熱はおのずと高温と低温の差を打ち消すように流れ、中程の温度で熱的な平衡に達する。人の気分や気質を表すtemperも、同じ語源のことばだ。もともとこれらの語は、両極端が混じり合って中和し中庸を指向する語感を持っていたのだろうか。だが今年の夏のように気温は絶えず上下に揺らぎ続け、コロナ禍のなか人の気分は浮き沈みを繰り返す。中庸は永遠に到達できない理想郷で、だからこそ価値がある美徳なのかも知れない。
tempで始まる単語は、temperatureやtemperの他にもたくさんある。temporal(時間の)とかtemporary(一時的な)など、時の概念を表す言葉が多い。音楽用語のtempoもその一つだ。ラテン語で時間を意味するtempusが語源だそうで、現代フランス語でも時間は「temps」と言う。tempusには時間の他に季節の意味もあり、初めの季節を意味するle premier tempsがle printemps(春)になった。
 面白いことに、フランス語の天気に相当する語は、時間と同じtempsである。一見全く違う概念に、どうして同一の言葉を当てたのか?ラテン語で時間と季節を同じ単語で表現することから想像するに、時計を持たなかった古代の人々は、自然の営みが時間の変化を知る手掛かりだったのではないか。だから、日々体感する気象に時の流れを肌で感じていたのかも知れない。青空にもくもくと湧き起こる入道雲、夕立の予感を乗せて吹き付ける冷たい突風、そして突如叩きつける大粒の雨。嵐を意味する英語のtempest(仏語のtempête)の中にも、はっきり「時間軸」が刻印されている。
面白いことに、フランス語の天気に相当する語は、時間と同じtempsである。一見全く違う概念に、どうして同一の言葉を当てたのか?ラテン語で時間と季節を同じ単語で表現することから想像するに、時計を持たなかった古代の人々は、自然の営みが時間の変化を知る手掛かりだったのではないか。だから、日々体感する気象に時の流れを肌で感じていたのかも知れない。青空にもくもくと湧き起こる入道雲、夕立の予感を乗せて吹き付ける冷たい突風、そして突如叩きつける大粒の雨。嵐を意味する英語のtempest(仏語のtempête)の中にも、はっきり「時間軸」が刻印されている。
日々の天気を彩る陽射しや雨は、二重の意味で天の恵みである。降り注ぐ光と水は地上の生命を遍く育み、その移ろいが人間に時間の意味を教えた。
temperature(温度)という言葉は、気質や気候が穏やかで程よいことを示すtemperateとよく似ている。熱すぎる風呂を冷水で埋めるように、熱はおのずと高温と低温の差を打ち消すように流れ、中程の温度で熱的な平衡に達する。人の気分や気質を表すtemperも、同じ語源のことばだ。もともとこれらの語は、両極端が混じり合って中和し中庸を指向する語感を持っていたのだろうか。だが今年の夏のように気温は絶えず上下に揺らぎ続け、コロナ禍のなか人の気分は浮き沈みを繰り返す。中庸は永遠に到達できない理想郷で、だからこそ価値がある美徳なのかも知れない。
tempで始まる単語は、temperatureやtemperの他にもたくさんある。temporal(時間の)とかtemporary(一時的な)など、時の概念を表す言葉が多い。音楽用語のtempoもその一つだ。ラテン語で時間を意味するtempusが語源だそうで、現代フランス語でも時間は「temps」と言う。tempusには時間の他に季節の意味もあり、初めの季節を意味するle premier tempsがle printemps(春)になった。
 面白いことに、フランス語の天気に相当する語は、時間と同じtempsである。一見全く違う概念に、どうして同一の言葉を当てたのか?ラテン語で時間と季節を同じ単語で表現することから想像するに、時計を持たなかった古代の人々は、自然の営みが時間の変化を知る手掛かりだったのではないか。だから、日々体感する気象に時の流れを肌で感じていたのかも知れない。青空にもくもくと湧き起こる入道雲、夕立の予感を乗せて吹き付ける冷たい突風、そして突如叩きつける大粒の雨。嵐を意味する英語のtempest(仏語のtempête)の中にも、はっきり「時間軸」が刻印されている。
面白いことに、フランス語の天気に相当する語は、時間と同じtempsである。一見全く違う概念に、どうして同一の言葉を当てたのか?ラテン語で時間と季節を同じ単語で表現することから想像するに、時計を持たなかった古代の人々は、自然の営みが時間の変化を知る手掛かりだったのではないか。だから、日々体感する気象に時の流れを肌で感じていたのかも知れない。青空にもくもくと湧き起こる入道雲、夕立の予感を乗せて吹き付ける冷たい突風、そして突如叩きつける大粒の雨。嵐を意味する英語のtempest(仏語のtempête)の中にも、はっきり「時間軸」が刻印されている。日々の天気を彩る陽射しや雨は、二重の意味で天の恵みである。降り注ぐ光と水は地上の生命を遍く育み、その移ろいが人間に時間の意味を教えた。
番外編:「民度」を訳せるか [語学]
麻生財務相の発言がまた物議を醸している。日本のコロナ死亡率が低い理由を問われて「おたくとうちの国とは、国民の民度のレベルが違うんだ」と持論を展開したらしい。その分析力の稚拙さはさておき、「民度」の意味が外国の人にうまく伝わっただろうか?麻生氏が英語で喋ったのか通訳がついていたのか詳しい状況は不明だが、民度を何と訳したのかちょっと興味をそそられる。もしくは相手が日本語に堪能だったのかもしれないが、民度という日常あまり使われない言葉を正確に理解している非ネイティブ日本語話者は少ないのではないか。麻生大臣によれば相手は皆絶句したとのことだが、単に「ミンド」の意味がピンと来ず、答えようがなかっただけかも知れない。
 この一件を伝える英文メディアも、民度の訳し方に苦心しているようである。ざっと見る限り、the level of social manners(共同通信)、cultural standards(テレグラフ、ジャパンタイムズ)、または直訳調でthe level of people(朝日新聞)など様々だ。確かにこれで辞書的な意味はわかるが、この言葉が時に孕む差別的なニュアンスを語らなければ、なぜ麻生節が国内で批判されたのか理解されないのではないか。
この一件を伝える英文メディアも、民度の訳し方に苦心しているようである。ざっと見る限り、the level of social manners(共同通信)、cultural standards(テレグラフ、ジャパンタイムズ)、または直訳調でthe level of people(朝日新聞)など様々だ。確かにこれで辞書的な意味はわかるが、この言葉が時に孕む差別的なニュアンスを語らなければ、なぜ麻生節が国内で批判されたのか理解されないのではないか。
都知事時代の石原慎太郎氏が、某近隣国を指して「民度が低い」と放言したことを思い出した。その物言いに侮蔑的な匂いを感じなかった人はいないだろう。言葉自体に本来棘はないと思うが、その一言を吐き捨てる人の思考回路が短絡的だと、たちまち語感が品位を失う。民度という言葉は、それを使う本人の民度が露呈するリトマス紙である。
 この一件を伝える英文メディアも、民度の訳し方に苦心しているようである。ざっと見る限り、the level of social manners(共同通信)、cultural standards(テレグラフ、ジャパンタイムズ)、または直訳調でthe level of people(朝日新聞)など様々だ。確かにこれで辞書的な意味はわかるが、この言葉が時に孕む差別的なニュアンスを語らなければ、なぜ麻生節が国内で批判されたのか理解されないのではないか。
この一件を伝える英文メディアも、民度の訳し方に苦心しているようである。ざっと見る限り、the level of social manners(共同通信)、cultural standards(テレグラフ、ジャパンタイムズ)、または直訳調でthe level of people(朝日新聞)など様々だ。確かにこれで辞書的な意味はわかるが、この言葉が時に孕む差別的なニュアンスを語らなければ、なぜ麻生節が国内で批判されたのか理解されないのではないか。都知事時代の石原慎太郎氏が、某近隣国を指して「民度が低い」と放言したことを思い出した。その物言いに侮蔑的な匂いを感じなかった人はいないだろう。言葉自体に本来棘はないと思うが、その一言を吐き捨てる人の思考回路が短絡的だと、たちまち語感が品位を失う。民度という言葉は、それを使う本人の民度が露呈するリトマス紙である。
小泉進次郎の話術と英語力 [語学]
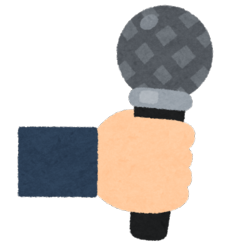 日本の政治家はスピーチが苦手な人が多い。話している時間の半分以上が「あー」とか「えー」で埋まる演説を耳にすると、だれか喋り方を教えてあげる人は周りにいなかったのかと少し気の毒になる。言葉を探してつい出てしまう「えーっと」の類は言語学でフィラー(Filler)と呼ばれ、スピーチでは極力避けるべきとその筋の指南書に必ず書いてある。安倍首相は歴代総理の中では弁舌が滑らかな方と思うが、「・・・と、このように思うわけであります」といった無駄な言い回しが多い。フィラー同様、情報量の薄い文言がスピーチの合間をつなぐと聞き手の集中力が削がれ、肝心な話の要点が記憶に残らない。
日本の政治家はスピーチが苦手な人が多い。話している時間の半分以上が「あー」とか「えー」で埋まる演説を耳にすると、だれか喋り方を教えてあげる人は周りにいなかったのかと少し気の毒になる。言葉を探してつい出てしまう「えーっと」の類は言語学でフィラー(Filler)と呼ばれ、スピーチでは極力避けるべきとその筋の指南書に必ず書いてある。安倍首相は歴代総理の中では弁舌が滑らかな方と思うが、「・・・と、このように思うわけであります」といった無駄な言い回しが多い。フィラー同様、情報量の薄い文言がスピーチの合間をつなぐと聞き手の集中力が削がれ、肝心な話の要点が記憶に残らない。その一方ピカいち演説力が光っていたのが小泉純一郎元首相だ。この人の言葉は短くて力強い。そしてフィラーにほとんど頼らない。「あー」や「えー」に代わり、ここぞという時この人はフッと沈黙する。すると、何を言い出すんだ?という期待が高まり、場の緊張感がぐっと凝縮する。そして「感動した!」と一言吐き出されるのを聞いて、ああそうか感動したのか、と大したことでなくても妙に納得してしまう。言うまでもないが、スピーチが上手いことと話の深度は全く関係ない。「私の内閣の方針に反対する勢力、これはすべて抵抗勢力だ」とかやんちゃな発言にも事欠かなかったが、言葉のインパクトを巧みにに利用する勘の良さでは最近の首相の中でダントツであろう(かつては吉田茂とか田中角栄とか味のある名言を残した曲者がいたが)。
最近なにかと注目を浴びる小泉進次郎環境相が、父の話術を忠実に受け継いで見事である。この人も沈黙の使い方が上手く、簡潔な言葉を淀みなく吐き出しカッコいい。あとから字面をなぞると結局何を言いたいのかよくわからない発言も多く、「もっともらしくて無意味」な進次郎風ネタを投稿する大喜利がネットで盛り上がっているらしい。とはいえ公人はネタにされてナンボ、耳目を集める吸引力に優れていることに変わりなく、発言内容はさておき話術ではどの政治家もこのくらいの水準を目指して欲しい。
先の国連気候行動サミットでも、小泉環境相の発言が注目された。地球環境問題が醸し出す堅苦しさを嘆いて"It’s gotta be fun, it’s gotta be cool, it’s gotta be sexy too."と言い放ったあれである。これは進次郎節が英語でも遺憾なく発揮されるという感動的な発見であった。とはいえ国を代表して発言する以上gotta-be的なタメぐち英語よりもう少し正調な言葉遣いを聞きたかった、と言うと少し要求が過ぎるか。語学の格調に関しては、同じサミット中にトランプ大統領の背中を口をへの字にして睨み付けたスウェーデンの少女がなかなかの貫禄で、感極まりつつ率直な思いをシンプルながら美しい英語で吐露した彼女は近寄りがたい凄みにあふれていた("How dare you"とか芝居じみた啖呵はともかく)。
オランダやスウェーデンは、ネイティブ並に英語を操る人がやたらと多いことで知られている。彼らの母国語がそもそも英語に近いせいでもあるが、同じゲルマン語派のドイツ語話者はインテリでも英語が流暢な人ばかりではない。ラテン系言語圏のフランスやイタリアではなおそうだ。オランダはテレビをつければBBCなど英語の番組が吹き替え抜きで流れているので、幼い頃から当たり前のように英語が耳に入ってくる。意地悪く言えばオランダ語だけであらゆる番組を制作する経済性が見込めないわけで、自国言語のマーケットが小さい国はその隙間を埋めるように英語が自然と生活のなかに染み込んでいるのだ。逆に、文化的影響力の強い言語を持つドイツやフランスは、観光地を除けば普段の暮らしの中で生の英語が聞こえてくる余地は少ない。その点で日本も事情は同じである。スウェーデン語が本国とその周辺でしか通用しないように日本語もマーケットの限られた言語かと思いきや、日本語を母国語とする人口はドイツ語やフランス語のそれより多く、その市場規模は侮りがたい。日本国内で暮らす限り、外国語を知らないとアクセスできないコンテンツにはほとんどお目にかからない。
日本語の地産地消で高度な文化圏が成立しているのは誇らしいことであるが、その結果私たちがふだん英語に触れる機会は学校の中だけになった。中学以降(今では小学校から)綿々と授業で絞られるのに、英語に苦手意識を持つ日本人は多い(TOEFLの国別ランキングで日本はアジア内最下位クラス常連である)。以前別のところでも書いたが、「テストで減点されない英語」を指向した教育に疲れ果てた私たちは、自発的なコミュニケーションのための英語を会得する意欲を失ってしまったのである。その意味では、タメぐちでも気軽に初対面の外国人と話せる進次郎英語(と社交性)は、むしろ日本人が目指すべき姿を体現しているのかもしれない。他愛もない軽口を交わすだけで「こいつ意外にいいヤツだな」と打ち解けることもあるし、それだけで世界への眼差しが少し優しくなったりするものである。



